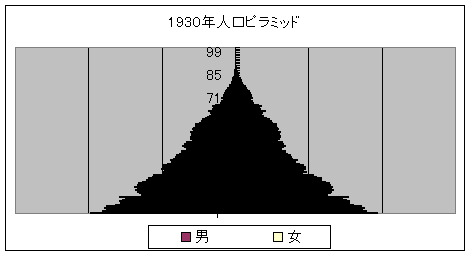
�q���[�}���E���\�[�X�iHRE704�j4�N���W�b�g
�R���v���C�A���X�ƃ��[�_�[�V�b�v
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
�嚠 ��
���̃R�[�X���[�N���o����ɂ������āA�����ɋL�q����Ă��镶��/�A�C�f�A�́A���p�̕\�L���Ȃ�����A���̍�i�ł���܂��B�܂��A�������̃R�[�X�̌������肪����܂ł́A���̃R�[�X���[�N�͑��݂��Ȃ��������Ƃ��m�F���܂��B
�R���v���C�A���X���m�����邽�߂ɍł��d�v�ȗp���́A�g�D�Ɛl�ł���B�R���v���C�A���X�����������邽�߁A���[�_�[�V�b�v���������Ȃ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�����ŁA���ݘb��ɂȂ��Ă���J�����X�E�S�[���ƃW���b�N�E�E�F���`�̒����ʂ��Ăǂ̂悤�ȃ��[�_�[�V�b�v�����߂��Ă����̂��A�ǂ̂悤�Ɏ��H���Ă����̂���T��B
�������A�Љ�̍\�����̂��̂��ω����Ă��錻�݁A���܂ł̃��[�_�[�V�b�v�����̂܂ܒʗp����̂ł��낤���B
����������Ă����Ǝv����l�b�g���[�N�Љ�ɂ����āA�R���v���C�A���X�̎����ɖ𗧂Ǝv���闝�O�Ƃ��āAWin-Win���_����グ��B
�����āAWin-Win���_�̋A���Ƃ��ĐV�������[�_�[�V�b�v�ɋ��߂�����������_�Â���B
�ڎ�
1.�͂��߂�
2.���[�_�[�Ƃ͉���
2.1�g�D�̕����ƃ��[�_�[�̕���
2.2�Y�Ɗv���Ƒg�D
3.�����̌o�c�҂Ɍ��郊�[�_�[�V�b�v
3.1���l�b�T���X
3.2�W���b�N�E�E�F���`�@�킪�o�c
3.3�ӂ���Ɍ��郊�[�_�[�V�b�v
4.�Љ�̕ϊv�ƃ��[�_�[�̕ϊv
4.1�l���s���~�b�h�Ƒg�D
4.2�Љ�̕ω��Ƒg�D�̕ω�
4.3�l�b�g���[�N�g�D
4.4�Q�[���̗��_
4.4.1���l�̃W�����}
4.4.2�p���I���l�̃W�����}
4.4.3����r�W�l�X�E�Q�[��
4.5�@Win-Win���_
5.���Z�ƊE�ɂ�����R���v���C�A���X
5.1�R���v���C�A���X�Ǝ�����̖���
5.2�R���v���C�A���X��Win-Win���_
6.�����^���[�_�[�V�b�v���狤�n�^���[�_�[�V�b�v��
6.1���n�^���[�_�[�V�b�v�Ƃ͉���
6.2�J�����X��S�[���ƃN���X��t�@���N�V���i����`�[��
6.3�W���b�N�E�E�F���`�Ƌ��E�̂Ȃ��g�D
7.���_
����1
�u���{�����ی����݉�Ђɑ���s�������ɂ��āv
����2
�����ƏW�c�H���Ŏ���
����3
�O�H�����ԃ��R�[���B������
�Q�l����
1.�͂��߂�
2001�N���{�v���싅�p�V�t�B�b�N�E���[�O�͉ߋ�2�N�ԃ��[�O�ʼn��ʂ̋ߓS�o�b�t�@���[�Y�̗D���Ŗ�������B���̗D���Ɋւ��āA�싅�]�_�Ƃ̖L�c�������A���̂悤�ȃR�����g���Ă����B
�����c��2000�N���A�Ă�����Ɍ��h�W���[�Y�ē̃g�~�[�E���\�[�_�����A�h�o�C�U�[�Ƃ��ď������B�ǂ����債�����Ƃ���܂��Ǝv���Ă������A���ʂ͗D���ł������B�������u�ߓS�i�C���ɂ����炵�����̂́u�����ɂ��킪�d�����D���邩������Ȃ��v�Ƃ�����@���������v�B�����͉��l���̑I���č����瓱���������A���ꂪ�u�ߎ�ȊO�ǂ̃|�W�V�����ł��I�肪���荞�܂�Ă���\��������A�v�Ǝv�킹�錋�ʂƂȂ����B�u���\�[�_���̓��j�z�[���������Ȃ��������A���c�ēɂ���A���ē���ɂ����������悤�Ȃ��̂ŁA�����������Ă����Ȃ��B�҂���Ƃ����̂͑I�����ł͂Ȃ������͂����v�i9��27���t�����{�o�ϐV���j�B
�����A�����ł���Ƃ���A�ߓS�o�b�t�@���[�Y�͏�ł͂Ȃ��������ЂƂ�̎w���҂����������������Łi�lj������̑I�肪�������Ƃ͎����ł��邪�j�g�D�̊�������}�ꂽ���ƂɂȂ�B�Ȃ��A�ߓS�o�b�t�@���[�Y�͍��܂łƖw�Ǔ�����͂Ő킢�Ȃ���D���ł����̂ł��낤���B�t�ɂ����A�Ȃ��ߓS�o�b�t�@���[�Y�͍��N�D�������̂Ɠ������͂������Ȃ��獡�܂Œ�����Ă����̂ł��낤���B
���݁A�r�W�l�X�̌���ɂ����ẮA�Љ�I�A���j�I�v���ɂ��A��Ƒg�D���傫���ϖe���悤�Ƃ��Ă���B�{�e�̖ړI�́A�ϖe������g�D�ɂ����郊�[�_�[�̖����ƁA�g�D�����[�h���Ă��������𖾂炩�ɂ�����̂ł���B
2.���[�_�[�Ƃ͉���
���{��Ƃ̑̎����P�E�ϊv������钆�A���[�_�[�V�b�v���C�Ȃǂ�����ɂ킽���čs���Ă���B�Ƃ���ŁA�����ł������[�_�[�ɂ́A�]���̈Ӗ������ɂ����Ă̕����ǂ���̃��[�_�[�͂������̂��ƁA�g�D�̒��̏����ȑg�D�ɂ����郊�[�_�[�A�����钆�ԊǗ��w���ΏۂƂ��Ċ܂܂�Ă���B
���[�_�[�Ƃ͖����ł����āA�}�l�W���[�Ȃǂ̂�����E���A�E�K�Ƃ͈قȂ�B�����̃��[�_�[�ɋ��߂��鎑���͂�����g�D�̒��Ƃ��Ẵ��[�_�[�Ƌ��߂��邱�ƂƁA���ꂪ�قȂ邾���œ����悤�Ȏ��������߂��Ă���̂ł���B�{�_���ł́A���[�_�[��������}�l�W���[�Ƃ͋敪���āA���炩�̑g�D�ɂ����ă��[�_�[�V�b�v�����Ă���A���邢�͔������邱�Ƃ����҂���Ă���l�Ԃ����[�_�[�ƈʒu�t���邱�Ƃɂ���B�]���āA�g�D���̐E�ʂł���}�l�W���[�A���{�I�ȐE�K�ł��镔���A�ے��ȂǂƂ͈قȂ����Ӗ������ŗp������̂Ƃ���B
2.1�g�D�̕����ƃ��[�_�[�̕���
���j�I�Ɍ��āA���n��E�̏W�Љ�ɂ����ẮA���[�_�[�Ƃ́A�����ǂ���̃��[�_�[�i���[�h����l�A���悵�ĉ��������l�j�ł��������Ƃł��낤�B���݂̒ʐ��ł́A���n��E�̏W�Љ�ɂ����Ă͐g���̕������}���Ă��Ȃ��Ȃ������悤�ł��邩��A���[�_�[�Ƃ����ǂ��ЂƂ̐g���ł͂Ȃ��A���P��������邱�Ƃ��Ȃ��A�l���Ȃ̗͗ʂɂ���ă��[�_�[�̒n�ʂ����������̂������Ǝv����B
���̎���̃��[�_�[�̓����́A�g�D�̕������}���Ă��Ȃ��A�܂�@�\�I�������}���Ă��Ȃ����Ƃł���B��{�I�ɂ́A���[�_�[�����̑��̐l�Ԃ���邱�Ƃ͓����Ȃ̂ł���B
�Ƃ��낪�A���̑̐����_�k�Љ�̎n�܂�ƂƂ��ɑ傫���ϖe���Ă������ƂɂȂ�B�_�k�̎n�܂�ƂƂ��ɒ�Z���n�܂�A�Љ�ɂ��K�w�A�g�����������邱�ƂɂȂ�B���̍����J�K���Ȃǂ����������Ƃ����Ă���B
�����琔��N�O�ɂ����̂ڂ邱�̎���ɂ����āA�g�D�̕����ƂƂ��ɋ@�\���������n�܂����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���̍����݂��ꂽ�Ƃ����Ă���s���~�b�h�Ȃǂ��A���݂̋Z�p�i���o������A�^�肷��Ƃ������n�[�h�ʂ̋Z�p�����ł͂Ȃ��A�@�B���g��Ȃ�����l�����K�v�Ƃ��ꂽ�J���҂̊Ǘ��A�����̘J���҂̓K���z���A�����v��A���邢�͋��z�̎������B�Ȃǂ̃\�t�g�ʂ��܂ށj�������Ă��Ă��A���ɍ���ł���Ƃ����B�����ł���Ƃ���A�������x�ȊǗ��Z�p���p�����Ă����̂ł��낤�B
�n���l�啶���ȂǂƂ������邱���̕������ԊJ���������ɂ́A���݂��猩�Ă��K�͂̑傫�����Ƃ����s���ꂽ���Ƃ��m���Ă���B���̂悤�Ȏ���̗v������A�Ñ�Љ�ɂ����ẮA���݂ł����[�_�[�Ƃ��Ēʗp����A���邢�̓��[�_�[�Ƃ��Ĉ��p�����@��̑����A�`�̎n�c��A�V�[�U�[�A�A���N�T���_�[�剤�Ȃǂ̋��l�ݏo�����B�ނ炪�����ɋ��l�ł������Ƃ͂����A�ނ�̐��ݏo�����鍑�͂ЂƂ�̐l�Ԃ��x�z����͈͂��͂邩�ɒ����Ă����B���̓����ɂ́A�l�X�ȍH�v�A�g�D���W���Ă������̂Ǝv����B���̂悤�ȈӖ�������A�ނ�͋ߑ�I�ȈӖ��ɂ����Ă����[�_�[�������Ƃ�����ł��낤�B
�������A���̎���̒鍑�̑����́A���̌�̗��j�̓W�J�̒��Ő����A�c�O�Ȃ���A����̋L�^�E���ՁE�L�������̌�̗��j�̒��ɂ͂�����Ǝc�����ƂȂ����j�Ɉ��ݍ��܂�Ă����Ă��܂����B
���̌�A�Í��̒������m�̓�����킢�s�����ƂɂȂ�B�������A���͌��ݓ`������قǐ^���ÂȎ���ł͂Ȃ������悤�ł͂��邪�A�Ñ�ɂ����ĉh�����悤�ȋ��卑�Ƃ����݂��Ă��Ȃ��������Ƃ����͊m���ł���B
���̌�A�l�X�����]�Ȑ܂��o�ċߑ�ɓ���킯�ł��邪�A�Љ�g�D�̂�����Ɍ���I�ȕω��������炵���̂��A�Y�Ɗv���ł���B
�u�Y�Ɗv���́A18���I�̌㔼�ɃC�M���X�Ŏn�܂�A19���I�̂����ɐ����[���b�p��A�����J����{�ɍL���������ۂ��w���B��̓I�ɂ́A���C�@�ւ𗘗p�����^�@�B��g�D�I�ɗ��p����H�ꐧ�H�Ɛ��Y�����y���A��v�Ȏ��{�~�ςƌo�ϐ����̌���ɂȂ��������ł���B�v
�u�Y�Ɗv���ȑO�̐��Y�`�Ԃ́A���Y��i���������l�X���Ƒ���P�ʂƂ��ĘJ�������Ă����B�_���͓y�n�ɑ���k�쌠�������Ă����B�����ĂقƂ�ǂ̏ꍇ�A�J���̒P�ʂ͉Ƒ��ł���A��w���V�l���q�����A�d���S���Ă����B�v
�u�Ƃ��낪�A�Y�Ɗv�����ɏo���������C���͂ɂ���ē�����^�@�B�́A���ꂼ��̉Ƒ������ɂ͍����߂������A�Ƒ��P�ʂ̘J���ʼn^�p����ɂ͑傫�߂����G�߂����B������^�]���^�p����ɂ́A�����̐��m�������l�ނ��K�v�ł���B�v�i�䉮 �����w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��xpp239�|240�j
�Y�Ɗv���ɂ���āA�J���҂͐��Y��i�������Ȃ��Ȃ�A�J���͂���邾���̑��݂ɂȂ��Ă��܂����ƃ}���N�X�݂͂Ȃ����B�܂�A�z�ꉻ�ł���B�J���҂͈���I�Ɏ��D����鑶�݂ɂȂ��Ă��܂��B�]���āA�ނ͐��Y��i�͍��L���A�Љ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��ނ̌��_�ł������B
�������A�Љ�̓}���N�X�̎v�����ʂ�ɂ͔��W���Ȃ������B�Ƃ����̂́A����Ȑ��Y��i�́A������^�c�E�^�]����̂ɗl�X�ȐE��̐l�Ԃ�K�v�Ƃ�������ł���B�����́A�@�B�̉^�c���s���Z�p�҂�����Ύ����肽�ł��낤�l�ނ��A�@�\�̕��G���ɔ����āA�t�@�C�i���X����A�J���Ǘ�����ȂǁA���Y�Ƃ͒��ڊW�Ȃ���������K�v�Ƃ���悤�ɂȂ����̂ł���B���̂悤�ȕ���̏]���҂�������z���C�g�J���[�ݏo���Ă������B�����ɁA�����̐l�X�������钆�Y�K�����`��邱�ƂɂȂ����B�Љ�͒P���ɓ�ɉ����邱�Ƃ��Ȃ��A�v�����N���Ȃ������B
�������A�{�_���ɂ����ẮA�v���ɂ��ė��j�I�A�Љ�Ȋw�I���͂��s�����Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA����ȏ�̕��͍͂s��Ȃ����Ƃɂ���B
2.2�Y�Ɗv���Ƒg�D
�Y�Ɗv���̌�ɐ���ɍ̗p���ꂽ�g�D�`�Ԃ́A������s���~�b�h�^�g�D�������Ă��邱�Ƃ������ł���B�������A�l�ގj��ɂ����āA���̌`�Ԃ̑g�D�́A�Y�Ɗv����ɐ����������̂ł͂Ȃ��B�×��A�R���g�D�͑�̂ɂ����Ă��̂悤�Ȍ`�Ԃ��̂��Ă�������ł���B���[�}�R���A�������́i�����ȊO�̌R���͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�@�\�I�������Ȃ���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ł��낤���j����A�����A�S�l���Ƃ����\���������Ă����B�S�l�����܂ł̓��[�}�s���Ɍ��炸�N�ł��Ȃꂽ���A����ȏ�͎s�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���������A���̈Ӗ��ł͐g���ɂ�鍷�ʂ��c���Ă����B
�R���ɂ����ẮA�����ƋR���A�C���ȂǁA�l�X�ȐE�킪���݂��邵�A���߂̂��ƈ�ۂƂȂ��ēˌ����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��킯�ł��邩��A���̌�̎���ɂ����Ă������ꏭ�Ȃ���s���~�b�h�g�D���̂��Ă��邱�Ƃ������B
�������A��ʎs���̎Q������g�D���傫�ȃs���~�b�h�\�������悤�ɂȂ����̂́A�Y�Ɗv���Ȍ�Ƃ����Ă��ǂ��ł��낤�B��ʂ̉�ЁA��ƌo�c�ɍL���g��ꂽ���ʁA�s���~�b�h�^�g�D�͍L���Љ�ɍ������낵�Ă������ƂɂȂ����B
3.�����̌o�c�҂Ɍ��郊�[�_�[�V�b�v
����ł́A���݂̑�\�I�s���~�b�h�^�g�D�ł�����Ƃɂ����āA���[�_�[�͂ǂ̂悤�ȃ��[�_�[�V�b�v�����H���Ă���̂ł��낤���B�o�c�҂Ƃ��āA��ςȐ��������߁A�����{�l�ɂ�����݂̂���J�����X�E�S�[���ƃW���b�N�E�E�F���`���P�[�X�X�^�f�B�[�Ƃ��Ď�グ�Ă݂�B
3.1���l�b�T���X
1999�N�ɓ��Y��COO�Ƃ��Ē��C�����J�����X�E�S�[���͓��N10���ɂ͓��Y���o�C�o���v�����iNRP�j�\�A���̂悤�ȃR�~�b�g�����g�\�����B�u���͎��̎O���ő�̕K�B�ڕW�Ƃ��Čf���A�����ꂩ�ЂƂł��B���ł��Ȃ������ꍇ�͐ӔC������ē��Y�����錈�ӂ������B�@2000�N�x�ɍ�������B�����邱�ƁA�A2002�N�x�ɉc�Ɨ��v�����Œ�4.5�p�[�Z���g�ɑ��₷���ƁA�B2002�N�x�ɗL���q����7000���~�ȉ��ɍ팸���邱�ƁA�̎O�ł���v�i�J�����X�E�S�[���w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����xpp262�|263�j�B
���̃R�~�b�g�����g�́A���{�l�̓x�̂����B����́A��ʐl�݂̂Ȃ炸�A���Y�Г��̐l�Ԃ����l�������悤�ł���B���܂ł̌o�c�g�b�v�͌����Ă��̂悤�Ȗ�������A�܂��Ă���\�����肷��ȂǂƂ������Ƃ͍l�����Ȃ������B�����Ă��̃��X�N��Ƃ����Ƃ������Ƃ́A�S�[���������ɖ{�C�ʼn��v�����s���Ă������A���̐ӔC�����Ƃ������Ƃ�@���Ɏ����Ă���̂ł���B
�R�X�g�J�b�^�[�ȂǂƂ������肪�����Ȃ��j�b�N�l�[���Ղ��Ă����S�[���ł��邪�A���Y�Г��̐l�g�����ɂ͂��قǎ��Ԃ͂�����Ȃ������悤�ł���B�Г��̐l�Ԃ́A���v�̒ɂ݂��ŏ��Ɋ����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ɠ����ɁA�ł����v�̕K�v����F�����Ă���l�B�Ȃ̂ł���B
�S�[���̒����̒��ɁA�f�g���C�g�E�t���[�v���X�i1999�N11��15���t�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�A�����ꂽ���R�H����ӂ̗�����Ǝ҂̃C���^�r���[�����p����Ă���B�u���Y���Č��ɐ������Ȃ���A�������������c��܂���B����̐V�����v��iNRP�j�ɏ���v��͂���܂���B����܂œ��Y������Ă����̂́A�扄���Ǝ�̉��ɂȂ�����ł����B���͓��Y�ɑ��ċ������h�̔O�ƒ����S�������Ă��܂��B���̓x�X�g��s���ăS�[������ɋ��͂��A�x�����Ă������Ǝv���Ă��܂��B���Y�ɂ͂��З��������Ăق����B���̂��߂Ȃ���ŋ]��������ł��B�v�i�J�����X�E�S�[�� �w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����x p189�j
�����̒����Ɉ��p���Ă���킯�ł��邩��A���R�D�ӓI�ȃR�����g��I��ł���̂ł͂��낤���A���ۂɒ��C��Ԃ��Ȃ������ɓ��Y�̎Ј�����b�����Ƃ����A�ӊO�ƃl�K�e�B�u�Ȉӌ��͕�����Ȃ��������Ƃ��v���o���B
�l�g�������I�݂ł������Ƃ������ƂƁA�����ЂƂA�S�[���������������Ă���悤�ɁA���Ƃ���]�ƈ��Ƃ����ǂ��S�̒ꂩ���Ђ�J���Ă���̂ł���B���Ƃ����̕ϊv�����������̂ł����Ă��A������߂�͂ł��Ȃ����Ƃ���ԗǂ��F�����Ă���̂ł���B
3.2�W���b�N�E�E�F���`�@�킪�o�c
�W���b�N�E�E�F���`�́A20���I�ł����Ƃ��̑�Ȍo�c�҂Ƃ����Ă���B1981�N��46�̎Ⴓ��GE�̉��CEO�ƂȂ�A�ȗ����|��21�N�Ԃ��̐E�ɂƂǂ܂�A����ȃ��[�_�[�V�b�v�̊�GE�̕ϊv�Ɏ��g��ł����B�i���o�[�����E�i���o�[�c�[�헪�A�V�b�N�X�V�O�}�A�T�[�r�X�d���A���E�̂Ȃ��g�D�Ȃǂ̐V�����R���Z�v�g�����X��GE�ɂ����炵�A�T�^�I�ȋ����Ƃł�����GE���X�����ōs���́E���s�͂ɕx���v���̍�����Ƃւƕς��Ă������B
�m���̓��Y�ɏ�荞��ł������S�[���Ƃ͈قȂ�A�E�F���`����ƂȂ���GE�̋Ɛт͍D���ł������B�u1�N��250���h���̔��㍂��15���h���̗��v���L�^���A40��4000�l�̏]�ƈ�������Ă���B�������e�̓g���v��A�ŁA���̃T�[�r�X�̓g�[�X�^�[���甭�d���ɂ�����܂ŁAGNP�i���������Y�j�ɂ������قƂ�ǂ��ׂĂ̂��̂ɋy�ԁv�i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��p148�j�Ƃ������̂ł������B�t�H�[�`����500�В����v���ł͑�9�ʁA���㍂�ł���10�ʂł������BGE�̒N��������ɖ������Ă����B�W���b�N�E�E�F���`�������ẮB
���̂悤��GE�̌���ɑ��āA�E�F���`�͊�@����k��������B�g�D�͍d�����A���������Ă����B����ł́A���̌�ɗ\�z�����Ζ����i�̏㏸�A���{��Ƃ̑䓪�Ȃǂɗ����������Ȃ��Ƃ��đg�D�̃X��������f�s�A1980�N���ɂ�41��1000�l�������]�ƈ����́A1985�N���ɂ�29��9000�l�ɍ팸���ꂽ�B�܂��A�i���o�[�����E�i���o�[�c�[�헪�ɂ��A����ȉ��̎��Ƃɂ��ẮA���p����邩�P�ނ��邩�̑I��������ꂽ�B
���̌��ʁA�ȑO�͂��܂��܂ȉƒ�p�d�C���i��GE�̖�������ꂽ���̂ł��邪�A���݉ƒ�Ŗڂɂł����v���i�͓d���Ɨ①�ɂ����ł��낤�B
3.3�ӂ���Ɍ��郊�[�_�[�V�b�v
�S�[�����E�F���`���A����߂ċ��͂Ȍ����������w���҂ł���B�ӂ���̒����ǂ�ł܂��C�t�������Ƃ́A��l�Ƃ��ɂߕt���̕����������ł���A�����ɂ�����邱�Ƃł���
�S�[���́A�E�F���`�Ƃ͈قȂ�A���c���݂̂���ɂ͂��܂肩�炾����v�ł͂Ȃ������炵���A���܂�X�|�[�c�ɐe���Ƃ������b��͏o�Ă��Ȃ��B���̑���A�J�[�h�Q�[���ɂ͐^���Ɏ��g��ł����悤�ŁA�R���g���N�g�E�u���b�W�ɂ܂���b���o�Ă���B������F�l�ƃy�A��g��Ńu���b�W�E�g�[�i�����g�ɏo�ꂵ�����A�S�s�����B�u�^���ȃv���[���[�Ƃ������̂́A�������Ƃ��A�u�����͂��ĂȂ������B���x�͏��Ă邳�v�ƌy���������Ƃ��ł����A�ǂ̈��A�ǂ̃T�C���A�ǂ̃J�[�h�����������̂��A����U��Ԃ��Ĕs����˂��~�߂悤�Ƃ���v�B�u�ǂ��炩���A�u����������A�l�̃~�X��������������Ȃ��v�ȂǂƏ���C�z�͂��������ɂȂ������v�B���̌��ʁA���ƂɃS�[���w�l�ƂȂ鏗���ɏ��߂ďo������ɂ�������炸�A�S�R�o���Ă��Ȃ����������ł���i�J�����X�E�S�[���w���l�b�T���X�xp50�j�B
�E�F���`�̏ꍇ�����l�ł���B�ނ͑����̃X�|�[�c�ɐe���悤�ł���B�����āA���̔ނ��܂��A�e����^�����̂���e�ł������Ƃ����B�u��͎��̐l���ɂ����Ƃ������e����^�����l�������B�O���[�X�E�E�F���`�͎��ɏ���т������A�s�k�ɍ����Ă͂����Ȃ����Ƃ������Ȃ���A�키���Ƃ̈Ӗ��������Ă��ꂽ�i�W���b�N�E�E�F���`�@�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x�@��p18�j�B�u���������̊y������m�����̂́A��ƃW���E���~�C�Ƃ����g�����v�Q�[�������ėV�L�b�`���e�[�u���̏ゾ�����B�v�u�w�Z�ɖ߂��Ď��Ƃ��Ă��邠�������A��������Ƃ���l���Ă����B�v�u�싅�̃O���E���h�ŁA�z�b�P�[�����N�ŁA�S���t�R�[�X�ŁA�����ăr�W�l�X�̏�ł̎��̕����������́A���̂Ƃ�����n�܂����悤���v�i�W���b�N�E�E�F���`�@�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x�@��p20�j�B
�ӂ���Ƃ������������ł���Ɠ����ɁA���͓I�Ȏv�l���s�����Ƃ����ʂ��Ă���B�����������ĕ������̂ł���A���̉�����O��I�ɒNj�����B�����āA�Nj����ē���ꂽ�s�����Ԃ����ƂɑS�͂��X����̂ł���B
�����̐l�́A�����Ă��^�����������Ƃ�����߂Ă��܂��B������߂Ă��܂��̂ŁA���s�̌�����Nj����悤�Ƃ͂��Ȃ��B���s�����ɐ�������Ȃ��̂ŁA�܂��������s���J��Ԃ����ƂɂȂ�B
�܂��A���s��U��Ԃ鏭���̐l�ł��A�����̏ꍇ�͔s���͂��Č��_������ꂽ���ƂŖ������Ă��܂��B�m�I�D��S�������邾���ŁA���ۂɒɂ݂��������v�ɂ܂ŏ��o���Ȃ��B���邢�́A���v�ɏ��o���`�͍�邪�A��������l���o���Ď��s���Ȃ��B���ǁA���s���J��Ԃ����ƂɂȂ�B
�u���s�������ׂā\�\�\���ꂪ���̎��_�ł���v�i�J�����X�E�S�[���@�w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����xp114�j�B������ӂ���ɋ��ʂ̓����ł���B
������ɂ��Ă��A���������ɍS��̂́A2�l�̃��[�_�V�b�v�ɋ��ʂ̃|�C���g�ł���B
�܂��A�ӂ���̃��[�_�[�V�b�v�E�X�^�C���ɂ͋��ʂ��������_������B����́A����Ƃ��͐M�p���ĕ����ɔC���Ă��܂��悤�ȃ��[�_�[�V�b�v�E�X�^�C�����Ƃ邪�A�ʂ̎��ɂ͏d���̋������悤�Ȃ��Ƃ܂Ō��o�����邱�Ƃł���B���͖������Ă���悤�Ɍ����邾���ł����āA�{���ɖ������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��邪�A����߂Ėʔ������ʓ_�ł���Ǝv����B
�S�[���̏ꍇ�A���Y�̌����m�邽�߂ɁA�����Ј����炶���Ɏd�������@��������B�u��@�I�ɂ����Ђɂ͎В����m��Ȃ��Ă��悢���ƂȂLj���Ȃ����Ƃ��������������B�В�����ҁA�ڋq�����≿�l�n���ɂ�����邷�ׂĂ̎����ɂ��āA�d�����X�s�[�h�A�b�v������@���d����W�����Q�̂��ׂĂɂ��Ēm���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�J�����X�E�S�[���@���Op166�j�̂ł���B�Ј��͂��ꂱ���q�����悤�ɍׂ������Ƃ܂ō��@��t�@�蕷���ꂽ���Ƃł��낤�B
���̂悤�ɁA�ׂ��������ɂ������悤�Ɍ����Ȃ���A�傫�Ȍ����Ϗ����s���B�u�r�W�l�X�v�����̍쐬�Əd�v�ڕW�̐ݒ肪�I�������A�В��͂���В��Ə햱��ɈςˁA����ȍ~�͔ނ炪�ӔC�������ăv����������������B�v�u���͈�т��ă~�N���E�}�l�W�����g�����ۂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�Ј��̔\�͂����������A�Ɛт����ڂ܂��邩�炾�B�Ƃ��Ɏd���̃X�s�[�h��x�点�邱�ƂɂȂ�v�i�J�����X�E�S�[���@�w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����x�@p223�j�B��U���j�����߂Ďw�����o������A�ߏ�ȉ����͂��Ȃ��̂ł���B
�W���b�N�E�E�F���`�����l�ł���B�u��ł��邱�Ƃɂ͂��܂��܂Ȃ����ʂ�����B���̍D���Ȗ̂ЂƂ��A���鎖����I�яo���A����Ɂu�O�����v����Ƃ������Ƃ��B�܂肱��͎����Ȃ�ł͂Ƃ����͂������ł���\�\�\�������y���߂����ȁ\�\�\�ۑ�������o���A�����Ă��̉ۑ�ɑS�͂��X�����ē������o�����Ƃ��邱�Ƃ��v�i�W���b�N�E�E�F���`�@�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��p317�j�B�Г��̍ō����͎҂����������ɂ��o�܂��ɂȂ�̂ł���B�m������Ȃ��̂ɂ��邳���Ǝv���Ă��A�f�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���̈���ŁA��ł��邠�����̂���18�N�ԁA�E�F���`�͎x�o���F�̃T�C�����������Ƃ��Ȃ������Ƃ����B�u�e���ƕ���̃��[�_�[�ɂ́A���������ɗ^�����̂Ɠ������������������炾�B���N�N�����ɂ��ꂼ��̎��Ƃ��K�v�ȗ\�Z��v�����A�����o�c�w��������U�蕪����B5000���h�����琔���h���܂ł̕����������B�e���Ƃ����ꂼ��̗\�Z�ɑS�ӔC�������A���̎x�o�������ǂ̒��x�܂ʼn��ɗ^���邩�f����B���̎d���ɂ�����߂��l�������A���̎d���̂��Ƃ�������悭�m���Ă���B���͂��̐l�����̐ӔC���d�������B�����̃T�C���̏�ɗ]�v�ȃT�C�����ςݏd�Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��ƈӎ�����A���̂�����v���z�ɂ��Ă͂邩�ɐ^���ɍl����悤�ɂȂ���̂��v�i�W���b�N�E�E�F���`�@�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��pp156-157�j�B
���[�_�[�V�b�v�Ƃ����ƁA�l�𗦂��Ă������ʂ��肪�d�����ꂪ���ł���B�������A���[�_�[������g�D�𗦂��Ă����ȏ�A�g�D�̍\����������킯�ɂ͂����Ȃ��B�����o�������͎̂R�X�ł������Ƃ��Ă��A�����ׂ��Ƃ��͈����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł���B
4.�Љ�̕ω��ƃ��[�_�[�̕ω�
�ŋߔ��\���ꂽ2000�N�x�̍��������ɂ����āA���߂ĘV�N�l�����N���l�����������Ƃ����B���O���ɔ䂵�āA���{�̘V��̃X�s�[�h�͐��E��ł���Ƃ����B�������A���O���ɂ����Ă��A�o�����̒ቺ�A��ËZ�p�̐i���ɂ�鎀�S���̒ቺ�����Ă���A���{���l�̍���Љ�𑁔ӌ}���邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�Љ�̑g�����s���~�b�h�^����I���^�ւƕω��𐋂��Ă���̂ł���B���̒��ŁA������̊�ƁE�g�D�������s���~�b�h�^�̑g�D���ێ����Ă������Ƃ͕s�\�ł���Ǝv����B�����Ō���Ă���̂��l�b�g���[�N�Љ�ł���B�l�b�g���[�N�Љ�Ƃ͂ǂ̂悤�ȓ����������Ă���̂ł��낤���B�����ăl�b�g���[�N�Љ���x����w�������Ƃ��āAWin�]Win���_�����グ��B
4.1�l���s���~�b�h�Ƒg�D
�ŋߔ��\���ꂽ2000�N�Ɏ��{���ꂽ���������̌��ʂł́A1920�N�̓������J�n�ȗ��n�߂ĘV�N�l�����N���l�����������Ƃ����B���̓��e�́A65�Έȏ�̘V�N�l����17.3���A����ɑ���15�Ζ����̔N���l����14.6���i1995�N�̒����ł͂��ꂼ��14.5���A15.9���j�ł������B�i�����V��10��31��http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011031-00001021-mai-pol (10/31/2001)�j
�}1�|1������Ε���ʂ�A�]���̐l�����z�͐l���s���~�b�h�Ƃ������t�����̂܂ܕ\���Ƃ���́A�s���~�b�h��̕��z�������Ă����B�u�l�ނ͗��j�̂قƂ�ǂ̊��ԁA15�Ζ����̎q��4�l�ɑ���65�Έȏ�̍����1�l�̊����Ő����ė����Ƃ����B���̔䗦�́A1950�N��܂ł͓��{�ł��قڕۂ���Ă����v�i�䉮 �����w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��xpp260�|261�j�����ł���B���ꂪ�傫������A���ɘV�N�l���ƔN���l���̋t�]���N�����Ă��܂����̂ł���B
�}1�|1����1�|4 �l���s���~�b�h�̐���
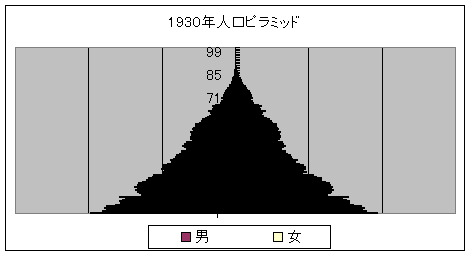
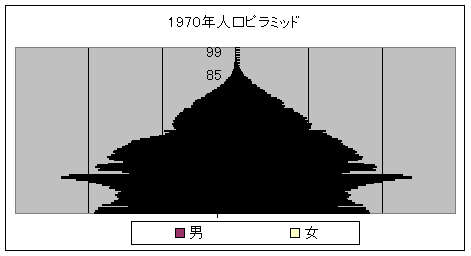
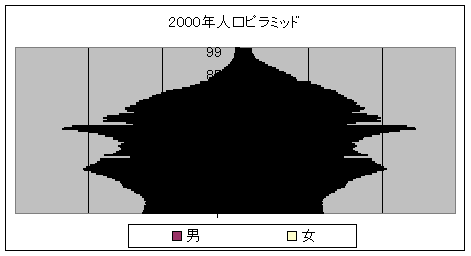
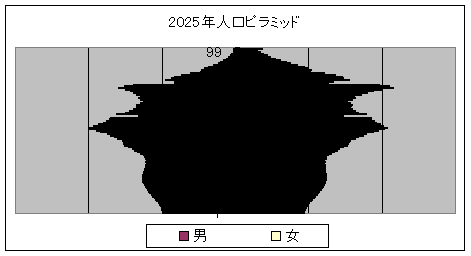
�������A�{�_���ł́A�l���s���~�b�h���̂��̂���Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B���́A�O�q�����Y�Ɗv���Ō��o�����g�D�ƁA�l���s���~�b�h�̌`�Ԃ̗ގ��ł���B
�Y�Ɗv���̌��ʂƂ��č̗p���ꂽ��Ƒg�D�ł����Ă��A�Љ�����Ȃ��ẮA���������Ȃ������ł��낤�B
�������A����ȑO�ɂ��A�ƒ���ȂǂŁA���K�͂ȃs���~�b�h�g�D�͌`����Ă������Ƃł��낤�B�Ƃ��낪�A�Y�Ɗv���ł��̂悤�ȑg�D����C�Ɋg�債���B���ʁA�g�D����C�Ɋg�傷��ƐF�X���a�݂���������̂ł��邪�A�s���~�b�h��̊�Ƒg�D�͍L��������ꂽ�B���̂킯�́A�Љ�S�̂��s���~�b�h��̍\�����̂��Ă�������ł���B
�Љ�S�̂ɂ����āA��ʐE�ʎ҂��߂�ł��낤����҂̐������Ȃ����߁i�͂����茾���ƁA����������ȑO�Ɏ��S����j�A�o���L�x�Ȑl�ނ��烊�[�_�[��I�ԏꍇ�ɂ͑I�����������A�����Ȃ�����Ȃ�ƌ��܂邵�A�Љ�I�ɂ����肪�悢�B�N���҂��猩�Ă��A���������������Ă�������A���[�_�[�Ȃ�����ʂ̐E�K�ɂقڎ����I�ɏA����킯�ł��邩��A���͂Ȕ������N����Ȃ��B�s���~�b�h�^�̑g�D�́A�Љ�I�ɂ�����₷���g�D�`�Ԃ������̂ł���B
4.2�s���~�b�h�^�g�D�̕��Q
�s���~�b�h�^�g�D�̕��Q�́A���݂̊����g�D���ώ@������܂��܂Ȍ��_���v�������ׂ邱�Ƃ��ł���B
�܂��A�g�D�̊K�w����d�ɂ��d�Ȃ��Ă���B�����Ă�ʂ����Ƃ���ƁA���ꂩ��n�܂��Č��ٌ����҂܂ł̒����͂̍s�K�v�ɂȂ�B�͂������Ă��炤���тɈꂩ��������J��Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�]���Ĉӎv���肪�x���B
�s���~�b�h�^�g�D�ɂ����ẮA�ׂ̃s���~�b�h�Ƃ̈ӎv�a�ʂ͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̓s���~�b�h�\���̒����㉺���邾���ŁA�s���~�b�h�O���ƈӎv�a�ʂ�}��@�\�͂Ȃ�����ł���B�܂��A�Ⴆ�s���~�b�h�����ɂ����Ƃ��Ă��A�قȂ������C���Ԃŏ���L����邱�Ƃ͂Ȃ��B�s���~�b�h�g�D�ɉ��̘A�g�͂Ȃ��̂ł���B
�܂��A�������ɂȂ��Ă���V����l���Ȃǂ��A�s���~�b�h�\�����Ɉێ����悤�Ƃ��邱�Ƃ��琶�܂�Ă����ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�����g�D�ɂ����ẮA����N���ň��̐l�����̗p�����ꍇ�A���̌�A����|�W�V�����ɏo�����邽�тɐl�����i���Ă����A�ŏI�I�ɓ����̒����玖���������a������܂łɂ͂��̑��̐l�Ԃ͑ޒ����邱�ƂɂȂ�A�Ƃ����Ă���B
�l��50�N�Ƃ����A�Ȃ����l���\�����s���~�b�h�^�����Ă���̂ł���A��L�̃V�X�e�������܂��������̂ł��낤�B�Ƃ��낪�A����12�N�x�̕��ϗ]���͏���84.62�A�j���ł�77.64�ɒB����̂ł���i�����Ȕ��\�j�B50���z�������炢�ň�l���������������ɂ��A����ȊO�̐l�Ԃɂ͑ސE���Ă��炤�Ƃ����V�X�e�����ێ�����ɂ́A����ȊO�̐l�Ԃɑ���M�����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ǂ��납�A���������ɂȂ����{�l�̑ސE��̎M���i�����30�N�߂����Ԃɂ킽���āj�p�ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ�Ƃ����S�̑傫���V�X�e���ł���B
�J�����X�E�S�[���������悤�Ȍo�������Ă���B�S�[���̓~�V�������ɏA�E��A�����ɏo�����Ă����A35�Ń~�V�������O���[�v���ɂ����ĉ��B�ȊO�ł͍ő�̋K�͂����~�V�������k�Ă�CEO�ɏA�C�����B�Ƃ��낪�A�~�V�������{�ЂŁA�Ў�ł������t�����\���E�~�V�����������ނ��A���̑��q�̃G�h���[���E�~�V�����������̍����p�����ƂɂȂ����B�G�h���[���E�~�V�������͒鉤�w�̎��K�Ƃ��ă~�V�������k�ĂŎd���ɂ��ȂǁA�S�[���Ƃ͗ǍD�ȊW��ۂ��Ă����͂��ł���i�G�h���[���E�~�V�������̓S�[�����Ⴂ�j�B�S�[���͎��͂ł��̒n�ʂ��l�������̂ł���B�~�V�������{�Ђ̍ō��o�c�ψ���̈���ɂ��I��Ă���B�N�ɉ�������K�v������̂��낤���H
�������S�[���͑ގЂ��邱�Ƃ�I�������B�u�g�b�v�̈֎q���p�����q�ɂ́A������ߋ���������ƒf����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������K��邾�낤�B�����āA����̑��Ղ����ނ��߂ɁA�����̑��̂��������`�[����g�D�����߂�ɈႢ�Ȃ��B40�N�ɂ킽���ĉ�Ђ��^�c���A�Г��ŕ���Ă����l���̌㊘�ɍ���Ƃ�����A�Ȃ����炻�̌X���͋����͂����B���e�����������Ƃ��A���������̂ł́A���e�̉e�ɂ��܂Ƃ��邱�ƂɂȂ邾�낤�v�i�J�����X�E�S�[���@�w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����xp102�j�B
�W���b�N�E�E�F���`�̏ꍇ�����l�ł���B�ނ�GE�{�Ђɏo�Ђ��A��������̈�l�ƂȂ����Ƃ��ɂ́A���������7�l���������ł���B���ꂪ�A�i�K���o�邽�тɐl�����i���A�ŏI�I�ɂ�3�l�̒�����I�ꂽ�B�I��Ȃ������l�Ԃ����́A�ގЂ���ꍇ�����������悤�ł���B
�E�F���`���g����p�҂�I�Ƃ��͂����ƒ��ړI�ł������B�ŏI�I��3�l�̎�������҂����肵����A3�l�ɑ��ẮA���̂����̒N����������Ɏw�������܂ł̂������ɁA�������g�̌�p�҂Ɉ��p�������邱�Ƃ��v�����ꂽ�B3�l�̂����ЂƂ�͎�����ɂȂ�邪�A����ȊO�̂ӂ���͎��C���������ꂽ���ƂɂȂ�B
�l���]�����������A�X�s���A�E�g���Ă�����͂ɂȂ�l�ނ�y�o���邱�ƂŗL����GE�ł���B��������ɂȂ�悤�Ȑl�Ԃ����\�Ȃ͂����Ȃ��B�l�ނ̖��ʎg���ł͂Ȃ����Ƃ����₢������GE�����ł��s��ꂽ�悤�ł���B����ɑ��ăE�F���`�́A�u���������l�����B���ꂪ�ǂ�Ȍ��ʂɂȂ邩�킩���Ă���BGE�̉�ɂȂ����l�Ԃ͒N�ł��낤�ƁA���M�ɂ��ӂ��M�ɂ��ӂ�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͂��̖{�l�ɑ傢�Ɏ��g�������Ă��Ă��炢�����B�N���������̒n�ʂ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȐS�z�����������Ȃ��v�i�W���b�N�E�E�F���`�@���O��p323�j�Ɠ����Ă���B�c���̂��납�狣�������ɐ����Ă����l�ԃW���b�N�E�E�F���`�炵�����t�ł͂���B
�s���~�b�h�^�̑g�D�ł́A�g�D�̏㕔�Ɉʒu����l���͌�����B�����ăg�b�v�͏�Ɉ�l�ł���B���̂ق����g�D�Ƃ��Ă͌����I�Ȃ̂ł��낤���A�Љ�I�ɂ͂��܂�ɂ��������傫���̂ł͂Ȃ����낤���B���ɁA�Љ�̑g�����ω����Ă��鍡�A�Љ�̈ꕔ�ŋ����Ƀs���~�b�h�g�D���ێ����邱�Ƃ́A���̑g�D�O���ɋt�s���~�b�h�̂Ȃ�Ƃ�����̈����]�蕔�����������邱�ƂɂȂ�B
I���^�Љ�ɂӂ��킵���g�D�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���B
4.3�l�b�g���[�N�g�D
�s���~�b�h�^�g�D���`������闝�R�̈�ɁA�Љ�̐l���\�������݂��邱�Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł���B
���̑��̗v���Ƃ��āA�ȒP�ɐG�ꂽ�ʂ�A�]���̏��̗�����s���~�b�h�^�g�D���`���d�v�ȗv���ƂȂ��Ă����̂ł���B�E�F���`���F�߂Ă���悤�ɁA���̎d���ɂ�����߂��l�������A���̎d���̂��Ƃ�������悭�m���Ă���̂ł���B���̂����A��ʎ҂͕����̏��o�H�������A�L���g�D�S�̂���Ղ��邱�Ƃ��ł���B
��ʎ҂͗Ⴆ�����̗ʂƎ��ɂ����Ă͉��ʎ҂ɗ�邱�Ƃ������Ă��A���̑��l���ɂ����Ă͉��ʎ҂��D�ꂽ����ɗ����Ă���B��ʎ҂̂ق������𑍍��I�ɔ��f�ł��闧��ɂ���̂ł���B�܂��A�����łȂ���Ύw���͂��ł��Ȃ��B
�}2�s���~�b�h�^�g�D�̏��
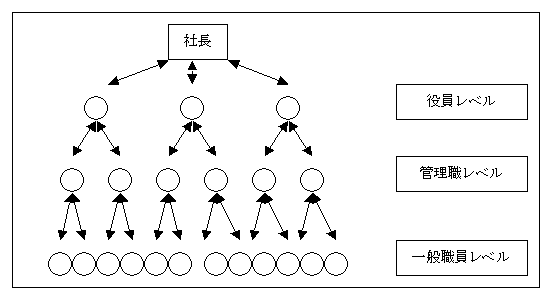
�Ƃ���ŁA��Љ�̌��݁A���̗���͏]���Ɠ����Ȃ̂ł��낤���B�}2�̂悤�ȃV�X�e���́A�]����Г����ōs���Ă����g�c�V�X�e���ȂǂƂ͎��ɂ悭�K�����Ă���B���ʎ҂����g�c���オ���Ă䂫�A��ʎ҂͎���̍L��������Ɉӌ���t�������Ă䂫�A�ŏI�I�Ɍ��ٌ����҂����ׂĂ̏����������Ĕ��f�������̂ł���B
�Ƃ��낪�A���݂ł͈�ʂ̉�Ђł����[���V�X�e�����L���g����悤�ɂȂ��Ă����B���݂̃��[���V�X�e�����g���Ă���l�Ԃł���Ηe�Ղɗ����ł���悤�ɁA���[���̑��M�V�X�e���͏�L�̂悤�Ƀs���~�b�h���������֓o���Ă䂭�ɏ]���l���������Ă����悤�ȑ��M��K�����������炳�Ȃ��B�ނ���A�ЂƂ�̔��M�҂��畡���̐l�Ԃɔ��M����A����Ɏ�M�҂����l��t�������Ĕ��M����悤�ȁA�g�U�^�̑��M�������炷�B
���̂悤�ȑ��M���@�̂��Ƃł́A�����钆�ԊǗ��w�͂��܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�܂��A��]���̘g�g�݂��đ�������ꍇ�ɂ���Ă͎ЊO�ɂ܂ŗ���Ă������ƂɂȂ�̂ŁA������u�����Ă����v���Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B�Ȃ��Ȃ�A�N�̂Ƃ���Ō��ق����Ă���̂��������ɂ킩���Ă��܂�����ł���B
���ۂɂ��̂悤�ȃV�X�e�����g���Ă݂�ƁA�ǂ��ʂƓ����Ɉ����ʂ����邱�ƂɋC�t������邪�A������ɂ��Ă��A���̂悤�ȏ����߂�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B
���̂悤�ȃl�b�g���[�N�Љ�ɂ����ẮA�]���̋���s���~�b�h�^�\���̑g�D�͋@�\���Ȃ��Ȃ�B����ɑ����āA�}3�̂悤�ȁA�����ȑg�D���Γ��̗���ŌW��荇���g�D�\���ɂȂ��Ă����̂ł��낤�B�}3�ɂ����ẮA5�p�`�̐�ɂ������Ă��鏬����3�p�`�����ꂼ��̏����ȑg�D�ł���B�ꉞ�s���~�b�h�^�g�D��\��3�p�`��p�������A���̑g�D�͏������L�ł�����x�̑傫���̑g�D�ɂȂ�̂ł��낤�B
�܂��A�}3�ɂ����Ă͏ȗ��������A���ꂼ��̏�����3�p�`�̐�ɂ́A���ꂼ��܂��ʂ̃l�b�g���[�N�ɂȂ����Ă���̂ł���B�Љ�S�̂Ƃ��ẮA���G�ɐ܂�d�Ȃ�������ȐD���̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B
�}3�ɂ����āA������3�p�`�̑g�D���̂��A���邢�͐}3�S�̂��ЂƂ̑g�D�ƌ��Ă��A�]���̂悤�ȊT�O�Ɋ�Â���Ƒg�D�Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�B������A���ꂼ�ꂪ��Ƒ̂̓������肩�O���Ƃ����ڂɌ��т��Ă��邩��ł���B
�}3�l�b�g���[�N�Љ�
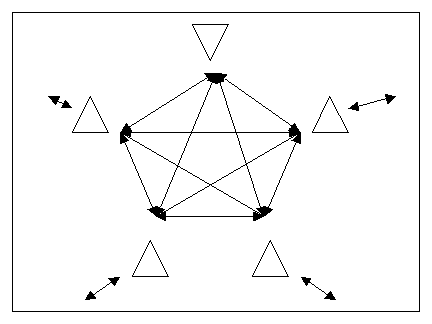
4.4�Q�[���̗��_
�����ŁA�l�b�g���[�N�Љ�ɂ����ėL���ł��낤�Ǝv����w�������Ƃ��āA�Q�[���̗��_�����グ��B�Q�[���̗��_���A�����̉Ȋw�I�����E�����Ɠ��l�ɐ푈�ɂ����ď�����Njy���钆����a�������B�������ߔN�A���̉��p�������A�r�W�l�X�̕���Œ��ڂ���Ă��闝�_�ł���B
4.4.1���l�̃W�����}
�Q�[���̗��_�̒��ŁA�ł��悭�m���Ă���Ⴊ�A���l�̃W�����}�ł���B�b���Ƃ����Q�l�̎��l���ʁX�ɂƂ���A��蒲�ׂ��Ă���B2�l�͕ʁX�Ɏ��Ă���Ă���̂ŁA���݂��̍s���͕���Ȃ��B
2�l���Ƃ����Ƃ����ƍ߂ɂ͊m����؋����Ȃ��A���������߂ĂƂȂ�i���̂悤�Ȏ�蒲�ׂ̐���͖{�e�ł͖��Ȃ��j�B
�����ŁA�x�@�͎���������|����B
�u���܂��B��2�l�Ƃ��ٔ邵�Ă��A2�l�Ƃ�1�N�̌Y���Ȃ��B���̂����A���܂����������_�𖧍�����A���܂��͖��ߕ��Ƃ��Ă��B���̑���A���_�̌Y����5�N���B�������A2�l�Ƃ�����������A2�l�Ƃ��Y����3�N���B�v
���݂��̍s���ƌY�����}�g���b�N�X�ɂ������̂����L�ł���B
|
|
�����������Ȃ� |
������������ |
|
�b���������Ȃ� |
�b 1�N �� 1�N |
�b 5�N ��0 |
|
�b���������� |
�b 0 �� 5�N |
�b 3�N �� 3�N |
���̂悤�ȏꍇ�ɂ����āA�b���͂ǂ̂悤�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ��\�z����邾�낤���B
�l�Ƃ��čD�܂����̂́A�Y���Ȃ����Ƃł��邪�A���̂��߂ɂ͎������������A���肪�������Ȃ����Ƃ��K�v�Ƃ����B�����������������Ƃ肪�m��i�Y���������Ȃ邱�ƂŕK�R�I�ɑ���͋C�t���j�A���Ƃŕ��Q���ꂽ�肷�邩������Ȃ��B
�ł���Ƃ���A���݂��ɍD�܂����̂́A���݂��ɔ閧����邱�Ƃɂ���āA1�N�̌Y���߂邱�Ƃł��낤�B���݂��̔�Q���ŏ����ɗ��߂���B����ł́A���݂��ɍ����I�ɍs������Ƃ��āA����̗��̂悤�Ȍ��_�ɓ���̂ł��낤���B���́A�e�Ղɑz���ł���ʂ�A�b���Ƃ��ɑ���𖧍����邱�Ƃɂ���āA���݂���3�N�̌Y���߂邱�ƂɂȂ�E���̗��̂悤�Ȍ��_�ɓ����Ă��܂��̂ł���B
�Ȃ��Ȃ�A���������������ꍇ�ɂ́A�Y����0�N��������3�N�ł���̂ɑ��āA�������������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�Y����1�N��������5�N�ɂȂ�B������������ꍇ�Ɩ������Ȃ��ꍇ�̊m���������Ȃ銄���ŗ^�����Ă����Ƃ��Ă��A�b�͖������������Y���̊��Ғl�͒Z���Ȃ��Ă��܂��B�܂薧��������������I�Ȃ̂ł���B�]���āA�b�͖�������̂ł���B
�t�ɁA���̗���ɂ������ꍇ�A�܂������������_�����̑�����Ȃ����B�]���āA������������̂ł���B
�]���āA�b���Ƃ���3�N�̌Y���߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���݂��ɖ���������Ȃ������ꍇ�ɂ͂��݂���1�N�ōςނ̂ł��邩��A���̕����ǂ��l���Ă��D�܂����悤�Ɏv���邪�A�b���������I�ɍs������Ƃ��̂悤�Ȍ��_�͏o�Ă��Ȃ��B���݂�������Ƃ��낪�Ȃ��ɂ�������炸�i���݂�������Ƃ��낪����̂́A���݂����������Ȃ������ꍇ�j�A���݂��ɖ����������Ƃ������_�Ɍ��ѕt���Ă��܂��̂ł���B
�l�A���邢�͌ʂ̊�ƂƂ��č����I�ȍs�����Ƃ��Ă���ɂ�������炸�A�Љ�S�̂Ƃ��Č���A�s���v�Ɍ��ѕt���Ă��܂����Ƃ���A�u�W�����}�v�ƌĂ�Ă���̂ł���B
4.4.2�p���I���l�̃W�����}
����������̃`�����X�����Ȃ��u���l�̃W�����}�v�́A�r�W�l�X�̏�ʂŌ����A�ꌩ�̋q���X���Ɍ��ꂽ�ꍇ�Ȃǂɓ��Ă͂܂�̂ł��낤�B���i�鑤�ɂ��Ă݂�A�ǂ̂��炢�����C������̂����炸�A�p���I�ɔ����Ă���邩�ǂ���������Ȃ��ꌩ�̋q�ɂ́A���z�ǂ����邾���J�̖͂��ʂɎv���Ă��܂��A���͓I�ȉ��i�����Ăł��Ȃ��ł��낤�B
����A�q�̑��ɂ��Ă݂�A�X�̐M�p�����ĕ���Ȃ����A�A�t�^�[�T�[�r�X������Ȃ��B�M�S�ɔ����C��������A�����l�i�𐁂��������邩������Ȃ��B�]���Ă�����ĂŌ��ɗՂނ��ƂɂȂ�B
���ʔ������͕s�����ɏI���B
����ł͉i���ɉ����N���Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂����A���ۂɂ͌��Ȃǂŕ��݊�肪�\�ȏꍇ�������̂ł͂Ȃ����낤���B
���̂悤�Ȏ�����p�^�[���������̂��A�p���I���l�̃W�����}�ł���B
���̏ꍇ�́A��L�̂悤�Ȗ������邩���Ȃ����ł́A����Q�[�����������Ȃ��̂ŁA���݂��ɐԂƍ��J�[�h��������悤�ɂ���B
���݂��̃J�[�h�̏o�����ƁA���_�p�^�[���͉��L�̂悤�ɂȂ�B
|
A�̑I��╲B�̑I�� |
�� |
�� |
|
�� |
A 2�_ B 2�_ |
A �|5�_ B 5�_ |
|
�� |
A 5�_ B �|5�_ |
A �|1�_ B �|1�_ |
��L���l�̃W�����}�Ɠ����悤�ɁA���ꂪ1���̃Q�[���ł���A���݂��ɕ����܂��Ƃ���A�����o�����ƂɂȂ�B
���̂悤�ȃQ�[�����ɌJ��Ԃ��ꍇ�ɂ́A�uTIT FOR TAT�v�ƌĂ��헪�i������TIT�헪�Ƃ������B�uTit for tat�v�Ƃ́A�����ؕԂ��̈Ӗ��j�������Ƃ��L���ł���Ƃ����Ă���B
TIT FOR TAT�헪
1. 1��ڂ͋����I�헪������āA����̏o��������i�܂�Ԃ��o���j
2. 2��ڈȍ~�́A�O�肪�o�����̂Ɠ����J�[�h���o���B���肪�����I�ȍs�����Ƃ���̂܂܋����I�s���𑱂��邵�A���肪��������o���������Ƃ��č����o���A���̎��̉�ɂ͂�����������o���ă��x���W����̂ł���B
�܂�A�ŏ��͂��݂��̋��������҂��Ă���U������邪�A��U���肪�������ꍇ�ɂ́A�ґR�Ɣ����ɑł��ďo��̂ł���B�����āA���肪���Ȃ��Ă�����x�����I�ȍs�����Ƃ����ꍇ�ɂ͋����Ă��̂ł���B
�Ȃɂ��A���ݐ��E�ŗB��̒��卑�ƌĂ�Ă��鍑�̊O��헪�Ƃ҂���ƕ������Ă���悤�ȋC�����邪�@���ł��낤���B
���ۂɂ��̃Q�[�������C���Ŏg���Ɓi���ۂɃQ�[��������ꍇ�ɂ͗L����̎��s�ɂȂ��Ă��܂����j�A���݂��ɍŏ����獕���o�������Ă��܂��ꍇ�����������ł���B
4.4.3����r�W�l�X�E�Q�[��
�Q�[���̓��e�͏�L�̌p���I���l�̃W�����}�Ɠ����ŁA������̉J��Ԃ����B�]���āA���_�z�����͏�L�Ɠ����ł���B
�������Q�[���̃��[���͈ȉ���2�ł���B
l �Q�[���̖ړI�͏����ƁB
l �����߂̏����́A�ŏI�t���[���ɗݐς��ꂽ�v���X�̃|�C���g���ł��邾���傫�����邱�ƁB
�Ƃ������̂ł���B
���̃Q�[���͎������ۂɑ̌��������̂��č\���������̂ł���B
���̃Q�[�����A��L�̌p���I���l�̃W�����}�Q�[���Ɠ����ł���Ƃ���A�r�W�l�X���C�Ƃ��Ď��グ��ɂ͗]��ɂ��|���Ȃ��B�����C�������������́A������x�Q�[���̃��[�����������Ă݂��B�����ŋC�������̂́A�ړI�͏����Ƃł���Ƃ����Ă��邪�A�u����Ɂv���Ƃ͂����Ă��Ȃ����ƁA�����߂̏����͓��_���v���X�łȂ��Ă͂����Ȃ����ƂɋC�������B
���݂��Ƀv���X�����߂�ɂ͂ǂ����邩�B�����͊ȒP�ŁA���݂��ɋ����I�s�����Ƃ�i�Ԃ��o���j�悢�̂ł���B
�����ł킪�`�[���͐Ԃ��J�[�h������̂ł��邪�A����͉��ƍ����J�[�h����Ă����B����͂��̃Q�[����T�^�I�Ȏ��l�̃W�����}�E�Q�[���ł���Ƃ݂Ȃ��Ă���̂ł���B�܂�A�u���v�Ƃ́u����ɏ��v���Ƃł���Ɩ������ɐM���Ă��܂����̂ł���B
���̂Ƃ��A�킪�`�[���͂ǂ̂悤�Ȕ�����������̂ł��낤���B���́A������Ԃ��o���������B���R�̈�ɂ́ATIT�헪��N��l�Ƃ��Ēm��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��B�������A����`�[���ɋ����I�Ȑ헪�����Ȃ��ẮA���݂��ɃQ�[���ɕ����Ă��܂��Ƃ���������̃��b�Z�[�W��`����ɂ́A���ꂵ�����@���Ȃ���������ł���B
���ʓI�ɂ́A�������������̃��b�Z�[�W�ɋC�t���A���݂��ɐԂ��J�[�h���o���������ƂōŏI�I�ɗ��`�[���Ƃ����������߂邱�Ƃ��ł����̂ł���B
���ʂ͂Ƃ������Ƃ��āA���̃Q�[������������Ƃ���͏d��ł͂Ȃ����낤���B����r�W�l�X�ɂ����āA�������ЂƋ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ꍇ�Ƃ����̂́A��ϑ����Ǝv����B
���肪����������ƌ����đ����ɂ���������V����A�Ƃ����̂ł́A�Ή��ł��Ȃ��ꍇ������̂ł͂Ȃ����낤���B
������A���鐶���ی���Ђ��������Ђ̐M�p�x���G���̋L���ȂǗp���ĕs���ɒ����E��掂����A�Ƃ���鎖�����������i����1�Q�Ɓj�B����ɑ��ẮA���Nj��Z�����s���������������̂ł��邪�A���ۂɂ́A���Ȃ���ʐ����ی���Ђ������悤�ȍs�ׂ����Ă����Ƃ����B
�܂�A����������Ă���̂�����A���Ԃ��Ă��A�Ƃ����킯�ł���B�Ƃ���ŁA�����̐����ی���Ђ̔j�]�ȗ��A����҂̐����ی���Ђɑ���s�M���ɂ́A���������̂�����B���ۂɐ����ی��_��c���́A1995�N���s�[�N�Ƃ��Č��葱���Ă���B�������A�i�C�S�̂̉e��������̂ł��낤���A�����ی���Ђ̌���ɂ���ƁA�����ی���Ђւ̕s�M�������������Ƃ�����������B
�}4 �ۗL�_��y�э\����̐��� ���z ���~
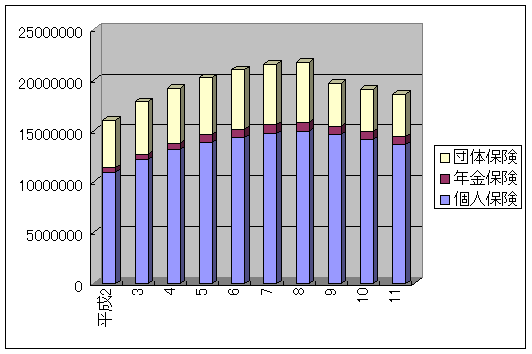
����11�N�x�ۗL�����x�[�X�ł́A�l�ی�1��1,587�����A�l�N���ی�1,403�����A�c�̕ی��̖���ی��Ґ�7,824���l�ɒB���Ă���B
�i�o�T�i���j�����ی������Z���^�[�w2000�N�Ő����ی��t�@�N�g�u�b�N�x�j
���̂悤�ȏŁA�������Ђ��掂��Ď��Ђ̌_��������܂�Ȃ��Ƃ����̂́A�]��ɂ���O����ł��낤�B�����āA�������Ђ܂œ����s�����Ƃ�����ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B
�p���I���l�̃W�����}�̍��ɂ����Ă��钴�卑�̂��Ƃ𝈝��������A�r�W�l�X�̌���ɂ����ẮA���́u�p���I���l�̃W�����}�v�A���邢�́u����r�W�l�X�E�Q�[���v�ɂ����Ē����悤�ȏ͑�ϑ����̂ł͂Ȃ����낤���B
4.5�@Win�|Win�헪
��L�̂悤�ɁA�����Ɋւ��o���������s���悤�Ȍ��ʂ������炷�悤�ȉ������@��Win-Win�@Solution�ƌĂԁB���݂��ɖ����ł���̂ł���A���҂Ƃ��ɏ��҂ł���ƌ�������A�Ƃ������Ƃł���B
�Ⴆ�A��L�ی���Ђ̗�ł����A�ی���Ђ����݂��ɔ�排���������J��Ԃ��̂ł͂Ȃ��A�����ی��̏d�v���������̊ԂɌ[�����邱�Ƃɂ���āA�ی���БS�̂̃p�C�������ɑ��₷�����l����̂ł���B�Е����������҂ƂȂ�A������������W�iWinner-Loser�j�̏ꍇ�ɂ́A�������ق��͏�Ɏd�Ԃ��̃`�����X�������������ƂɂȂ�����A���݂��̂��߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƕ����Ă��Ă�������������悤�ȍs�����Ƃ����肵�����ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�����I�ɂ͂��݂��ɔs�҂ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
5.���Z�ƊE�ɂ�����R���v���C�A���X
���Z�E�ɂ����ẮA����Ҍ_��@�A���Z���i�̔��@�����ɕ���13�N4��1���Ɏ{�s�����ȂǏ��@�߂̐������i�B�܂��A���Z�������Z�@�ւɑ��čs�������ɂ��Ă��A���̊�ƂȂ錟���}�j���A�������\���ꂽ�B����́A�]���̌쑗�D�c�����A�ٗʍs������̌��ʂ��Ӑ}�������̂ł���B�u���Z�����ɂ��ẮA����10�N�Ɂu�V�������Z�����Ɋւ����{�����ɂ��āv�i������140���j���߁A���ȐӔC�����̓O��Ǝs��K������ɁA���m�ȃ��[����O��Ƃ����������̍����s���ւ̓]����}���Ă��Ă���Ƃ���ł���B����11�N�ɂ́u�a����������Z�@�ւɌW�錟���}�j���A���v�A����12�N�ɂ́u�ی���ЂɌW�錟���}�j���A���v���߁A����ɂ��A�ē��ǂ̌����ē@�\�̌���y�ѓ����ȍs���̊m���݂̂Ȃ炸�A���Z�@�֓��̎��ȐӔC�Ɋ�Â��o�c�𑣂��A�����ċ��Z�Ɛ��S�̂ɑ���M���̊m����}���Ă���Ƃ���ł���v�i���Z���u�،���ЂɌW�錟���}�j���A���ɂ��āv������170���j�B����ɁA����13�N�ɂ́u�،���ЂɌW�錟���}�j���A���v�����肳��A��\�I3�Ǝ�̋��Z�@�ւɊւ��Ă̌����}�j���A�����o�������B���̌���ׂ��ȕύX�E�������������A���Z�������̍ۂ̉^�p��ƂȂ��Ă���B
���Z�������}�j���A���̈ʒu�t���́A�����܂ł������������Z�@�ւ���������ۂɗp���������ł���Ƃ���Ă���A�����}�j���A���̍��ڂ��ꎚ���߂����Ɏ��s���邱�Ƃ����߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�t�ɁA���ꂼ��̋��Z�@�ւ����ȐӔC�̌����̉��A���ꂼ��̋K�́E�����ɉ������Ǝ��̃}�j���A�����쐬�A���s���邱�Ƃ����߂��Ă���B�����ɂ������Ă��A�����}�j���A�����@�B�I�E���I�ɓK�p���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɔz�����邱�Ƃ����߂��Ă���B�������A�`�F�b�N���ڂ̌�����u���Ă��邩�v�܂��́u�Ȃ��Ă��邩�v�Ƃ���̂́A���ɂ��Ƃ��̂Ȃ����肷�ׂĂ̋��Z�@�ւɃ~�j�}���E�X�^���_�[�h�Ƃ��ċ��߂��鍀�ڂł���Ƃ���Ă���B���ۂ̃`�F�b�N���X�g���ꗗ����Ε���Ƃ���A���͂قƂ�ǂ̍��ڂ���L�̂悤�Ȍ���ŏI����Ă���̂������ł���B
�]���Ƃ͈قȂ�A���Z�@�ւɂ͎��ȐӔC�̌����̉��ŃR���v���C�A���X�������E���{���邱�Ƃ����߂��Ă���B�]���͌쑗�D�c�����E�ٗʍs���̉��ł���̂������ق��ĕ����Ă���悩�����̂ł��邪�A���݂͂����͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B�ꌾ�Łu���ȐӔC�v�Ƃ����Ă��A���̎w���������ǂ̂悤�ɂ��ׂ��ł��邩�����Ă���̂�����ŁA���̈�[�������ی��ƊE�Œ[�������I�悳�ꂽ�̂��O�q�̔�掁E���������ł������̂��낤�B
���Z�ƊE���[���O�q�̃l�b�g���[�N�Љ�Ɏ�荞�܂�Ă���BWin-Win���_���L���ɋ@�\����̂ł͂Ȃ����낤���B
5.1�R���v���C�A���X�ƃ��[�_�[�̖���
�R���v���C�A���X���������Ă�����ŁA���[�_�[�̖����͂���߂đ傫�����̂�����B�R���v���C�A���X�́A�P���ɖu�@�ߏ���v�ł��邩��A���ɓI�ɂ͖@�߂��`���I�ɏ��炵�Ă���Ύ������悤�ȋC������B�������A���ݎЉ�I�ɋ��߂��Ă���R���v���C�A���X�́A�P�Ɍ`���I�ɖ@�߂���邱�Ƃ����߂��Ă���̂ł͂Ȃ��A���ϋɓI�ɎЉ���߂Ă��鍂�x�ȋK�͂���邱�Ƃ����߂��Ă���̂ł���B
���̂��Ƃ́A�ŋ߂̑�a��s�����ɂ�������n���ٔ����̔����ɂ�����Ă���B���̎����ł́A����830���~�Ƃ������z�̑��Q�����z���b��ƂȂ�A���Ǐ��@���̂��̂������\�i�ׂ̔����ӔC�ɏ����ݒ肷��`�ŏ��@���������������i2001�N12��5���Q�c�@�{��c�ɂ����ĉ��j�B�������A���̔������̂��̂͌��ǁA�u�����������z2��5000���~����s���Ɏx�������ƂȂǂ������ɑ��n�فi���������ٔ����j�Řa�������������v�ihttp;//kabu.zakzak.co.jp/news/kiji/2001121100.html (2001/12/11)�j�B
�������A�����̒��ŁA������̒��Ӌ`���ƒ����`���ɂ��ẮA��ό��������߂Ă���A���̊�ɓK�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A������l�ւ̑��Q������F�߂�i���z�͕ʂƂ��āj�����ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv����B
�����̒��ŁA�u������́A�݂�����@�߂����炷�邾���ł͏[���łȂ��A�]�ƈ�����Ђ̋Ɩ��𐋍s����ۂɈ�@�ȍs�ׂɋy�Ԃ��Ƃ𖢑R�ɖh�~���A��БS�̂Ƃ��Ė@�ߏ���o�c���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�u������́A�]�ƈ����E���𐋍s����ۈ�@�ȍs�ׂɋy�Ԃ��Ƃ𖢑R�ɖh�~����@�ߏ���̐����m������`��������A������܂��A������̑P�ǒ��Ӌ`���y�ђ����`���̓��e���Ȃ����́v�ł���Ƃ��Ă���B�܂��A�u��������������ȊO�̎����ɂ��Ă��A�Ď��`�����̂ł���A���X�N�Ǘ��̐��̍\�z�ɂ��Ă��A���ꂪ�K���ɍs���Ă��邩�Ď�����`��������v�ƁA������̓��[�_�[�Ƃ��Ď���R���v���C�A���X�����s���邾���łȂ��A��ЂƂ��ăR���v���C�A���X�����s�����邽�߂̋Ɩ��S�ʂɐӔC���Ƃ��Ă���B�i�ȏ���p�́A���n�ّ�10����������12�N9��20������ �{�������@��1573���j
�č��ɂ����Ă��A���l�̔�����1996�N�ɏo����Ă���B�P�A�}�[�N�E�C���^�[�i�V���i���E�f���o�e�B�u�i�����i�f���E�F�A�B��@���ٔ���1996�N9��25���ANo.13670�j�ł���B
�P�A�}�[�N�Ђ́A����ÃT�[�r�X��Ђł������B�P�A�}�[�N�Ђ̃T�[�r�X��p����悤�ɁA��t��ɕs�@�ȋ��t�����x�������Ƃ��đi�����A�����A�ُ����̑���2��5�疜�h�����̎x����������ꂽ�B����ɑ��āA������̊ēӔC��Nj����邽�߁A���傪�i�����N�������̂ł���B
���̎����ł́A������͐ӔC�����Ȃ������B���́A�P�A�}�[�N�Ђ̓R���v���C�A���X�ɑ��Ă͂��Ȃ�ϋɓI�ɑΉ����Ă����̂ł���B���{�̍��@������ȑO����ACFO���R���v���C�A���X�E�I�t�B�T�[�ɔC���A����ɏ]�ƈ��ɑ��ėϗ��E�R���v���C�A���X���C�����{�A�č��E�ϗ��ψ����݂���Ȃǂ��Ă������Ƃ��]�����ꂽ�B
�A���A�ٔ����͖������Ŏ�����̐ӔC��Ə������̂ł͂Ȃ������B��������Г��ɃR���v���C�A���X�E�V�X�e�����\�z���A�����ϋɓI�ɊĎ����Ă���ꍇ�ɂ́A������i�y�я㋉�����j�́A��Џ]�ƈ��ɂ�����������m�ł���s���s�ׂɑ��ċN�����ꂽ�i�ׂɂ����Ă��̐ӔC����Ƃ�邱�Ƃ��ł���Ƃ��ꂽ�B���R���̔��ł���ꍇ�ɂ́A�ӔC�������B
������ɂ͐ϋɓI�ɃR���v���C�A���X�ɌW�邱�Ƃ��v������Ă���B���܂ł̂悤�ȁu�m��Ȃ������v�ł͂��܂���Ȃ��̂ł���B�i�P�A�}�[�N�ЂɊւ��鎖��Dawn-Marie
Driscoll, W. Michael Hoffman, Ethics and
corporate governance: Leadership from the top�j
�č��ɂ����Ă��A���̔������ЂƂ̊�Ƃ��Ċ�Ƃ̃R���v���C�A���X�ɑ����g�݂��傫���ω����������ł���B
�ȏ�̔����Ɠ��l�ɁA���Z���̌����}�j���A���ɂ����Ă�������y�ю������̖�������Ϗd������Ă���B����́ABIS���|�[�g�iBank for International Settlement , Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations�j���Č��肳�ꂽ���̂ł��邪�A�����͈�a���������Ď���ꂽ�B
���{�ɂ����ẮA�������͂��Ȃ�`�[�����Ă���A������Ƃ����ǂ��o�c�w�̈���Ƃ������́A�P�Ȃ鍂���T�����[�}���ł���ꍇ�������A�����I�Ȍo�c���͏햱��̂�荂�x�Ȍo�c�@�ւ������Ă���ꍇ�����������B
�������Ȃ���A���@�̋K���A��Ƃ̍ō��ӎv����@�ւ��������ł���A���̍ō��ӔC�҂���\������Ȃ̂ł���B�R���v���C�A���X�̖��Ɋւ��ẮA����������[�_�[�Ƃ��ăR���v���C�A���X�𗦐���s���Ă������Ƃ����߂��Ă���B�������A�o�c�`�Ԃɍ��킹�āA���s������A���̑��̎�����ɑ���������̂�������ɑ����Ă��̖�����S�����Ƃ��F�߂��Ă���B
���Z���̌����}�j���A���́u������̈ӎ��v�̊m�F�Ƃ������ڂɂ����āA
l �u�R���v���C�A���X�Ɋւ��ẮA����������������搂�͂��Ď�g��ł��邩�B�܂��A�������́A�����E�Ɨϗ��ς����{���A�����E�K�ɂ�����E���y�ѕی���W�l�ɑ��ĂȂ����Ǘ��̏d�v���������E�������镗�y��g�D���ɏ�������ӔC���ʂ��Ă��邩�B�v
l �u��\������́A�N�������⋒�_����c���A�\�ȋ@����Ƃ炦�A�@�ߓ�����ɑ����g�ݎp���������Ă��邩�B�v
l �u������̓R���v���C�A���X�S��������c�ƕ���Ɠ��l�Ɉʒu�t���A�K�Ȑl�ނƋK�͂��m�ۂ��A�S�������ĊǗ�����ƂƂ��ɋƐѕ]���A�l���l�ۂɂ����ēK�ȕ]����^���Ă��邩�B�v
l �u��������g���A�Г��O�̃R���v���C�A���X�̖��ɑ��A�K���Ɋ�Â��A�����A�����ɒf�łƂ����p���őΉ����Ă��邩�B�v�i���Z���u�ی���ЂɌW�錟���}�j���A���v�j
�Ƃ������_�����߂��Ă���B
�P���ɖ@�߈ᔽ�������܂�̂ł���A�R���v���C�A���X�ᔽ�������܂镔����݂��ăR���v���C�A���X�ᔽ�̌������E��������A���邢�͌��ʂ����邩������Ȃ��B�������A�R���v���C�A���X�Ƃ͒P�Ȃ�@�ߏ���łȂ��A��荂�x�Ȋ�Ɨϗ��̎��H�ł��邱�Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B�����āA������ɂ́A��ƑS�̂̃R���v���C�A���X���i�����߂��Ă���̂ł���B
�Ⴆ�A��ƕ��j�Ƃ��Čڋq�d�����f���Ă��Ă��A�̔��S���̎�������u�Ƃɂ���1���ł��������甄���L���v�ƞ������Ă����疳�Ӗ��ł���B
����ɁA�ŋ߃R���v���C�A���X�Ɋւ��Ė��ɂȂ�̂́A���ю�`�ƃR���v���C�A���X�̊W�ł���B�����̎��сi�����j�̍���ɔ��f�����͔̂��オ�قƂ�ǂŁA�R���v���C�A���X�����炵������Ƃ����ċ������オ��킯�ł͂Ȃ��i�������R���v���C�A���X���ᔽ�Ƃ��ēE�������Ή��炩�̏������������̂ł��낤���j�B�̔��̌���ɂ���҂ɂƂ��ẮA�R���v���C�A���X����̂��߂ɕK�v�Ƃ����菇�͂Ȃ�Ƃ��ς킵���ꍇ�������A����Ȃ��̂�n�������Ɏ���Ă������1���ł������_�����肽���Ƃ����U�f�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B������Ƃ����āA�R���v���C�A���X�ᔽ�ɑ��鏈�������������Ă����̂ł́A�̔��������̂��̂��ޏk���Ă��܂��B
�����Ŗ{�e�ɂ����Ē�Ă���̂��AWin-Win���_���R���v���C�A���X���i�̊�{�����Ƃ��Ď��グ����̂ł���B
5.2�R���v���C�A���X��Win-Win���_
Win-Win���_�̂����Ƃ��P���ȃR���v���C�A���X�ւ̓K�p�́A��ƂƏ]�ƈ��Ƃ̊W��TIT�헪�����p���邱�Ƃł���B�܂�A�����͏]�ƈ��ɑ��ėZ�a�I�Ȑ�������A�����R���v���C�A���X�ᔽ�������ꍇ�ɂ́A������������^����Ƃ������̂ł���B
�����ɁA�R���v���C�A���X�d����ł��o�����߂ɐE���ɑ���ܔ��K������肵�A������������������A�������^������ΏۂƂȂ�]�ƈ��̍s���͈͂��L�ߖ�����������Ƃ��������Ƃ͈�ʓI�ɍs���Ă���B�������A�������݂̂ŃR���v���C�A���X���ێ����Ă������Ƃ�������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B
�܂��A��ƂƏ]�ƈ��Ƃ̊W�ɂ����ēK�p���ł����Ƃ��Ă��A�O�q�����悤�ɁA�Љ�̓l�b�g���[�N�����Ă������Ƃ��\�z����Ă���B�R���v���C�A���X�ᔽ���������Ƃ��āA�]�ƈ����������������́A���͏I���Ȃ��B
�ŋߘb��ɂȂ��������Ƃ̏W�c�H���Ŏ����i����2�j�A�O�H�����Ԃ̃��R�[���B�������i����3�j�Ȃǂ����Ă��A���̉e���͈ᔽ�҂�P���ɏ�������Ƃ��������Ƃł͎������Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�Љ�̓l�b�g���[�N�����Ă��邩��ł���B�����Ƃ̏W�c�H���Ŏ����ɂ��Ă��A���͐H���ł��N�������l�Ɛ����Ƃ̖��ł͂Ȃ��A��ʏ���҂Ɛ����Ƃ̖��A���邢�͓����ƂƐ����Ƃ̖��Ɋg�債�Ă���B����͎O�H�����Ԃł������ł���B���Ђ̓R���v���C�A���X�ᔽ�ɑ��鏈�����͂邩�Ɍ������Љ�I���ق��A�Ɛт̈����Ƃ����`�ł����ނ��Ă���B
Win-Win���_�́A�Г��݂̂Ȃ炸�A�Όڋq�A������ƁA�Ή�������ƂȂǁA��������ʂɑ��ēK�����Ă����w�͂��K�v�Ƃ���Ă���̂ł���B�܂��A���̂悤�ɍl����ƁATIT�헪�͎��͂��܂���ɗ����Ȃ����ƂɋC�t�����Ǝv���B
���́ATIT�헪���L���ɋ@�\����̂́A�����ؕԂ����m���ɑ���Ƀ_���[�W��^������ꍇ�ł���B���̏ꍇ�A����ɑ��Ď������D�ʂȗ͂������Ă��邩�A���Ȃ��Ƃ��Γ��̗͂������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ʏ킻�̗͊W���u�₵�Ă����ƑΌڋq�Ȃǂ̊W�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��ł��낤�B�������A���̗͊W�́A�l�b�g���[�N�Љ�ɂ����镗�]��Q�̎���Ȃǂ�����ƁA���͈��肵�����̂ł͂Ȃ��A�ӊO�Ƃ��낢���̂ł��邱�ƂɋC�t�������B�܂��A�������ЂƂ̊W�ɂ����āA�P���Ȃ����ؕԂ��헪���D�܂����Ȃ����Ƃ͕ی���Ђ̔�排��������Ŏ��グ���Ƃ���ł���B
���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�Ȃ��R���v���C�A���X���K�v�Ȃ̂��A�R���v���C�A���X���ǂ̂悤�Ɏ��H���Ă������Ƃ��������Ƃɑ��āAWin-Win���_���L���ɉ��Ă���邱�ƂɋC�t���B
�Ȃ��R���v���C�A���X���K�v�Ȃ̂��B�R���v���C�A���X�͑���Ƃ̋����W��ۂ������Ă�����ŁA�K�v�����ׂ��炴����̂�����ł���B�Όڋq�W�ł́A��Ƒ�������I�ɂ��̃o�[�Q�j���O�E�p���[�𗘗p���Ċ�ƂɂƂ��ėL���ȗ��ꂩ���������v���Ă͂Ȃ�Ȃ��BWin-Win�헪�Ɋ�Â����A��ƂɂƂ��Ă��A�ڋq�ɂƂ��Ă��D�܂������ʂ�������ł��낤�헪���Ƃ��ď��߂ĉi������ǍD�ȊW���z����̂ł���B�t�ɂ����A�l�b�g���[�N�Љ�ɂ����ẮA����Ɉ��Ղɕ�I��������悤�Ȑ헪�͍D�܂����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�ЂƂ�ЂƂ�̌ڋq�̂����ؕԂ��ȂǑ債�����Ƃ͂Ȃ���������Ȃ����A���ꂪ�܂Ƃ܂��Ĉ�U�M���W�����Ȃ���ƁA�C���s�\�ɂȂ��Ă��܂��B
����ł́A�R���v���C�A���X�͂ǂ̂悤�Ɏ��H���Ă����̂��BTIT�헪�ł������Ƃ���A�Ƃɂ����ŏ��͑���̍s���ɂ������Ȃ������I�ȍs�����̂邱�Ƃł���B�R���v���C�A���X��ɋ��v���Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ł́A���肪�R���v���C�A���X�ɊO���s�����Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ǂ̂悤�ȍs�����D�܂����̂ł��낤���BTIT�헪�̋�����Ƃ���͂����ؕԂ��ł���B
�������A�Ⴆ�Ί�ƑΏ]�ƈ��Ƃ������v���ȏ������O���Ƃ̊W�ɂ����ėv�������ꍇ�������ẮATIT�헪���L�����Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȃ����B����́A�u����r�W�l�X�E�Q�[���v�̍��ł����グ�����Ƃł��邪�A����ɂ�����̃��b�Z�[�W��`���邽�߂ɂ́A�����炪�����I�s������葱����K�v�����邩��ł���B�Q�[���̗��_�ł́A����Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������Ȃ��Ƃ����O��̉��Ő헪���g�ݗ��Ă��Ă���B�Ƃ��낪�A�����ɂ̓R�~���j�P�[�V�������\�ȏꍇ�������B
�u����r�W�l�X�E�Q�[���v�̍u�]�ŏo�Ă����|�C���g�̂ЂƂɁA����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������}��邩�ǂ��������������Ƃ������̂ł������B�������A���̏ꍇ�̓Q�[���ł��邩��A����Ǝ������킹�ċ����I�s�������Ƃ������Ƃ̓��[���ᔽ��������Ȃ��B�������A�����̃r�W�l�X��ł��̂悤�Ȗ�肪�������ꍇ�A�R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ͏d�v�ł���A�܂��K�������s�\�ł͂Ȃ��ł��낤�B����ɂ͂�����̃��b�Z�[�W���`����Ă��Ȃ��ƈ���I�Ɍ��_���ĕs���ɏo��̂͑�l�C�Ȃ��Ǝv���邪�������ł��낤���B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A��ƍs���͒P��̑���ɑ��Ă����ł͂Ȃ��A�L���Љ�ɑ��郁�b�Z�[�W���܂�ł���̂ł���B
���́A�p���I���l�̃W�����}�Q�[���̎��H�����͗ϗ��w�̕���Ői�߂��Ă���B�����ł́A�����ɕ���������́A���肪�}�ɏ�����Ƃ��Ɋm���ɕ����ق������ʓI�ł���Ƃ������X�������炩�ɂ���Ă���悤�ł���i���c�@���Y�u�u���l�̃W�����}�v����v http://www.ethics.bun.kyoto-u.ac.jp/~okuda/ethics/dilemma.html �i2001/12/19�j�j�B�Q�[���̗��_�ɂ��ẮA�ʍe�ɂ����āA���ڂ������グ��\��ł���̂ŁA�{�e�ɂ����Ă͂���ȏ�̒Nj��͍s��Ȃ��B
6.�����^���[�_�[�V�b�v���狤�n�^���[�_�[�V�b�v��
�]���̂悤�ȃs���~�b�h�^�g�D���ێ������Ȃ��Ȃ��Ă����ł��낤���Ƃ́A�{�e�ɂ����Ė��炩�ɂ��Ă����Ƃ���ł���B���̏ꍇ�A���[�_�[�Ɋ��҂����������]���Ƃ͑傫���قȂ������̂ɂȂ邱�Ƃ��\�z�����B
���̂��Ƃ��䉮�@����́u�O���`����̒E�p�v�Ƃ������t�ŕ\���Ă���B�u�u�O���`�v�Ƃ́A�u�O�N��v�u���Д�v�u�\�Z��v�́u�O��v��]����ɂ���o�c�A�܂��͑g�D�Ǘ����@���B�����̓��{�ł́A�u�O���`�v����Ƃ̋Ɛт�]�������Ƃ��Ĉ�ʉ����Ă��邪�A���͂��ꂱ���u�g�呦���v�v�̔��z�𐧓x�������������g��u���̕\��ł���v�i�䉮 ����w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��xp285�j�B�������A���̂悤�ȋ��������Ă����ƁA�u���{�Љ�S�̂��S�[���̂Ȃ������n���Ɋׂ��Ă��܂��̂ł���v�i�䉮 ����@�w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��xp286�j�B
�����ŁA�����Љ�猈�ʂ��A���n�^���[�_�[�V�b�v�����B
6.1���n�^���[�_�[�V�b�v�Ƃ͂Ȃɂ�
���n�^�̃��[�_�[�V�b�v�Ƃ́A�ȉ��̂悤�ȓ����������̂ł���B
l Win-Win�헪�̂悤�ȋ����I�헪���A�g�D���݂̂Ȃ炸�A�g�D�O���Ƃ̊W�ɂ����Ă��K�p����B
l �l�ޕ]���ɂ����āA�O���`��E���A���I���ʂ̕]�����d������B
l �C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW���f����
�Ȃ�Win-Win�헪�̗̍p�ɂ�鋭���I�헪���K�v�ł��邩�B�O�q�����悤�ɁA�Љ�̑g�����̂��̂��ω����Ă��錻�݂ɂ����āA������o���������Ƃ���헪����葱���邱�Ƃ́A����Ƃ͂����Ȃ��B���ɁA���݂̃r�W�l�X�ɂ����ẮA��x�蒅�����C���[�W�����Ƃ͂���߂ē���B�t�ɗǂ��C���[�W��蒅������ɂ͒������Ԃ��K�v�ɂȂ�B�ł���Ƃ���A�����I�헪����葱���邱�Ƃ̐��������e�Ղł��낤�B
�蒅�����C���[�W���̂������ɍ���ł��邩�������ȉ��̂悤�Ȉ�b������B�C�^���A�ő�̎����ԃ��[�J�[�ł���t�B�A�b�g�E�O���[�v�ɁA�����`�A�Ƃ����u�����h������B��O�Ԓ��S�̃t�B�A�b�g�ɑ��āA�ǂ��炩�Ƃ����ƍ����A�㎿�Ȏԍ��ɓ���������B�����`�A�̓��[���b�p���ł��A�C�^���A�A�t�����X�A�I�����_�Ƃ������n��ł͑����̔���������Ă���̂ɑ��A�C�M���X�ł͂����ς蔄�ꂸ�A�ŋ߃C�M���X����P�����Ă��܂����B1970�N��ɒ蒅�����A�K�т₷���Ƃ����C���[�W���Ȃ���������ł���B�͂����肢���āA1970�N��̎����ԂȂǁA�ǂ���K�т₷�������̂ł���A���d��Ȍ��ׂ��������Ԃł��������Ă����ɂ�������炸�A�C�M���X�ł̓����`�A�͎K�т₷���Ƃ����C���[�W���蒅���Ă��܂����̂ł���B���̌�A�]���̗ǂ��Ԃ���葱���A���[���b�p�嗤�ł͈��̕]�������Ђ��A�C�M���X�ł̈��]�͕����Ȃ������̂ł���B
�l�ޕ]���ɂ��ẮAFSA�̋��Z�����}�j���A���ł��������Ă���Ƃ���A�ߓx�̋Ɛяd���̓R���v���C�A���X���A���邢�͌y�����镗���݂₷�����Ƃ́A�O�q�̂Ƃ���ł���B
�������A���I�]���͓���B�E�F���`�����̂悤�ɏ����Ă���B�u���̂悤�ɐl���]���͔��Ɍ��i�ł���ɂ�������炸�A���N�̎Ј��̈ӎ������ł͋����ׂ����ʂ��o�Ă���B42�̎���̂����A�����x�������Ƃ��Ⴂ�̂��A���̎��₾�������炾�B�v�u�u���Ђ́A�����̂������ʂ������Ă��Ȃ��Ј��ɑ��Ēf�łƂ����p�����Ƃ��Ă���B�v�v�u2001�N�̒����ł́A���̎���ɃC�G�X�Ɠ������Ј���75�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ��B99�N��66�p�[�Z���g����͉��P���Ă��邪�B�ق��̎���ł͂����ȂׂĖ����x�������̂ɔ�ׁA���̐����͋ɒ[�ɒႢ�iGE�ł̃L�����A�́A�u������Ƒ��ɍD�܂����e����^���Ă���v�Ƃ������ڂɂ��ẮA90�p�[�Z���g�ȏオ�C�G�X�Ɠ����Ă���j�v�i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��pp262�j�����ł���B���̌��ʂɑ��ăE�F���`�́A�u���̌��ʂ́A�ǂ̃��x���ł��I�ʂ������ɏd�v�ł��邩�������Ɠ����ɁA�Ј��̂ق�������ɑ�_�ŗ����ȕ]����]��ł��邱�Ƃ������Ă���v�Ǝ��掩�^���Ă���B
���ɂ́A���̓��v���l�́A����ɑ�_�ȕ]�������߂Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����ɑ����]���ɑ���s���ƁA���l�ɑ��鍂�]���ւ̔����������悤�Ɏv����̂ł��邪�������ł��낤���B�������ɁAGE�͋ɂ߂đ�_����i�I�Ȑl�ޕ]���������A���H���Ă����Ƃł���B����ɂ�������炸�A4�l��1�l�A���̑O�N��3�l��1�l���]���ɖ������Ă��Ȃ��̂ł���BGE�Ј���30���l�����Ƃ���ƁA7��5��l���s���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���������A30���l�̎Ј����ЂƂ̉��l�ς̉��ɕs���Ȃ��]�����邱�ƂȂǕs�\�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B����ȂƂ���ɂ��A����s���~�b�h�^�g�D���I�����}����v��������̂ł͂Ȃ����낤���B���̑g�D�����^������l�b�g���[�N�^�g�D�ł́A�]�������鑤���]������鑤���[���̍s���]�������₷���Ȃ�ł��낤���A�g�D�Ƃ���Win-Win�헪���邢�͋��n�^�헪��[���Â��ō̗p����̂ł���A�s���͂͂邩�ɏ��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�Ō�́A�C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW���f����Ƃ����_�́A�ӊO�Ɏv���邩������Ȃ����A���n�^���[�_�[�V�b�v�ɂƂ��ďd�v�ȃ|�C���g�ł���Ǝv����B
�C�m�x�[�e�B�u�łȂ��ڕW���f����Ƃ������Ƃ́A�����O��Ƃ��đQ�i�I�ȖڕW���f����Ƃ������Ƃł���B�����I�ł���A�Z�a�I�ł��邱�Ƃ���A���n�I�Ɏv���邩������Ȃ����A���͑S�����n�I�ł͂Ȃ��B�����̏�Ԃ����^�̂��̂Ƃ��ď��������ǂ��Ă����A�Ƃ����l�����́A���͐��ɎO���`���̂��̂Ȃ̂ł���B
�C�m�x�[�e�B�u�łȂ��ڕW���f����ꍇ�́A�̗p������̓I�Ȑ헪�����܂ł̌o���܂������̂ɂȂ�B���̏ꍇ�A�V���Ȕ��z���́A���܂ł̌o�������d������邱�ƂɂȂ�B���߂���l�ނ����R�o���d���ƂȂ�A�V���Ȕ��z�����܂��]�n�͈�w���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�z���_�ł́A����Ԏ�̊J���ӔC�҂𑱂��ĒS�������邱�Ƃ͂Ȃ������ł���B����Ԏ�𑱂��ĒS�������ꍇ�A�O�삪���������ꍇ�͂ǂ����Ă����̉��ǔł���肽���Ȃ�A�V���Ȓ�������Ȃ��Ȃ�B�z���_�͓���Ԏ��S�����������邱�Ƃɂ��n�����A�V���ȃ`�������W�����߂����ƂɂȂ�B
�C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW�Ƃ́A�g�D�ɂƂ��Ďu�̍����ڕW���f����Ƃ������Ƃł���B�u�̒Ⴂ�A�����̌o�c�w�W�����P���悤�ȂǂƂ����ڕW�ł́A�g�D�̉i���I�Ȕ��W�͖]�߂Ȃ��B�������āA�Z���I�Ȑ����̂��܍��킹�̂��߂ɃR���v���C�A���X������ȂǂƂ������Ƃ��N����̂ł���B
�R���v���C�A���X�����̂��߂Ɏ�����͗��悵�čs�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����v�������Z���̌����}�j���A���ɂ��������B���n�^���[�_�[�ɂ́A�C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW��ݒ肵�A���̖ڕW��g�D�̃����o�[�ɓ��X�Ɣ��\���A���̖ڕW�B���ɕK�v�ȍs���𗦐悵�Ď���Ă������Ƃ����߂��Ă���̂ł���B
�Ƃ���ŁA�ɂ߂��̋�����`�҂ł���A���㗬�o�c�҂ł���S�[����E�F���`�ɂ́A���n�I���z�͑S���Ȃ��̂ł��낤���B
6.2�J�����X�E�S�[���ƃN���X�E�t�@���N�V���i���E�`�[��
�S�[���ɂ����ċ��n�I���z�A��������Win-Win�I���z�́A�N���X�E�t�@���N�V���i���E�`�[���i�ȉ�CFT�Ɨ����j�̐ݒu�ɕ\��Ă���B
CFT���̂̓~�V����������ɂ��łɃS�[���ɂ���Ĕ��z�A�̗p����Ă����BCFT�Ƃ́A���̖��̂Ƃ���A��������f�I�ɁA�E�����Ė��ɑΏ����悤�Ƃ����`�[���ł���B
�u���������ڋq�̗v���̓N���X�E�t�@���N�V���i���Ȃ��̂ł���B�R�X�g�ɂ���A�i���ɂ���A�[���ɂ���A�ЂƂ̋@�\��ЂƂ̕��傾���ł͉���������̂ł͂Ȃ��B�ǂ�ȉ�Ђł��A�ő�̔\�͕͂���ƕ���̑��ݍ�p�̒��ɔ�߂��Ă���v�i�J�����X�E�S�[���w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����xp172�j�B�ނ͓��Y���o�C�o���v�������쐬����̂ɁA�O���̒����ȃR���T���^���g��ЂȂǂɂ͑S�����炸�A�Г���CFT���쐬���ăv�������쐬�����Ă���B
�S�[�������Y�ɒ��C���Ă܂����v�Ɏ�������̂��A���R�X�g�̐��̐����ł���B���Y�ł́A�w���R�X�g�����҂Ɣ�ׂč����ɂ�������炸�A�S���������Ȃ���Ă��Ȃ������B�w������͊J���G���W�j�A�Ȃǂɔ�ׂ�ƎГ��I�Ȓn�ʂ��Ⴍ�A�����͂��Ȃ���������ł���B�������A�w���R�X�g�����R�X�g�ɐ�߂銄����60���ɒB���Ă���A�R�X�g�팸�ɂ͍w���R�X�g������������ɕK�v�������̂ł���B���̂��߁A�w���S���҂̃X�e�[�^�X���グ�A�G���W�j�A�ɂ̓N���X�E�t�@���N�V���i���ȗ��ꂩ�狦�͂��邱�Ƃ����߂Ă���B
�܂��A�g�D�̂�����ɂ�CFT���A�}�g���b�N�X�g�D���f�����̗p���Ă���B���Y�����Ƃ��s���Ă���n����c���Ƃ��āA�̔��E���i���E�w���E�o���Ƃ������E�����e�������Ƃ����}�g���b�N�X�ɉ����Đ��E�̓��Y���ĕҐ��������̂ł���B2�̎�������Ƃ������Ƃ́A�}�g���b�N�X�̌�_�Ɉʒu����l�ԂɂƂ��ẮA2�̕��C���������ƂɂȂ�B�u�Ј���2�̐ӔC���i2�l�̏�i�����j���ƂɂȂ�B1�l�̎Ј��́A�����̑�����n��Ŏ��v���グ�邱�ƂƁA�����̑�����E�����O���[�o���Ɍ����������v�������߂邱�Ƃ́A2�̐ӔC�����B���̂悤�ȑg�D�ł͂���߂č����������Ɛ₦�ԂȂ��R�~���j�P�[�V�������K�v�ɂȂ�v�i�J�����X�E�S�[���@���Op230�j�B2�̎��̌�_�Ɉʒu����Ј��̂Ƃ���ʼn�����肪�������ꍇ�́A�n�掲�ƐE�����ɉ����Ė�肪�㕔�ɓ`�����Ă����B��������A���͂���ނ�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��A�N���X�E�t�@���N�V���i���Ȋϓ_����������}���邱�ƂɂȂ�B
�S�[���́A�R�X�g�팸�ɍۂ��āA�����̉�������Ђɂ����͂�v�����Ă���B�����ɂ��A�N���X�E�t�@���N�V���i���ȊW�i���݂��ɗ��v�ɂȂ������}���Ă���Win-Win���_�j����������Ă���ł��낤���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
6.3�W���b�N�E�E�F���`�Ƌ��E�̂Ȃ��g�D
���育��̎O���`�҂ł���悤�Ɏv����E�F���`�ł��邪�i�ނ̒����ǂ�ł���ƁA�ނ̋�����99���͑ΑO�N��ł̉�Ђ̋Ɛь���ɂ���悤�Ɏv����B�c��1���̓S���t���H�j�A�Ɛь���̂��߂ɔނ��̗p���Ă���{��̒��ɂ́A���m�ɋ��n�I���z��Win-Win�I���z�f���Ă�����̂��������邱�ƂɋC���t���B
�uGE�̉��l�ρv�Ƃ����W��̒��ɁA�u���E�̂Ȃ��p���ōs�����饥�������̏o���ɂƂ���邱�ƂȂ��˂ɍō��̃A�C�f�A��ǂ����߂�������s�Ɉڂ��v�Ƃ������̂�����B�����D�ꂽ�A�C�f�A���������ꍇ�ɁA����������̏������镔���œƐ肷��̂ł͂Ȃ��A�L��GE�Ƃ��ċ��L���A�S�̂̋Ɛт�L���Ă������Ƃ������̂ł���B���̂��߂ɂ́A���E�̂Ȃ��g�D�iBoundary-Less Organization�j���K�v�ɂȂ�̂ł���B�܂��A���E�̂Ȃ��g�D���������邽�߂ɁA��V�V�X�e���̈�Ƃ��ăX�g�b�N��I�v�V���������Ă���B�X�g�b�N��I�v�V�����ɂ́A�����̕���̋Ɛт��ǂ���Ή�БS�̂̋Ɛт��ǂ��ł���{�[�i�X��������Ƃ����V�X�e���Ƃ͈قȂ�A��БS�̂̋Ɛт���V�ɔ��f�����Ƃ������ʂ����҂ł���B�܂��A�����ł���A�����̃A�C�f�A�𑼐l�Ɋ��p������Ƃ������z�ɂ��Ȃ���i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��pp287-315�j�B��Ђ̒��ɂ����鋤�n�I���z�ł���B
�܂��A�ނ̓V�b�N�X�V�O�}��ʂ����ڋq�d����`��ϋɓI�ɑł��o���Ă���B�V�b�N�X�V�O�}�͒P�Ȃ�i���Ǘ��p�V�X�e���̂悤�Ɍ������Ă��邪�A�����Ă����ł͂Ȃ��Ƃ����B
�V�b�N�X�V�O�}�̓��������A���i�̕i���͊m���Ɍ��サ�Ă���ɂ�������炸�A�ڋq����̔������F�������̂ł͂Ȃ������Ƃ����B���̂��Ƃ��A�E�F���`�͔[���̗�������Đ������Ă���B�V�b�N�X�V�O�}�̓����ɂ�鐶�Y�i������ɂ��A���i�̕��ϔ[����16������8���ɒZ�k���ꂽ�Ƃ���B����ŁA50���̕i�����オ�}�ꂽ�ƍl���Ă����̂����A�ڋq�͂��̂悤�ɂ͎���Ă͂��Ȃ������B�Ȃ����Ƃ����ƁA�[���ɂ��������������ł���B���ϔ[���ɁA�Ⴆ�ΑO��5���Ԃ̂�����������ꍇ�A���ϔ[���������ɂȂ����Ƃ��Ă��A�ڋq�ɂ͂������郁���b�g���Ȃ��B�����[���������̂ł���A�[����������Œ�������悢����ł���B���Ȃ̂́A�[�����s�m���Ȃ��ƂȂ̂ł���B
�V�b�N�X�V�O�}�́A�P�Ȃ�i���Ǘ��V�X�e���ł͂Ȃ��B����́A�ڋq�̃j�[�Y���m���ɏ���������Ŋ��p�����A����ɑ傫�Ȑ��ʂ����҂ł���̂ł���B
�V�b�N�X�V�O�}�����ɂ܂��ȉ��̃G�s�\�[�h���悭�\���Ă���B1998�N�Ɏs�ꓱ�����ꂽ�V�b�N�X�V�O�}�E�f�U�C���ɂ��CT�X�L���i�[�́A�����X�L�����ɂ����������Ԃ��]���^��3���Ԃ���17�b�ɒZ�k�����Ƃ����B�Ƃ��낪�A������ː��Ȃ̈�t����E�F���`���������莆�ɂ��A���̈�t�������Ƃ��������̂̓X�L�����̎��ԒZ�k�ł͂Ȃ�100���h��������@�B��������قǂ��ēd���v���O���R���Z���g�ɍ����������ł����ɓ��������Ƃ����������ł���i�W���b�N�E�E�F���`�@�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��p177�j�B�V�b�N�X�V�O�}�̊ϓ_������ڋq�d����GE�̏d�v�ȃ|���V�[�ɂȂ��Ă���̂ł��邪�A��������n�I���z�AWin-Win�I���z�ł���ƌ����邾�낤�B
7.���_
���݂̎Љ�́A�l���\���̕ω��Ƃ����Љ�w�I�ȕω��ƁA��ɂ��]���̃q�G�����q�[�̕ω��i����j�Ƃ����Ȋw�Z�p�I�ω������܂��āA�s���~�b�h�^�g�D��O��Ƃ������̂���l�b�g���[�N�^�g�D��O��Ƃ������̂ɕω�������B
�g�D���ω�����A���R���[�_�[�ɗv������闝�O���ς���Ă����B�]���́A���[�_�[�͓ƒf��s�ł������ꂽ��������Ȃ����A���ꂩ��̎Љ�ɂ����ċ��߂���̂́A���n�^���[�_�[�V�b�v�ł���B
���n�Ƃ́AWin-Win�헪�Ɋ�Â������I�헪�ȂǁA�g�D�̓��O���킸�������邱�Ƃ�ʂ��āA�g�D�ɂ�����C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW���������Ă������Ƃł���B
�]���́A�Ƃ�����ΐl�Ɛl�Ƃ����킹�邱�Ƃɂ���đg�D���h�����A�V���Ȕ��W��ڎw�������̂ł���B�������A���ꂩ��́A�C�m�x�[�e�B�u�ȖڕW��ݒ肷�邱�Ƃɂ��g�D���A�l���h�����A���W��ڎw���̂ł���B�O���`�ɑ�\����鐔���̒��덇�킹�ł́AWin-Win�헪�̂悤�Ȕ��f���v�������헪�͎�蓾�Ȃ��B
���[�_�[�V�b�v�̂���������n�I�Ȃ��̂ɂ��ď��߂ăl�b�g���[�N�Љ�ɗv�������Win-Win�헪�������ł���̂ł���B
�l�b�g���[�N�������Љ�ɂ����ẮA�R���v���C�A���X�ᔽ�̉e���͐[�����L�͈͂ɍL������̂ƂȂ�B�R���v���C�A���X�ᔽ����Ɠ��̔��������݂̂ʼn��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���n�I�Ȕ��z�����邱�Ƃɂ���āA�����I�Ȕ��z�̂��Ƃł͋@�\���ɂ��������R���v���C�A���X�������Ȃ����{���邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł���B
�����āA���̍ۗv������郊�[�_�[�V�b�v�Ƃ́A�������狤�n�I�Ȃ��̂ɂȂ�̂ł���B
����1
�u���{�����ی����݉�Ђɂ��ẮA�ی��_�Ɋւ��鎖���ł����ĕی��_��ғ��̔��f�ɉe�����y�ڂ����ƂƂȂ�d�v�Ȃ��̂ɂ��āA��������邨����̂��鎑�����쐬���A�ی��_��ғ��ɔz�t�E���Ă������Ƃ��m�F���ꂽ�B���̍s�ׂ́A�ی��Ɩ@��R�O�O���P����X���Ɋ�Â��ی��Ɩ@�{�s�K����Q�R�S���S���ɒ�G����B���̂��߁A�{���A���Ђɑ��A�ی��Ɩ@��P�R�Q���P���̋K��Ɋ�Â��A�ȉ��̓��e�̍s�������i�Ɩ����P���߁j���s�����B�v�i�u���{�����ی����݉�Ђɑ���s�������ɂ��āv����13�N11��1�����Z�� http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/hoken/f-200111101-2.html (2001/12/19)�j
����2�����ƏW�c�H���Ŏ���
�u�����ƐH���Ŏ���
�@��ꖜ�ܐ�l����Q��i���A���ő�K�͂ƂȂ��������Ƃ̏W�c�H���Ŏ����B���i����̒x���x�d�Ȃ�Ή��̕s��ۂŐM�p�����������Ђ́u�ڋq����`�v���f���čďo�������B�������A�������甼�N�߂�������������Q�҂Ƃ̕⏞���͑����A����グ�����������܂܂ŁA�M���ւ̓��͌������B
�@���H���ł̌���
�@�u�ٔ����Ă����Ă܂����v�B���{���̏���(30)�́A��������k���������ނƌ��S���̎Ј��ɂ�������ꂽ�Ƃ����B�u����������Q�҂Ȃ̂ɁA�܂�ň��҈������ꂽ�v�B�����A�Ԏӗ��Ȃǖ�l�\���~�̎x���������ߑ��ȍقɒ����\�����Ă��B�@�@�@�@�@�@�@
�@�����͘Z�����{�A�X�[�p�[�Ŕ��������ᎉ�b�������݁A������������f���C�ɏP���l���ԓ��@�����B�g���ǁh�ō��������ނ͈��߂Ȃ��Ƃ����B
�@���͎�����A��S�l�Ԑ��́u���q���܃P�A�Z���^�[�v��ݒu�A�⏞���ɓ��������B�L�́u�ܐ猏���������͖�S�����c�������ɂȂ����v�Ɣ�Q�ґΉ��̏���������������B
�@�������A���̌��ԓx�ɑ���s���̐��͑����B�����̔�Q�҂���b�����c�����ٌ�m�́u���ꂵ���⏞����Ȃ��A���Ô�ȊO�͔�Q�҂̏o���ɂ���ĕς��Ă���v�Ɣᔻ�B�u�ꓖ����I�ȑΉ��ŁA�������������̎p���ƕς��Ȃ��v�Ǝ茵�����B
�@�u�Љ�Ƃ��ꂪ�������v�i���h���V�В��j�Ƃ̔��Ȃ���A�O���̗L���҂�����邽�߂ɐ݂����u�o�c����ψ���v���A�����ɐg���Ƃ�������ږ�ٌ�m�𐘂����B���������Z���^�[�̓���N���k�����́u���͂Ȃɂ���Ԃ̖�肾�������A�܂��������Ă��Ȃ��悤���v�Ƃ������B
�@���g�b�v����]��
�@�o�c�ʂł����̑O�r�͑���B�����̉e���Ŕ���グ�������B�㌎���Ԍ��Z�ł͓�S�l�\�O���~�̌o�푹�����o���A�ƊE�g�b�v�̍������Ƃɖ����n�����B
�@��i�͂قƂ�ǂ̃X�[�p�[�̓X���ɖ߂������A����҂͖߂�Ȃ��B�\�ꌎ�̋����Ȃǂ̔���グ���O�N������l�����̌��ʂ��ŁA���S�����y�������㏞�͂��܂�ɂ��傫���B
�@�����ƐH���Ŏ����@�����Ƒ��H�ꂪ���������ᎉ�b���Ȃǂ�����ꖜ�ܐ�l��������f���C�Ȃǂ�i���A���ݎc�����物�F�u�h�E���ۂ̓őf�����o���ꂽ�B���̌�A�����ɂȂ����k�C���E����H�ꐻ�̒E�������̉����������B���{�x�͓��Њ�������߂��Ɩ���ߎ��v���e�p�ŏ��ޑ���������j�B�i�����ʐM�j�v
�i���s�V��2000�N12��19�� http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2000dec/19/16.html �i09/11/2001�j�j
����3�O�H�����ԃ��R�[���B������
�u�u���R�[���B���v�S���劲��������
���O�H�����ԁA�S�ГI�ɉB���H��i8��28���z�M�j
�@�O�H�����ԍH�Ɓi�{�Г����s�`��j�̃N���[�����A���R�[���i����E�����C���j�B�������ŁA���ׂ��^�A�Ȃɓ͂��o���A����ɔ̔��X�Ɏw�����ĂЂ����ɏC������u���R�[���B���v�̕��j���A�i���ۏؕ��A�T�[�r�X�A�v�A�����̌v�S����̊������o�Ȃ�����c�Ō��܂��Ă������Ƃ��A�Q�W���A�x������ʑ{���ۂ�^�A�Ȃ̒��ׂŕ������B��c�Ō��肵�����j�Ɋ�Â��A�v�A��������Ȃǂ��u��ݏC���v�̎��{���j�𗧂ĂĂ����B
�@���ۂ́A�B���H�삪�N���[�����B���̒��S�ƂȂ����i���ۏؕ������łȂ��A�S�ГI�ȋK�͂ōs���Ă������Ƃ𗠕t����Ƃ݂āA����A��c�ɏo�Ȃ����������玖��悷��B
�@���ׂɂ��ƁA���Ђł̓��[�U�[����̃N���[�����́A�{�Ђ̕i���ۏؕ��ɏW�߂���B�������ň��S���ɂ������Ɣ��f���ꂽ���́A���������w�b�h�Ƃ��āA�̔��X�Ƃ̑����ƂȂ�T�[�r�X����A�v�A�����e����̎����A�ے��N���X����������u�N���[�����c�v�ŋc�_�B�����Ń��R�[���Ȃǂ̑Ή����K�v�Ƃ��ꂽ�Č��ɂ��ẮA�����N���X�ō\������u���R�[���E���P����v�Ɏ���A���j�����܂�B
�@�{���ΏۂƂȂ����P�X�X�W�N�ȍ~�A��p�ԁu�f�{�l�A�v���^�g���b�N�A��^�o�X�A���^�o�X�̂S���Ń��R�[���B�����s��ꂽ�B
�@���̂S���ɂ��ẮA��������N���[�����c���A�����c�Ɠ��������o�[�ɂ���c�ŁA���S���肪����Ɣ��f���ꂽ�B�������A��c�ł̓��R�[�������ɁA��݂ŏC�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B
�@��c�̌�����āA�v�A�������傪�A��ݏC���̂����Ȃǂ̑Ή���������B�T�[�r�X���傩��̔��X�ɉ����C���̎w�����œ`�B�����B�����ɂ́u�ɔ鈵���v�u��舵�����Ӂv�ȂǂƏ����ꂽ��A�O���ւ̏��R���h����|�̒��ӏ����������Ă���A�B���̓O�ꂪ�}��ꂽ�B�v
�i�����ʐM2000�N8��28���z�Mhttp://www.jiji.co.jp/edit/topics/data2000/200008/0827mitsubishi/0828n4.html �i09/11/2001�j�j
�Q�l����
Bank for International Settlement (1998), Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations, http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm (09/05/2001)
Carlos Ghosn (2001), Renaissance, �i���� ���q��i2001�j�w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����x�_�C�������h�Ёj
Dawn-Marie Driscoll, W.
Michael Hoffman (1998), Ethics and
corporate governance: Leadership from the top), Journal of Management,
volume 27, 1998, Administrative Staff Collage of India, http://www.asci.org.in/publications/ascijl/v27/V27_ethics.html
(12/19/2001)
�ؑ��@���i2001�j�w�V�������Z�č��Ɠ����č��x�o�ϖ@�ߌ�����
���Z���u�،���ЂɌW�錟���}�j���A���vhttp://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf�@�i08/30/2001�j
���Z���u�ی���ЂɌW�錟���}�j���A���vhttp://www.fsa.go.jp/manual/manualj/hoken.pdf�@�i08/30/2001�j
���Z���u�a����������Z�@�ւɌW�錟���}�j���A���vhttp://www.fsa.go.jp/manual/manualj/yokin.pdf�@�i08/30/2001�j
���Z���u�،���ЂɌW�錟���}�j���A���ɂ��āv������170��http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/shouken.pdf �i08/30/2001�j
�����@���i1974�j�w�w�����@��E���x��������|�t�H
�����@���i1986�j�w�f��̃��[�_�[�x������Е��|�t�H
�����@���i1990�j�w��Z�̘_���x������Е��|�t�H
�O�����@�v��i1988�j�w���R�Q�d�@�G���[�g����̌����x������Е��|�t�H
���n�ّ�10����������12�N9��20������ �{�������@��1573�� �i�Ёj�����@��������
�䉮
����i1993�j�w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��x
PHP������
�����@���c�i1991�j�w�����p�@�u�킪���O�v�x������Ќ�����
�Y�o�V����ޔ�
�i2001�j�w�u�����h�͂Ȃ��Ă������\���A�������A�O�H������
�����̐[�w�x�p�쏑�X
��@����i�ďC�j�O���[�r�X�E�}�l�W�����g�E�C���X�e�B�e���[�g�i�ҁj�wMBA�Q�[�����_�x�_�C�������h��
Jack Welch, John A. Byrne
(2001), Jack Straight from the Gut,
John F. Warner Books, �i�{�{ ����i2001�j�w�W���b�N�E�E�F���`
�킪�o�c�x���{�o�ϐV���Ёj
���c �M�j�i1998�j�w���̍��̎��s�̖{���x�u�k��