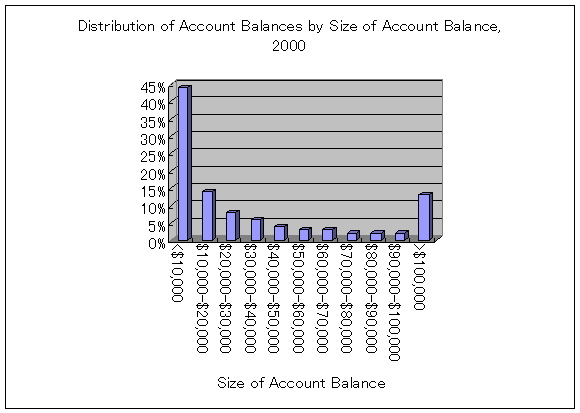 Source: Tabulations from EBRI/ICI Participant-Directed Retirement Plan Data
Collection Project.
Source: Tabulations from EBRI/ICI Participant-Directed Retirement Plan Data
Collection Project.�q���[�}���E���\�[�X�iHRE705�j4�N���W�b�g
�Ɛѕ]���ƕ�V�\�\�����I�w�W����
Rushmore University
Global Distance Learning DBA
�嚠 ��
���̃R�[�X���[�N���o����ɂ������āA�����ɋL�q����Ă��镶��/�A�C�f�A�́A���p�̕\�L���Ȃ�����A���̍�i�ł���܂��B�܂��A�������̃R�[�X�̌������肪����܂ł́A���̃R�[�X���[�N�͑��݂��Ȃ��������Ƃ��m�F���܂��B
�c����Ƃɂ�����]�ƈ��̋Ɛѕ]���́A���炩�Ɏ��ѕ]�����d�������悤�ɂȂ�A�]���̔N���I�F�ʂ͎キ�Ȃ����B�Ƃ��낪�A���ю�`�̈�ʉ��Ƌ��ɁA���̃}�C�i�X�ʂ��N���[�Y�A�b�v����邱�ƂɂȂ��Ă����B
���ю�`���d�������悤�ɂȂ����̂́A�]���̂悤�ɐ��i����肳������Δ���Ă�������Ƃ͈قȂ�A�����鏤�i����ɂ����Ďs�ꂪ���n���Ă������ƂɌ���������B�ŋ߂ł́A�ǂ̎Y�ƕ���ɂ����Ă��ڋq�d�����������A�܂��R���v���C�A���X���d�v�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��邪�A���͑o�����ɁA�s��̐��n�������̌����Ƃ��Ă���B�Љ���n�����Ă���̂ł���B
�����Ŗ{�e�ł́A���ю�`���d�������悤�ɂȂ��Ă����w�i�ƁA�����ɂ����ėv�������l�ނ𖾂炩�ɂ���B���ɁA�]�������ł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ɏ]�ƈ��ɑ��ĕĂ����������s�̕�V�V�X�e���̃����b�g�E�f�����b�g��ʂ��Č������Ă����B
�ŏI�I�ɂ́A���n�Љ�ɂ����āA������I�ȕ�V���x���m�����Ă����K�v���𗝘_�t���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���B
�ڎ�
1.�͂��߂�
2.�o�c���Ƌ��߂���l�ޑ�
2.1�K���s��
2.2�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[
2.3���n�s��ɂ�����ڋq���C�����e�B�[
3.�ƐъǗ��̕��@
3.1�J���X�}�^
3.2�}�j���A���Ǘ�
3.3�ڕW�ɂ��Ǘ�
3.4�ƐтƂ͉���
4.��V�̕���
4.1�X�g�b�N�E�I�v�V����
4.2�ސE���E�ސE�N��
4.3�@401�ik�j
5.�����I��V�̌n����̒E�p
5.1�J�t�F�e���A�v����
5.2���[�N�V�F�A�����O
6.������I�ȕ�V�Ƃ�
6.1��V�Ƃ��ẴJ�t�F�e���A�v����
6.2��V�Ƃ��Ẵ��[�N�V�F�A�����O
7.���_
�Q�l����
1.�͂��߂�
�c����Ƃɂ�����]�ƈ��̋Ɛѕ]���́A���炩�Ɏ��ѕ]�����d�������悤�ɂȂ�A�]���̔N���I�F�ʂ͎キ�Ȃ����B�Ƃ��낪�A���ю�`�̈�ʉ��Ƌ��ɁA���̃}�C�i�X�ʂ��N���[�Y�A�b�v����邱�ƂɂȂ��Ă����B
���ю�`�ł͂ǂ̂悤�Ȏ��т��グ�������]���̑ΏۂƂȂ�B����ڕW�𗧂ĂĂ��܂��ƁA�B���ł��Ȃ����ꂪ���邽�ߊȒP�ȖڕW�������ĂȂ��悤�ɂȂ��Ă��܂����肵�Ă���B�܂��A�]�����q�ϓI�ɉ������i�]��������Ƃ��Ă��]�����₷���j�����I�ڕW���d������邽�߁A�Ƃɂ������ʂ��o�����Ƃ����ɒ��͂��A���̂��ƌڋq���ǂ��Ȃ낤�ƒm�������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������悤�ȒZ���I����Ɋ�Â��c�Ǝp�����͂т��邱�Ƃɂ��Ȃ����B
����ł͂����Ȃ��Ɖc�Ɗ����̎��I���ʂ�]���̍ۂɏd������ƁA�c�Ɛ��т��}�ቺ�A���x�͌o�c�T�C�h���Q�ĂĎ��I�]���d���̕��j��P��Ȃǖ������ڗ��B
���ю�`�͖��炩�Ɍo�c���̕ω��ɔ����ėv�������悤�ɂȂ������̂ł���A�������Ƃ��Ă͊Ԉ���Ă͂��Ȃ��Ǝv����B
����ł́A�����I�ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ��ю�`�Ɋ�Â����]�������A�]�ƈ��ɕĂ����ׂ��Ȃ̂ł��낤���B
2.�o�c���Ƌ��߂���l�ޑ�
��ƂɂƂ��āA�ǂ̂悤�Ȑl�ނ����߂��Ă��邩�́A���̊�Ƃ�������Ă���o�c���ɂ���āA�傫���قȂ邱�Ƃ��e�Ղɗ\�z�����B��Ƃ͌o�c���ɍ��v�����헪�����̂ł���A���̊�Ƃ�������헪�����̂܂ܓ��Ă͂߂Ă��A���܂������킯�ł͂Ȃ��B
�Ⴆ�A���K���ɘa���i�߂��Ă���Ƃ͂���������̒n��Ɛ�������Ă���d�́E�K�X���ƂȂǂƁA���E���œ����悤�Ȑ��i����萢�E���̎s��ŋ������Ă��鎩���ԋƊE�ł́A���߂���l�ނ����R�̂��ƂȂ���قȂ��Ă��邱�Ƃ��\�z�����B�܂��A���J��s�ꂪ�O�r�ɗm�X�ƍL�����Ă����ƂƁA���n�����s��ł̌���ȋ����ɂ��炳��Ă����ƂƂł��قȂ�͂��ł���B
��Ƃ̂�����Ă���o�c���Ƌ��߂���l�ނ��A�ȉ����͂���B
2.1�K���s��
���Z�s����A�ق��10�N�قǑO�܂ł́A�呠�Ȃ����͂Ƃ��鋭�͂ȋK���Ɏ��ꂽ�쑗�D�c�����̉��Ŕɉh��搉̂��Ă����B
�쑗�D�c�����̉��ł́A�ƊE���[����j��s�ׂ̓^�u�[�i�������͂Ƃ�ł��Ȃ������点����j�ł��������߁A�݂��o���A�a���A�萔���A�ی������Ȃǂ�����}�[�W�����͌Œ�I�ł���A�ϓ������邱�Ƃ͋�����Ȃ������B
�}�[�W�������Œ�I�ł��邽�߁A��Ƃ̗����𑝂₷���߂ɂ͔��グ�傳���邱�Ƃ��B��Ƃ�������@�ł������B
���Z�ƊE�݂̂Ȃ炸�A���{�̊e�ƊE�ɂ͋ƊE�V�F�A���ُ�ɋC�ɂ���C�����c���Ă��邪�A����͓��{�̊e�ƊE�������𒆐S�Ƃ���쑗�D�c������������ƊE�ō̗p���Ă������̖��c�ł��낤�B
���̂悤�ȋƊE�ł́A���グ�傳���邱�Ƃ�����ړI�ƂȂ�A�m���}��^���ĂƂɂ����B��������Ƃ��������@�������B
�܂��A�K���ƊE�ɂ����ẮA���i�̍��ʉ����}��ɂ����B�����O�܂ł̓��{�̋��Z�ƊE�ł́A��s�A�،��A�ی��e�ƊE���ł͔̔����Ă��鏤�i�͂قƂ�Ǔ����ł���A�Ⴂ�͕t���Ă��邨�܂����炢�����Ȃ������B�܂��戵�����i�����i�����ł͂Ȃ��\�N����ł���A�戵���i�̕������������B�]���āA���Z�Ɋւ��鍂�x�ő����I�Ȓm�������߂��Ă���킯�ł͂Ȃ������B
���i�Ɋ�{�I�ȍ����Ȃ��̂ł��邩��A��ƋƐт͒P���ɔ̔��͂̍��Ō��肳���B�����ŁA�c�ƃ}���B�͍I�݂ȃZ�[���X�g�[�N�Ƌ����Ȕ̔����@�Ŕ��荞�݂�}��B�铢�����삯�ȂǓ��풃�ю��ł���B�����،��́����R�c�ȂǂƝ��������c�ƕ����������̂́A���̂悤�Ȍo�c���̉��ɂ����Ăł���B�،���Ђ̊e�x�X�ɏ�������c�ƐE�����l�X�X�̐��������邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�S�Ј�ۂƂȂ��ē���̖�����܂���̂ł���B
�����ی���Ђ̉c�Ƃɂ����Ă��A�����̂������ȂǂƌĂ��c�ƐE�����ʓ������āA�F�l�m�l�e�ʂȂǂ�Ђ��[���琶���ی��ɉ��������Ă������B���ꂪ�\�ł������̂́A�����ی��̉��������Ⴂ�����n�s�ꂪ���肾��������ł���B�����ی�������91.8���̐��n�s���ɂ����ꍇ�ɂ͎�蓾�Ȃ��헪�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���Ǝv���邪�������ł��낤���B
���̂悤�ȏꍇ�ɕK�v�Ƃ����l�ނ́A����ɂ��߂����A�^����ꂽ�m���}�����Ȃ��Ă����l�ނł���B�{�В����Ő헪���l�����ƂɂƂ��ăR�A�ƂȂ�l�ނ����߂��邪�A���̂悤�Ȑl�ނ��������߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�P���Ȏd�������Ȃ��Ă����l�ނ����߂��A�l�ވ琬�̕��������R���̂悤�ɍs��ꂽ�B
�P���Ȏd�������Ȃ��Ă����Ƃ����Ӗ��ł́A�����Ƃɂ����郉�C���J���҂�A�R���r�j�G���X�E�X�g�A�̓X���Ȃǂ��A�����悤�Ȕ��e�ɕ��ނł���B
�����ɋ��ʂ���̂́A�d���̃}�j���A�����ƁhHire and Fire�h�i�ق��Ă̓N�r�ɂ���j��O��Ƃ����l������ł���B
�d�����}�j���A����������Ƃ������Ƃ́A���̎d�������m�ɒ�`����Ă���Ƃ������Ƃł���B���S�ɒ�`����Ă���ȏ�A�����œ����l�Ԃɑn�����͗v������Ȃ��B�v������Ă���̂́A�����Ƀ}�j���A�������Ȃ����Ƃł���B�܂��A�d�����̂��}�j���A���ɒ�`����Ă���̂ŁA���̎d�������Ȃ������ł���Α��͊��ł�������B�����ŁA�ق��Ă̓N�r�ɂ���悤�Ȑl��������邱�Ƃ�����B
�d���̃}�j���A�������hHire and Fire�h������A���{�����č��ł����������W�����B�č��ɂ����ẮAJob Description�ƌĂ��ɂ߂ďڍׂȐE�����e���L�ڂ������ʂ��쐬�����B�č��ł͓`���I�ɔN���I�Ȑl���͍s���Ă��Ȃ������Ƃ����邪�A�t�Ƀ��C�I�t�Ȃǂ͋Ζ��N���̎Ⴂ�҂���s����̂����ʂł������B
�����ŁA�č��̉�Ђɋ߂�l�Ԃ́A�����̐E���𒉎��ɂ��Ȃ����Ƃ��d�������BJob Description���͂ݏo���悤�ȍs���͂Ƃ�Ȃ��Ȃ�B���̌��ʁA���ƂȂǂł́A����|�X�g�ɒ��N�����l�Ԃ������邱�ƂɂȂ�A�g�D�̍d�����������B
�W���b�N�E�E�F���`��GE�ɂ����Ă܂��Ŕj���悤�Ƃ��������I�̎��́A���̂悤�ɂ��Đ��ݏo���ꂽ�̂ł���B
���̂悤�Ȋ����I�̎������ݏo���ꂽ�w�i�ɂ́A19���I���ȗ��̓Ɛ莑�{��`�ȂǂƌĂ�鎞��ɁA���{�Ƃ̓s�����hHire and Fire�h������s���Ă������ʂƂ��āA1930�N��ȗ��J���҂͖@����Ƃ��������̊l���ɏ��o���Ă������o�܂�����B���̂悤�Ȍ�����1940�N��Ɋm�����Ă������B�������A���j�����ȖڂŒ��߂�A��2�����E���Ƃ��̌�̃p�N�X�E�A�����J�[�i�ƌĂ��č��ЂƂ菟���̎����ʂ��āA�����I�Ȍo�ϊg�傪���������߁A���̖�肪�N���[�Y�A�b�v����邱�ƂȂ��߂��Ă������̂ł���B
���̌�1970�N��ɓ����āA���{��h�C�c����̌o�ϓI���Ђ������Ă���ɏ]���A����܂ŕێ����Ă������{�E�Z�p���ʂɂ����鈳�|�I�D�ʂ�ۂ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B�u���̓����A��@���������Ă���҂͎Г��ɂ����Ȃ������GE�̓A�����J�̏ے��ł���A��ƋK�͂ł������������z�ł���10�ʂ̊�Ƃ�������Ƃ��낪���N�ɂ킽���ăA�W�A����̍U�������܂�A���W�I��J�����A�e���r�A�S�|�A�D���A���ɂ͎����Ԃ܂ŁA�A�����J�̎Y�Ƃ����X�ƈ��|����Ă������GE�ł��A�e���r�����Ƃ������Ɋׂ�A���{���͂��߂Ƃ��鐢�E�Ƃ̋����ɂ��炳��A���v���H����悤�ɂȂ����v�i�W���b�N�E�E�F���`�w�킪�o�c�xpp174�\175�j�B
���̌��ʕč���Ƃɂ����āA��K�͂ȃ��X�g�����s���邱�ƂɂȂ����̂ł���B���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�W���b�N�E�E�F���`��GE�ōs�������v���č��ɂ�����S�ʓI�ȏƎ��ɂ悭�}�b�`���Ă��邱�Ƃ������ł���ł��낤�B
�t�ɁA���{�ɂ����Ă͔N���I�A���邢�͉Ƒ��I�o�c���s���Ă������߁A��_�ȁhHire and Fire�h����͎���Ȃ������B���̔w�i�ɂ́A�S�̂Ƃ��Č���Α�2�����E���㒷���ɂ킽���đ������o�ϊg�傪�w�i�Ƃ��Ă��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���{�ɂ����Ă��A1970�N��ɓ���ƍ������z������������ɓ˓����A�č��Ɠ��l�Ȗ�肪���ݓI�ɂ͑��݂��Ă����B���ꂪ�]����Ƃ͂Ȃ�Ȃ������̂́A����ł��o�ϐ������������������ƁA����ё�2�����E���y�ѐ��̃p�[�W�̌��ʁA�������̔N��̘J���l�������Ȃ��A�ʏ�ł�������̐���ɔz�����ꂽ�ł��낤�|�X�g���������N�w�ɋ������ꂽ���ƂȂǂ̗v�����l������B
���̌���A�o�u���I���܂ł͂��̂悤�ȏ��������B�Ƃ��낪�o�u���i�C������ƁA����قǓ��{�ɍ��t���Ă����Ǝv��ꂽ�N���V�X�e�����������Ȃ������B���́A1980�N�㍠����N���V�X�e���ł͖�E�҂̃|�X�g���s�����邱�Ƃ������ɂȂ�A�l�X�Ȗ�E�����l���o����A�����̂��Ȃ��Ǘ��E���������ݏo�����ȂǔN���V�X�e���̌��E�������n�߂Ă����̂ł��邪�A��Ƃ͖�D��ɏI�n�A���{�I�ȉ����ɂ͏��o���Ȃ������B���̌��ʁA�o�u�������ɔN���V�X�e���̕����炩�ɂȂ�ƁA��Ƃ͏]���́u�Ƒ��I�v�o�c�����Ȃ���̂āA��]���ă��X�g���̖��̉��ɏ]�ƈ��̎�肪���s���邱�ƂɂȂ����B�ŋ߂́u�]�ƈ��������Ȃ�����Ɛт������v�Ɣ������ĕ��c�����������o�c�҂܂ŏo��n���ł������i�ꉞ�����͔ے肳��Ă���B����1�Q�Ɓj�B�������A���X�g���Ƃ������������Ƃ���Ŕ�p�̍팸�͈ꎞ�I�Ȃ��̂ł����Ȃ��A���̉��s�͏]�ƈ��̃�������ቺ�����A��Ƃ̒����I�Ȑ�����ۏႷ����̂ł��Ȃ��B
�������A���{�̊�Ƃ��S�����̑�����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B1990�N�����瑽���̋��Z�@�ւ��̗p�����̂��A�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ����헪�ł���
2.2�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[
��ʓI�ɁA�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�ƌĂ��̂́A�ڋq��������������A����������Ƃ����t�����l���ڋq�ɒ��邱�Ƃɂ�������Ē����Ƃ����헪�ł���B
�K���s��ɂ����Ă͑��Ђƍ��ʉ��������i���J�����邱�Ƃ͂ł����A���Z�@�ւ́i���邢�͋K�����ǂ́j�s���ŊJ�����ꂽ���i�邵���Ȃ������̂ł��邪�A�܂���̋K���ɘa�Ƃ����܂��āA�l�X�ȏ��i��ł���悤�ɂȂ�A���Z�@�ւ̎��R�x�͑����ɍ��܂����̂ł���B
���̌��ʁA�����̋��Z�@�ւŁA���Ă͒P�Ȃ�c�ƐE���ł��������̂��A�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[�A�t�@�C�i���V�����E�A�h�o�C�U�[�ȂǂȂǁA�l�X�Ȗ��̂ŌĂ��悤�ɂȂ����B�����]�ƈ��Ɋ��҂��ꂽ�̂́A�]���̂悤�Ɉꗥ�̏��i���������肷�邱�Ƃł͂Ȃ��A�ڋq�̗���ɗ����āA�ڋq�̖����������A����ɂ���ď��i������Ă����̔��헪�ł���B
�Ⴆ�ΐ����ی���Ђɂ����ẮA�]���ł���Ƃɂ������z�̕ی��ɉ��������悤�Ƃ������̂ł��邪�A�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ��Ă̗�������悤�ɂȂ�ƁA�ڋq�̃��C�t�E�T�C�N�������̗l�X�ȏ��Ɋ�Â����́A�ڋq�ɕK�v�Ƃ���鐶���ی����Ă��Ă����A��Č^�̉c�Ƃ��d�v�ɂȂ�B
���̂悤�ȉc�ƃX�^�C���ɂ́A��L�K���ƊE�Ŋ��Ă����悤�ȃ^�C�v�̐l�ނ����߂��Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��낤�B��Č^�̉c�Ƃ����Ȃ����߂ɂ́A�l�X�ȏ��i�m�����K�v�ɂȂ�B�ڋq�ɐ����ی���̔����悤�Ƃ��āA�������W�������ʁA�ڋq���œK�Ȑ����ی��ɉ������Ă��邱�Ƃ����蓾��B����ʓI�ɂ́A�����ی��ɓ���߂��Ă���P�[�X�������B���̂悤�ȏꍇ�ɂǂ����邩�����ł���B
�ȑO�ł���A�����ς�Ɗ��U�����𒆎~�A���̋q������n�߂邵���Ȃ������B����ɑ��āA�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ��ẮA���̒��x�ň����������Ă͂����Ȃ��B������ڋq�̋M�d�ȏ����o�����̂ł���B�����ŁA�ی����i�ȊO�̏��i�̔̔����l����B�ꍇ�ɂ���Ă͎ЊO�̏��i�����߂邱�Ƃ����蓾��ł��낤�B�܂��A�ی��ɓ���߂��Ă���̂ł���A�œK�ȕی��ɂ��ăA�h�o�C�X���邱�Ƃ����邩������Ȃ��B�ی��̔̔������ی��������̃A�h�o�C�X�����Ă��������킯�ɂ͂����Ȃ��ł��낤���A��X���l���ĉa�T�������Ă����̂ł���B
�܂��A�ꗬ�̃\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�́A�ڋq����˗����ꂽ���������ɂ��Č�����������̂ł͂Ȃ��A�ڋq���ǂ̂悤�Ȗ�������Ă��邩���ڋq�ɑ����Ĕ������A���̃\�����[�V���������Ƃ����B�܂��A���̏ꍇ�A�戵�����i�͎��А��i�Ɍ��肳��邱�Ƃ͂Ȃ��B���i��̔����鑤�ɗ����Čڋq�ɑΉ�����̂ł͂Ȃ��A�ڋq�̑��ɗ����ď��i���w�������`�������邩��ł���B�u���̂��߁AOA�@��̏��Ђł���A�S�����郁�[�J�[�ɑ����Đ��i��̔��㗝�X����A�ڋq�ɑ����Ċe���[�J�[���琻�i���Ă���w���㗝�X�ցAOA���[�J�[�ł���A���А��i�������Ĕ���Ƃ����v���_�N�g�A�E�g����A���А��i���܂߂��x�X�g�ȑg�ݍ��킹��}�[�P�b�g�C���ւƓ]�����i��ł���B���ɁA�x�m�ʂ�NEC�Ȃǂ�SI���ƕ��́A���А��i���戵���Ă����܂�Ȃ��Ƃ����������^������ɓ����Ă���v�i���� �r��w�l�ރ}�l�W�����g�_�xp29�j�����ł���B
���̂悤�Ȏ���͋��Z�ƊE�ɂ����Ă����W������B�ی��ƊE�ɂ����ẮA�����ی��Ƒ��Q�ی���Ɏ戵�������㗝�X�A����̐����ی���Ђ̐��i���戵���ی��u���[�J�[���������悤�ɂȂ����B�܂��A�̔��`�����l���Ƃ��āA�����̏،���ЁA�ŗ��m�Ȃǂ��o�R����������B�܂��A�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[�̃\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ��Ă̐��ݗ͂Ɋ��҂��āA�،��ƊE�����߂Ƃ��āA�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[��g�D����������B
�Ƃ���ŁA�����ی��ƊE�͂��Ȃ�ȑO����\�����[�V�����E�v���o�C�_�[��ڎw���Ă����͂��ł��邪�A���قǂ̌��ʂ��������Ȃ��B����͂Ȃ����낤���B
�܂��l������̂́A�c�ƐE���ƌĂ��̔��E���̗̍p�̐��ł���B�ڂ����ٍ͐e�ł��G��Ă���̂Łihttp://fpohkuni.com�j���������������A�ŐV�̃f�[�^�ł́A�S�c�ƐE���̂����A���ɂӂ���ɂЂƂ肪���߁A���̕��V�K�ɍ̗p����Ă���B
���m�ɂ́A����11�N���ݐЂ̉c�ƐE��326,974�l�ɑ��ĕ���12�N���ݐА���293,293�l�A�������A����12�N�x���Ɉ�ʉߒ������i����ɒʂ�Ȃ��Ɛ����ی��̔̔����ł��Ȃ��j�ɍ��i�ҍ��i�������̐���154,974�l����i�o�T �w����13�N�Ő����ی����v���x������Еی��������j�B��ʉߒ������́A��Ђ����߂���ւ�����肵�Ȃ���Έꐶ�L���ł���B��L�̐������Ӗ����Ă���Ƃ���́A����12�N�ݐЂ̉c�ƐE���̂����A���ɔ�������N�ȓ��Ɍ��ݏ����̐����ی���Ђɋߎn�߂��Ƃ������Ƃł����B�������A�����ی��̉c�ƐE���ł��g�b�v�N���X�ɂȂ�ƁA���ɐ����ی���Ђ̎В�����������Ă���Ƃ������B�]���āA�I�ʂ��������̂ł��邪�A����ɂ��Ă��ُ�ɍ������E���ł���B
�����đ��ɂ�������̂��A�c�ƐE���̋Ɛѕ]���̐��ł���B������ٍe�ł��G�ꂽ�Ƃ���A�����̐����ی���Ђ̋��^�̌n�ɂ����ẮA�̔����т����ƌ����Ă��傫�ȃE�F�C�g���߂Ă���B�ŋ߂ł́A�R���v���C�A���X�ɑ���p���Ȃǂ��]�����ڂƂ��đg�ݓ�����Ă��邪�A���̎������ɂ͋^�₪�c��B�c�ƌ���̏�i���R���v���C�A���X��̕]���������Ƃ������Ƃ́A�R���v���C�A���X�̈Ӗ���Ɨ�������l���čD�܂����Ȃ��B���ۂɂ́A�c�ƌ���ɂ���l�Ԃ��R���v���C�A���X�ɑ���p����]�����Ă���i�ق��ɕ]���̕��@���Ȃ��j�̂�����ł���B�R���v���C�A���X���ڂ��Ɛэl�ۂɑg�ݍ���ł���Ƃ����Ă��A���̏ꍇ�A���m�ɃR���v���C�A���X�ᔽ��Ƃ��Ă���̂łȂ�����A�Ⴂ�]���͉�����ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�c�ƌ���̒��ɂ́A�ʏ킻�̉c�ƌ���S�̂̋Ɛсi���̏ꍇ�͔��グ�j�ɉ����ăC���Z���e�B�u���x������ꍇ�������B�]���āA�M�S�ɃR���v���C�A���X�𐄐i������́A�c�Ɛ��i�ɏd�_��u���₷���B���̌��ʁA�R���v���C�A���X�Ɋւ���l�ۂ͑哯���قƂȂ��Ă��܂��B�����̐l�Ԃɑ��ē����悤�ȍl�ۂ������Ă���̂ł���A�l�ۂ��Ă��Ȃ��̂Ɠ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
�܂��A�c�ƐE�����g�͂ǂ��ł��낤���B�Ⴆ�A�O�q�̂悤�ɁA�ڋq���œK�Ȑ����ی��ɓ����Ă�����A����߂����肵�Ă����ꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ȉc�Ɗ������\�z����邾�낤���B
�����A�{���̃\�����[�V�����E�v���o�C�_�[��ڎw���̂ł���A������i�[���ڋq�̐l���v�������������A���_��o���A���̏��i�̔̔����l����A����߂��Ă����ꍇ�ɂ͓K�ȕی��v�ɂ��ăA�h�o�C�X����A�Ȃǂ��l������B�Ƃ���ŁA���ꂪ�]���E�l�ۂɔ��f�����̂ł��낤���B�O�q�̕x�m�ʂ�NEC�Ȃǂ�SI���ƕ��ł͑��А��i���戵���Ă����ꂪ�]������邱�Ƃ����m�Ɏ�����Ă����B�������A�����ی���Ђł��A���������Ă��鑹�Q�ی���Ђ̑��Q�ی���̔����邱�Ƃ͉\�ł���B�������A���Ƃ��Όڋq�ɃA�h�o�C�X���s���������ŁA����̔��グ�������Ă��Ȃ��ꍇ�̕]���͂ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B���炭�A�����]������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�����āA���̂悤�ȕ]������A���ɂ������������E���Ɍ���Ă���̂ł���B�����ی��ƊE�̏ꍇ�A�݂��Ƀ����N�������Ă���̗p�V�X�e���ƕ]���V�X�e���̍��{�I�ȉ��v���K�v�ł���Ǝv����B
�u�]��������ɂ��l�͍s������Ƃ����̂��A�܂��^���ł���B�o�c���O��o�c���j�ɂ��A�l���s������Ƃ����̂́A�����ʂ̌��ۂ��Ƃ炦�Ă���ɉ߂��Ȃ��B��Ƃɋ߂鑽���̐l�͕]��������߂Ɏd�������A�s�����Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����āA�g�D���̍s�����A�ŏI�I�Ɋ�ƕ������K�肵�Ă���̂ł���v�i���� ����w���ꂩ��̐l���]���Ɗ�xp1�j�B������Ƃ�����s���K�͂��������悤�Ǝv������A���̂悤�ȍs����]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����炨��ڂō����Ȃ��Ƃ������Ă��A�c�O�Ȃ�����H���Ă����l�Ԃ͂��Ȃ��̂ł���B
2.3���n�s��ɂ�����ڋq���C�����e�B�[
�ڋq�ɑ��ă\�����[�V��������邱�Ƃɂ���Ĕ̔����т��グ�邾���łȂ��A�l�X�ȕ��@��p���Čڋq���C�����e�B�[�����コ���邱�Ƃ����݂̂悤�Ȑ��n�s��ł͗v������Ă���B�����n�s��A���邢�͔��W�r��Ŋg�債����s��ɂ����ẮA���i�̉c�Ɠw�͂����Ȃ��Ă��A�ڋq�͌J�Ԃ�������Ƃ��珤�i���Ă���邱�Ƃ����҂ł����B
�������A���n�s��ɂ����ẮA�ڋq�͓����悤�ȃT�[�r�X�E���i����Ă���鑽���̊�Ƃ̒�����1�Ђ�I�Ԃɉ߂��Ȃ��B���ɐV�K�Ɋl�������ڋq�ɂ��ẮA����ȍ~��������Ƃ�I�����Ă����Ƃ͌���Ȃ��B�܂��A���ʉ����͂���Ȃ��s��ł́A�����͂ǂ����Ă����i�����ɂȂ��Ă��܂��B�ی��̂Ȃ����i�؉��������Ɋ����܂�Ă��܂������ł���B����ł́A����̘J�͂ƃR�X�g�������ĐV�K�J������Ă��Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA���łɎ���̂���ڋq���炢���Ɍp���I�Ɏ������荞�ސ헪���d�v�������悤�ɂȂ��Ă����B
���̑�\�I�ȗ�Ƃ��Ă�������̂��q���Ђ̍s���Ă���}�C���[�W�E�T�[�r�X�Ȃǂ̃t���[�N�G���g�E�t���C���[�Y�E�v���O�����i�J�Ԃ������q���Ђ𗘗p���Ă����ڋq�ɑ���D���v���O�����j�ł���B
�����Ƃɂ����Ă��A��ƓƎ��̃N���W�b�g�E�J�[�h�i�C���n�E�X�E�J�[�h�j�s���A�����グ�z�ɉ����Ċ����������グ�Ă����Ƃ������V�X�e������������Ă���B�P���ȃ|�C���g�E�J�[�h�Ȃǂ��A���l�Ȋ�Ɠw�͂̂�����ł���B
�������A�����̌ڋq�T�[�r�X�ɂ��A���_���w�E����Ă���B���������͑��ЂƂ̍��ʉ��ɂȂ�����������Ȃ����A�V�X�e���̎蓖�������A���Ђɂ����Ă��e�Ղɓ������邱�Ƃ��ł���B���ЂƂ̍��ʉ���}�邽�߂ɂ́A�ڋq�Ҍ��������߂邵���Ȃ��B�܂�A���Ђ̗��v���������邱�ƂɂȂ�B�č��ł́A�������������̍q���Ђ��ߓ����������Ă����Ƃ���Ƀ}�C���[�W�E�T�[�r�X���킪�N������v�������A�q���Ђ̌o�c���ꂵ�������B�����ɍ�N9��11���̃e�����N���������߁A�����̍q���Ђ��ꋫ�ɗ�������Ă���̂́A�����̐V���Ȃǂł����m�̒ʂ�ł���B
�ڋq�̃��C�����e�B�[���u���m�v���邢�́u�J�l�v�Œނ낤�Ƃ��邩�疳��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ǁA�ڋq�̃��C�����e�B�[�������邽�߂ɂ́A�ڋq�Ɛڂ�������œ����Ă���]�ƈ��ЂƂ�ЂƂ�̓w�͂Ɋ|���Ă���̂ł���B
�܂��A��Ƃ̑��ł��^�[�Q�b�g�ƂȂ�ڋq�̍i�荞�݂��s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���{�o�ϐV���A���}�g�^�A������q ���j�́u���̗������v�ɁA���n�s��̗�����������[����b���ڂ��Ă����B
�O�z�̓��}�g�^�A�ɂƂ��đn�ƈȗ��̏d�v�ڋq�ŁA���В��͎O�z�ɑ��������Ă͐Q���Ȃ��ƌ����Ă����قǂ������Ƃ����B�Ƃ��낪�A�u��ꎟ�Ζ���@��A���c���͎��Ђ̋Ɛш����̑Ή���Ƃ��āA�z�������̒l������v�����Ă����B���ꂾ���ł͂Ȃ��A���Ђ̎O�z�ꑮ�ԗ����O�z�̔z���Z���^�[�𗘗p���Ă���̂Œ��ԗ���������Ƃ����B����ɁA�z���S���̎Ј����O�z�̎{�ݓ��ɏ풓���Ă��邩��A�������g�p�����ƌ����Ă����B�v
�u�O�z�̋Ɛщ܂łƂ��������ł��ׂĂ����ꂽ���A�͎���Ȃ������B����ǂ��납�A���c���͖������������t���Ă����B�G���ʑ��n�A����v���f���[�X�����f��̑O�����Ȃǂ̍w�����������Ă���B�v
�u���Ɠ��������S�ɖ������Ă���B�ő�̎���悾����䖝���Ă������A���x�����B�v�i���{�o�ϐV��2002�N1��21���w���̗������x�j
�������ă��}�g�^�A�͎O�z�ƌ��ʂ����B���̂悤�Ȍo�܂��o�āA���Ƃ����ڋq����̉^�A�Ƃ���l�ڋq����̑�}�Ǝ҂ւƓ]�����������}�g�^�A�́A���Ǒ傫�Ȑ��������߂邱�ƂɂȂ����̂͂����m�̒ʂ�ł���B
�Ƃ���ŁA�O�z���Ȃ�����������Ԃȑԓx����ꂽ���Ƃ����ƁA�O�z�ɂƂ��ă��}�g�^�A�͑����̑I�����̒��̂ЂƂɉ߂��Ȃ���������ł���B���ɍ��ʉ����}���Ă���T�[�r�X����Ă���̂łȂ���A������ł���ւ�����̂ł���B
�܂�A���}�g�^�A�̎v���Ƃ͋t�ɁA�O�z�̓��}�g�^�A�ɑ��ă��C�����e�B�[�������Ă��Ȃ������̂ł���B���̂悤�Ȍڋq�ɑ��Ă����C�����e�B�[�����߂�w�͂͂���ׂ��ł��낤���A����̌ڋq�̗v���ɉߏ�ɉ����邽�߂ɂ́A���̌ڋq�̂��߂����̓���ȃT�[�r�X����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�Ђ��Ă͑��̌ڋq�̖����x���Q���邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B
�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA���Ђ̃^�[�Q�b�g�ƂȂ�ׂ��ڋq�����͂�����ƒ�߁A�ڋq���i�荞�ނ��Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B���}�g�^�A�̗�Ō����A�l�ڋq�ɂ͂�����ƃ^�[�Q�b�g���i�����̂ł���B
����ł́A�ڋq���C�����e�B�[�����߂���ʓI�ȕ��@�͂���̂��낤���B�O�q�̂悤�ɁA�ꎞ�͑�ϗL���ł���Ǝv��ꂽ�}�C���[�W�E�v���O�����Ȃǂ́A�����Ƃ����Ԃɖ͕킳��A���Ƃ͒P�Ȃ�l��������ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A������d�����k�Ƀ}�j���A���������Ƃ���ŁA�����ɒ������Ă��܂��A�V�������Ԃɂ͑Ώ��ł��Ȃ��Ȃ�B�]���āA�傫�ȑg�D�ŏォ��̎w���ɂ���Čڋq���C�����e�B�[�����߂��i�́A��ό����Ă���B
�t�ɁA����̏]�ƈ��ɂ́A��Ɍڋq�̗���ōl���A�ڋq�������ێ����邽�߂ɑn�ӍH�v���Â炷���Ƃ����߂��Ă���B�ڋq�̗v���ɉ����邽�߂ɂ́A�]���̑g�D�̘g���ċ����W��z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�܂��A�ڋq�Ƃ�����I�ȑ����W�ł͂Ȃ��A���n�I�ȃM�u�E�A���h�E�e�[�N�̊W��z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�܂��A���̂��Ƃ͗����Ƃ̊����ɂ���Č������̒��_�ɒB���Ă����Ǝv���Ă����H��ɂ����鐶�Y�����ɂ��ω��������炵�n�߂��B
�H��ɂ������ё�ʐ��Y�ɂ��R�X�g�_�E���������������̂́A����ł͌ڋq�̖ؖڍׂ��������ɂ͉����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����ŁA�����ƕ�������߁A�H��1�l����̐��i����������܂ŒS����������������ꂽ�H�ꂪ���邻���ł���B���̍ő�̃����b�g�́A���ʑ���̒����ɉ������邱�Ƃɂ���B�܂��A�����I�ȃ����b�g�Ƃ��ẮA��K�͂Ȑݔ��������s�v�Ȃ��Ƃ���������ł��낤�B�����āA���ʑ���̒����ɉ�������Ƃ������Ƃ́A�P�����グ����Ƃ������Ƃł���B��ʐ��Y�ł͐l����̈������O���Ƒ����ł��ł��Ȃ��ɂ��Ă��A�����̗������Y���@���̗p���邱�Ƃɂ���ē��{�����ɐ��Y���_�������Ƃ��A����҂ɋ߂��Ƃ��������b�g�ɓ]���ł���̂ł���B
�����悤�Ȃ��Ƃ́A���}�g�^�A����}�ւŐ��������錍�Ƃ��d�Ȃ�B��}�ւ��n�߂�O�̂��Ƃł��邪�A���Ђ͑��Ђ��x��Ē������A���ɐi�o�����B���̌��ʂ́A���Ƒ��Ђɔ�ׂ�ƒ������Ⴂ���v���ƂȂ��Č���Ă��܂����B�^�A�Ƃ͓����K���Ǝ�ł��邩��A�������Ƃ����Ă���Η��v���������悤�ɂȂ�Ȃ��Ă͂��������B���̗��R�́A���ЂƂ̏o�x����J�o�[���邽�߁A���Ђ͑�ʗA���������߂�����𒆐S�Ɍڋq�l���𐄐i�������Ƃɂ���B�����̉ݕ��͏W�z�̎�Ԃ͂�������̂́A�P���͍����B���Ƒ��Ђ͂�������肭���p���āA����Ə����������ėA�����Ă����̂ł���B���̂��Ƃ��A��ɑ�}�ւގ��̃q���g�ɂȂ��������ł���B��}�ւ͉ƒ�̎�w���^�[�Q�b�g�ڋq�Ƃ��邪�A��w�͉^����l�����肵�Ȃ����A�����Ŏx�����Ă����B���̂����A��}�ւ̉�Ђ͂�����̎�w�ł��ȒP�ɉו��������悤�ȃV�X�e�������グ�A���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�����āA�u��}�ւ�S�����S�I���݂́A����Ōڋq�ɐڂ����3���l�́u�Z�[���X�E�h���C�o�[�iSD�j�v�ł���B�ނ�͉ו��̏W�z�A�c�ƁA�W���ȂǂЂƂ�ł��܂��܂ȋƖ������Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��Ɂu���i���̐E�l�v�̂悤�ȓ����������߂���B�T�b�J�[�Ō����A�őO���́u�t�H���[�h�v�ɂ�����ނ�̂��C�������Ɉ����o���A�y���������Ă��炤���B�S���o�c�̐����͂����ɂ������Ă���v�i���q ���j�w�o�c�w�xp171�j�̂ł���B�P�Ȃ鎖�Ə�̃A�C�f�A�ł͂Ȃ��A�������̓I�Ƀp�b�P�[�W���Čڋq�ɒł������炱�����}�g�^�A�͐��������̂ł���B
���n�Љ�ɂ����Čڋq�̒����ɍׂ��������Ă������߂ɂ́A�K�͂̎��v��Nj����邩���ɁA�H���ЂƂ�ЂƂ肪�H��ƂȂ�~�N���g�D�ɕς���Ă�������Ȃ��A���邢�͏]���͎Ԃ��^�]���Ă���悩�����^�]�肪���܂��܂ȋƖ������Ȃ��T�[�r�X�t�����g�ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ͑�ϋ����[���B
�ڋq���C�����e�B�[�����߂���悤�Ȏs��ɂ����ẮA�ڋq���i�荞�ނ��ƁA����ɂ�����ٗʌ����傫���Ȃ邱�Ƃ���l���āA�]���̂悤�ȃs���~�b�h�^�g�D�ł͂Ȃ��A���n�I���z�Ɋ�Â��l�b�g���[�N�g�D�����߂���悤�ɂȂ�̂ł���B
3.�ƐъǗ��̕��@
�g�D�ɂ͑��l�Ȃ���������݂���B�O�q�̋K���s��ɂ������Ƃ��A�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ��Ċ��Ă����Ƃ��A���邢�͐��n�s��ɂ������Ƃ��A���ꂼ��̎s��̓����ɍ��v���Ă���̂ł���A���ɓ������d�v���������Ă��Ƃ�����̂ł���B�����A���[���[���ŐV�K�ڋq���l���ł���̂ł���A���̂悤�ȍ����̂�ׂ��ł���A�ڋq���C�����e�B�[����ɒNj�����ׂ��ł͂Ȃ����낤�B
��Ƃ̂�������قȂ�̂ł��邩��A�ƐъǗ��A���邢�͂��̑O��ƂȂ�l���Ǘ��̕��@�����R�قȂ��Ă���B��\�I�ȊǗ����@����������グ�A�ǂ̂悤�Ȋ�ƁA�s��ɍ��v���Ă���̂����ڏq����B
3.1�J���X�}�^
��ɁA������Ƃ��Ƃ̗����グ���Ɍ�����A�l�哱�̊Ǘ����@�ł���B���S�ƂȂ郊�[�_�[���S�Ă����d���Ă����B�ǐ�����l�Ԃɂ́A���[�_�[����ʂ̎w�����^�����A���̒ʂ�ɍs�����邱�Ƃ����҂���Ă���B
���R�A���̕]�����w���ɏ]�������ǂ������d�v������A�ʂɔ\�͂��������ǂ����͖���Ȃ��B
���_�Ƃ��ẮA�S�Ă����[�_�[�l�����d���Ă��邽�߁A���f�������A�w���̈�ѐ����ۂ��₷�����Ƃ��グ����B
���_�́A������x�ȏ�̋K�͂̑g�D�ɂȂ�ƁA���������[�_�[�ɏW�����߂��Ă��邽�߁A���[�_�[���s�݂̏ꍇ�̃}�l�W�����g���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ���������B�܂��A�l�̋Ɛт͂ЂƂ�̃��[�_�[�ɂ���Č��߂��Ă��܂����߁A�����œ����l�ԂɂƂ��ẮA���l�ɑ��ĉ����ꂽ�����]�����A�����Ђ����ɂ���Č��߂��Ă��邩�̂悤�Ȋ��o�������₷���B���ꂾ���łȂ��A��������ۑ�������Ă����\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�I�Ȏd��������C���Z���e�B�u���Ȃ��Ȃ�A�ǂ����Ă��w����҂��ɓI�Ȏp���ɂȂ菟���ł���B
�����ȑg�D�Ɍ����Ă���Ǘ����@�ł���ƌ����邾�낤�B
3.2�}�j���A���Ǘ�
�J���X�}�^�̌��_���������ׂ��A�ŏ��ɍ̗p�����̂��A�}�j���A���ɂ��Ǘ����@�ł���B
�}�j���A���Ǘ��Ƃ́A�ʂ̐E���͂��A���ꂼ��̐E�����}�j���A���ɒ�`����B�����āA���̎d�������Ȃ���l�Ԃ����̐E���ɏA����̂ł���B
�O�L�K���s��̕����ł��G�ꂽ�Ƃ���A�}�j���A���Ǘ��̌��_�́A�E�����Œ艻����Ă��邱�Ƃ���A�Ƃɂ������������₷�����Ƃł���B
�싅�ɚg����A�O�V�ԂɃS�����]�������Ƃ��ɁA�V���[�g�ƎO�ێ肪�����̃|�W�V�������炿���Ƃ��������A�q�b�g�ɂ��Ă��܂��悤�Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȊԌ��߂邽�߂ɁA�l�������������B����Ȃ��u�������v�̂Ƃ��ɔ����Ă����Ԃɑg�D�͔�剻���Ă����B�����g�D�Ƃ͗m�̓������킸�����悤�Ȃ��̂ł���炵���B
�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N���邩�ƌ����ƁA�O�V�Ԃ̃S���ɔ�т��悤�ȍs�����]������Ȃ�����ł���B�Ⴆ�A�V���[�g���O�V�Ԃ̃S���ɔ�т����Ƃ��āA���܂��ܕߋ��ł����Ƃ���B�ނ͌����ĎO�V�Ԃ̃S���ɔ�т����Ƃ����҂���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�ߋ��ł����̂́A�����V���[�g�̕ߋ��]�[���ɔ����ł���Ɖ��߂����B�t�ɁA�����ނ�����������ǂ��Ȃ�̂ł��낤�B���R�G���[���L�^�����B
�t�@�C���v���[���]�����ꂸ�A���s�������]�������̂ł���A�N�����̂悤�ȍs���������ĂƂ낤�Ƃ͂��Ȃ��Ȃ�͓̂��R�ł���B
�������A���̂悤�ȊǗ����@�ɂ����_�͂���B�Ⴆ�A�������̖��o���҂��g���ăr�W�l�X�����藧���Ă���悤�ȏꍇ�i�A���o�C�g�𑽗p����n���o�[�K�[�E�V���b�v�Ƃ��R���r�j�G���X�E�X�g�A�Ȃǁj�A�]�ƈ��̏K�n��O��Ƃ��ċ��炵�Ă����̂ł͎��ԓI�ɂ��A�R�X�g�I�ɂ��Ԃɍ���Ȃ��ł��낤�B�����Ń}�j���A���ɂ��Ǘ����v�������̂ł���B
3.3�ڕW�ɂ��Ǘ�
���Ƀ|�s�����[�Ȃ̂��A�ڕW�ɂ��Ǘ��ł���B����ےP�ʂɖڕW��݂��A������]�ƈ��ЂƂ�ЂƂ�ɔz������B������m���}�ȂǂƌĂ����̂ł���B
�������A�ォ��^������ڕW�͉��X�ɂ��Ċ�]�I�ϑ��Ɋ�Â������y�ϓI�Ȃ��̂ł���ꍇ�������B��������ڕW��ݒ肵�Ă��ꂪ�ł��Ȃ��ƖڕW���B�ł���Ƃ��ĕ]������Ȃ��̂ł��邩��A���R���ꂩ��̓u�[�C���O���N���邵�A�]�ƈ��̃��������ቺ����B
�����ŁA�ŋ߂ł͏]�ƈ��Ƃ̘b�����ŖڕW�����߂�悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�������A�ڕW��ݒ肵�Ă��̒B���x�ŕ]������̂ł���ŏ�����ڕW��Ⴍ�ݒ肵�Ă��܂��悢�B�܂��A�ڕW�̓�Փx���]�����Ȃ��ƁA�ȒP�ȖڕW�����ݒ肵�ĒB�������҂����Ƃ��ł��Ă��܂��B�܂��A���Ƃ���s�ɂ����ėa���c����Z���c��������ڕW�ɐݒ肵�Ă��܂��ƁA���̈����ݏo��ւ̗Z���𑝂₵����A�Z�����җ������Č�������̗a���c�����҂����肷��ȂǁA���e������Ȃ����т�Ϗグ�Ă����Ă��܂����ƂɂȂ�B
���̂悤�ȋƐт��^�̋ƐтłȂ����Ƃ͖��炩�ł���B�Ǘ��҂́A�Ɛт̎��ɂ��Ă��������`�F�b�N���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B���̂��߂ɂ́A������̃R�~���j�P�[�V�������K�v�ɂȂ��Ă���̂ł���B
3.4�ƐтƂ͉���
�u�������J�[�u�ɂ��]�����c�����Ƃ���l�����́A�Ԉ�������_�Ɋ�Â��Ă���B�Ԉ�����e��؎��ɂ��Ă��镶�����琶�܂�Ă���B�Ȃ���w���ƌ�́A���т̕]������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�v
�u���т��グ�悤�Ƃ���w�͂͏��w�Z1�N�̂Ƃ����琶���̈ꕔ�ɂȂ��Ă���B���w�Z���琬�т̕]���͎n�܂��Ă���̂��B�I���́A�t�b�g�{�[����`�A���[�_�[�̃`�[���Ƃ������Ƃ���ł������Ȃ��Ă���B�����w����͓��w��F�߂��A�ʂ̑�w����F�߂��Ȃ��̂́A�I���������Ȃ��Ă��邩��ł���A��w���s���ɁA�ŗD�G��D���̏ƍ������^�����̂��܂��A�I���������Ȃ��Ă��邩�炾�B�v
�u���܂��20�N�Ԃ��̂����A�����݂͂Ȓi�K�]�����Ă���B�Ȃ��A�N���Ă��鎞�Ԃ̂قƂ�ǂ��߂����E��ŁA�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�v�i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��p255�j
�W���b�N�E�E�F���`�̂悤�ɖ��m�Ɍ������Ă��܂��ƁA���̂Ƃ���ł���Ǝv���Ă��܂������ł��邪�A����ł́A�]�ƈ��̋ƐтƂ͉����ǂ̂悤�ɑ��肷��̂ł��낤���B��L�u�ƐъǗ��Ƃ͉����v�̃p�[�g�ł��A�ƐтƂ͉����������Ė��炩�ɂ��Ȃ������B�������A�قƂ�ǂ̕����A�ƐтƂ͔��グ���A���㍂�Ȃǂ̐��l�ő������̂ł���Ɨ������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B����Ȋw�I�Ȍ��t�Ō����A�����ڕW�ł���B�]�ƈ��̋Ɛс������ڕW�Ȃ̂ł��낤���B
���ݑ����̊�Ƃ����ʂ��Ă���̂͐��n�s��ł���B���n�s��ɂ����ẮA�������ڋq�̃��C�����e�B�[���q���~�߂Ă������Ƃ��v������邱�Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B
�Ⴆ�A���Z�@�ւ��ڋq�ɏ��i�����߂�ꍇ���l���Ă݂悤�B�ڋq�ɃA�v���[�`���邽�߁A�ڋq�̃|�[�g�t�H���I���������A���̌��ʁA�K���ȃ|�[�g�t�H���I�ł��邱�Ƃ����������Ƃ���B���̏ꍇ�A�ڋq�̃��C�����e�B�[���ێ����邽�߂ɂ͂ǂ̂悤�ȍs�����v�������̂ł��낤���B�ڋq�̃|�[�g�t�H���I���K���Ȃ��̂ł���ȏ�A����ȏ�̃A�h�o�C�X���s�v�ł��邵�A����ׂ����i���Ȃ��B���������邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�Ƃ���ŁA�]�ƈ������̂悤�ȑΉ�����������Ƃ���Ƒ��͕]���ł���̂ł��낤���B
�u�u���v���ꎞ�A�]���ɂ��Ă��A�ڋq����̗a���莑�Y�𑝂₷���Y�Ǘ��^�c�Ƃ�O�ꂷ��v�B���C�����،��̉�����p�В��͍��t�����錾�A�c�ƕ��j��]�������B�x�X�̋Ɛѕ]���ŕ]����̖�6�����߂Ă������v�̊�����1�|2���Ɍ��炵�A�a���莑�Y�̑����z��8�|9���֍��߂��B�ڋq�̐M�����d������c�Ƃ��B�v
�u���N��B�a���莑�Y�͑��������A�o��Ԏ����\�z�ȏ��70���~�ɖc���B�Q�Ă����Ђ͉������瑹�v����_���x���̎��v�ڕW��ݒ肵�A����8����B�����ď��߂ėa���莑�Y�����z��]������`�ɏC�������B�v
�u�č����̎��Y�Ǘ��^�c�Ƃ����M���X�Ŏ����������������`���{�،��B3�N�Ԃ̋ꓬ�̖��A�l�������̌o��Ԏ��͗v700���~�ɒB���A�x�X��l����7���팸�ɒǂ����܂ꂽ�B�v�i�ȏ���p�͂���������{�o�ϐV��2002�N1��29���u�a�߂���Z�v�j
�c�Ɛ��т��d������A���ǂ͉�]�������ڋq�Ɋ��߂�u�����v�̎����甲���o���Ȃ��B�̎��̓]����}�낤�Ǝv���Ă��A�c�Ɛ��т��オ��Ȃ��ƁA�������Ɠ����o���Ă��܂��B�����������`�،����A�l����͕����Ȃ��ƌ����Ă͂��邪�A���j�I�ɂ͓��Ђ����{�ɂ�����l�c�ƕ�����k��������̂�2�x�ڂȂ̂ł���B
���̂悤�ȍs���������t������ƁA�\�����[�V�����E�v���o�C�_�[�Ƃ��Ẳc�ƕ��j�i��L2�Ђ̏ꍇ�͎��Y�Ǘ��^�c�Ɓj���F�Č����Ă��܂��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��N����̂��ƌ����ƁA��ƋƐтɂ��Ă��A�l�̋Ɛтɂ��Ă��A���ǂ͍����I�Ȏw�W�ɂ���Ă̂ݑ����邩��ł͂Ȃ����낤���B
��Ƃ́A�����I�ȖڕW�ȊO�ɂ��A�n��Љ�ɍv������A�Ȋw�Z�p�̔��W�ɍv������A�n�����ɍv������Ƃ������ڕW�������Ă���i1�K�ł������ׂ��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���A�ȂǂƂ������Ƃ��������Ă����Ƃ�����������Ƃ͎v���Ȃ��j�B�܂��A��Ƃ��c�Ɗ������s���Ă�����ł̖ڕW�Ƃ��āA���q�l�̖������ŏd�����A�@�߂����炵���K���Ȕ̔��������s���A�Ȃǂ��݂����Ă��邱�Ƃ������B���̂悤�ȖڕW���݂�����̂́A�ڋq�����x���グ�邱�Ƃ������I�ɂ͍����I�Ȏw�W�i���グ���Ȃǁj�ɊҌ�����邱�Ƃ�����Ă���̂ł���B
�Ƃ��낪�A���̂悤�ȕ��j������Ă��A���ǂ͉c�Ɛ��т��オ��Ȃ��Ă͕]������Ȃ��B��L�،���Ђł́A�킸�����N�ŋO���C�������悤�ł���B���NJ�ƋƐт͍����w�W�Ŕ��f����Ă��܂����߁A���F�������Ȃ�Ƃ������Ɠ����Ă��܂��̂ł���B�o�u�����Ƀ��Z�i�������Ƒ�ՐU�镑�����Ă����Ȃ���A�i�C�������Ȃ�Ɛ���o���Ȃ��Ȃ������{��Ƃ̍s�������̂��Ƃ������Ă���B
�������A���I�]���͓���B20���I�ɂ�����ł��̑�Ȍo�c�҂ł���W���b�N�E�E�F���`�����̂悤�ɏ����Ă���B�u���̂悤�ɐl���]���͔��Ɍ��i�ł���ɂ�������炸�A���N�̎Ј��̈ӎ������ł͋����ׂ����ʂ��łĂ���B42�̎���̂����A�����x�������Ƃ��Ⴂ�̂��A���̎��₾�������炾�B�v�u�u���Ђ́A�����̂������ʂ������Ă��Ȃ��Ј��ɑ��Ēf�łƂ����p�����Ƃ��Ă���B�v�v�u2001�N�̒����ł́A���̎���ɃC�G�X�Ɠ������Ј���75�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ��B99�N��66�p�[�Z���g����͉��P���Ă��邪�B�ق��̎���ł͂����ȂׂĖ����x�������̂ɔ�ׁA���̐����͋ɒ[�ɒႢ�iGE�ł̃L�����A�́A�u������Ƒ��ɍD�܂����e����^���Ă���v�Ƃ������ڂɂ��ẮA90�p�[�Z���g�ȏオ�C�G�X�Ɠ����Ă���j�v�i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��pp262�j�����ł���B���̌��ʂɑ��ăE�F���`�́A�u���̌��ʂ́A�ǂ̃��x���ł��I�ʂ������ɏd�v�ł��邩�������Ɠ����ɁA�Ј��̂ق�������ɑ�_�ŗ����ȕ]����]��ł��邱�Ƃ������Ă���v�Ǝ��掩�^���Ă���B
���ɂ́A���̓��v���l�́A����ɑ�_�ȕ]�������߂Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����ɑ����]���ւ̕s���ƁA���l�ɑ��鍂�]���ւ̔����������悤�Ɏv����̂ł��邪�������ł��낤���B�������ɁAGE�͋ɂ߂đ�_����i�I�Ȑl�ޕ]���������A���H���Ă����Ƃł���B����ɂ�������炸�A4�l��1�l�A���̑O�N��3�l��1�l���]���ɖ������Ă��Ȃ��̂ł���BGE�Ј���30���l�����Ƃ���ƁA7��5��l���s���������Ă��邱�ƂɂȂ�B���������A30���l�̎Ј����ЂƂ̉��l�ς̉��ɕs���Ȃ��]�����邱�ƂȂǕs�\�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�W���b�N�E�E�F���`�Ƃ͑ΏƓI�Ƃ��v���鏬�q�@���j�������悤�ȔY�݂�ł������Ă���B
�u�l���l�ۂƂ������͔̂��ɑ厖�Ȃ��̂��B�Ј����ꐶ���������Ă���̂́A�����̎d����F�߂Ă��炢��������ł���B�����ĎЈ��̓����Ԃ�������ɕ]�����A���i�⏸���ɔ��f���邱�Ƃ͑g�D�̊�������}�邤���ŕK�v�s���ł���B�v
�u�������A���̕��@�_�ɂȂ�ƁA�����ւ������ƂɋC�����B���{�ł́A�d�����Ј��l�ɒ��ڌ��т����Ƃ����Ȃ��A�W�c�Ŏd�������Ȃ��Ă��邩��ł���B�v�i���q�@���j�w�o�c�w�xp269�j
�����ŁA�l�ł͂Ȃ��W�c�Ƃ��ĕ]��������A�܂��A�]���҂ɂ��]���̂Ԃ���Ȃ������߂Ɂu�����Ȓ����]�_�Ƃ̍l�Ă������@�v�����{�����肵�����A�[���̂������̂͌�����Ȃ����������ł���B
�u���̌��_�́A��i�̖ڂ͗���ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�����A�Ј��ɂƂ��Ă݂�A�d��������Ă����Ȃ��Ă��]���������ł͔[�����Ȃ��B�ꐶ����������l�Ƃ��Ȃ������l�ɍ������Ȃ���A���������^���A�Г��������ێ��ł��Ȃ��Ȃ鋰�������킯�ł���B�v
�u�����ōl�����̂́A�u������̕]���v�ƁA�u������̕]���v�B������̕]���͕����ɂ��]���A������̕]���Ƃ͓����ɂ��]���ł���B�����ĕ]�����ڂ͎��тł͂Ȃ��g�l���h���B�v
�u�����ł��邩�A���\���Ȃ����A���Ȏ�`�ł͂Ȃ����������̋C���������邩�A�v�����̋C���������邩�ȂǁA�l���Ɋւ��鍀�ڂɓ_��t����B�̑��̍̓_�̂悤�ɁA�����̎Ј��̍̓_���W�߁A�ō��̓_�ƍŒ�̓_���O���A�c��𑫂��ĕ��ϓ_���o���B�܂�A�����̖ڂŕ]������B�v
�u���{�ł́A�q�ϓI�ɒʗp������ѕ]���̕����͌�������Ȃ��B�Ȃ�A���߂Ď��O�̍�Ƃ��ĉ�����̕]�����s������悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł���B�������P�Ƃł͂Ȃ��A���̐��x�ƕ��p����̂ł��邪�A���́A�l���̗ǂ��Ј��͂��q�l�Ɋ���ǂ��Ј��ɂȂ�ƐM���Ă���B�v�i���q�@���j�@�w�o�c�w�xp270�j
���́A�W���b�N�E�E�F���`�����l�ȕ]�����@�ł���360�x�]�����������ƂŗL���ł���B
�u���ԓ��̕]���Ƃ����͉̂��ł����������A���̕]���V�X�e���ɂ��Ă��A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA�u�����������v�\��������B����������������̂悢���ƈȊO�͌���Ȃ��Ȃ�A�S���̕]�����ǂ��Ȃ�B�v�i�W���b�N�E�E�F���`���Op248�j
�]�����j�����܂�p�ɂɕύX����邱�Ƃ́A�]���̈�ѐ���ۂ���������D�܂����Ȃ��B�������A������Ƃ����ē����]�����j�����炾��Ƒ����Ă���ƁA�]�����т��グ�邽�߂Ɏd��������l�Ԃ��o�Ă��Ă��܂��B
���̂悤�ȈӖ��ł́A����@���ꂪ�����̒��ŏq�ׂĂ��邱�Ƃ͋����[���B�u�l���]���̂����\�͂̕]���́A�Ǘ��҂������̐l�Ԃ̉��l��]������̂ł͂Ȃ��A�܂��A�l�Ԃۗ̕L���邷�ׂĂ̔\�͂�]������̂ł͂Ȃ��A�ۗL���Ă���\�͂̂����A�����ꕔ�ł���d���̒S����Ƃ��ĐE�����s�\�͂�]��������̂ł���B���̐E�����s�\�͂́A��ʂɒn���C�́A���f�́A���́A�́A�w���͂ȂNJe�v�f���ɕ]�������B���̂��߁A�]������Ƃ������Ƃ͋Z�@�ł���A�Z�p�I�Ȃ��̂ł���ƍl������B�P��������A����������ΏK���������̂Ȃ̂��B�v�u�]������鑤���A��Ƃ��K�v�Ƃ��Ă���\�͂𑨂��Ă���̂ł���A�S�l�i�A�S�\�͂𑨂��Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ̔F���������Ƃ��d�v�ł���B�v�i����@����w���ꂩ��̐l���]���Ɗ�x�j
�]�����t�Ƀe�N�j�J���Ȃ��̂ł���ƕ߂炦�A�]���҂̕��S���ߓx�ɂȂ�Ȃ��悤�ɔz�����Ă���B�܂�Ƃ���A�l�Ԃ��l�Ԃ�]������̂ł���B�����ł��邱�Ƃ����҂���̂��Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
3.5�o�����X�E�X�R�A�J�[�h
���݂ł́A��������ROI�i�������{���v���j��EPS�i1�����藘�v�j�Ƃ����������w�W�����Ŋ�Ɖ^�c���[���ɍs������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ���������n�߂Ă��Ă���B
�����āA���ݑ����̊�Ƃ�������悤�Ƃ��Ă���̂��o�����X�E�X�R�A�J�[�h�̍l�����ł���B�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�́A�����I�w�W�ƃI�y���[�V������̎w�W�i�ڋq�����x��g�D�̉��P�Ȃǁj�̗��ʂ��g�o�����X�ǂ��h�܂�ł���B����ɂ���āA���܂��܂Ȗʂ����ƋƐт�]�����悤�Ƃ������̂ł���B
�u���̃X�R�A�J�[�h�͔�s�@�̃R�b�N�s�b�g�ł����A�e��v��̎w�j�ՂƎw����̂悤�Ȃ��̂ł���B��s�@�̑��c�͕��G�ŁA�p�C���b�g�ɂ͑����ʂ���̏ڍׂȏ�K�v�Ƃ����B�R����X�s�[�h�A���x�A���ʁA�ړI�n�Ȃǂ̏��̂ق��A���݂����č���̏�Ԃ��������l�ȍ��ڂɂ��Ĕc�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ĒP��̎w�W�ɗ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
��̓I�ɂ́A
�@�ڋq�͂ǂ����Ă��邩�i�ڋq�j
�A�ǂ̕���ŗD�搫���m�ۂ��邩�i��Ɠ����j
�B���P�ƕt�����l������]�n�͂��邩�i�Ɩ����P����у��x���A�b�v�j
�C����͂ǂ����Ă��邩�i�Ɛсj
�Ƃ������w�W���I��邱�ƂɂȂ�i���o�[�g S.�L���v�����A�f�C�r�b�g P. �m�[�g���u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�Ƃ͉����vpp158�|159�j�B
�����őI�ꂽ�̂́A�����Ƃ̃o�����X�E�X�R�A�J�[�h�̗�ł���B�]���āA�����Ɍf����ꂽ���ڂ����ׂĂ̊�Ƃɓ��Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ��B�����āA����4�̍��ڂ̒��ɂ��܂��܂ȕ]���w�W������ɐݒ肳��邱�ƂɂȂ�B
�u����܂ł̓`���I�ȍ����w�W�́A�O�L�ɉ����N���������������Ă������ł��邪�A���ɂǂ�����Ɛт����P�ł��邩�͋����Ă���Ȃ��B�������A�X�R�A�J�[�h�́A��Ƃ̌��݂Ə����̐����̊�b��z�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�v
�u����ɁA�`���I�ȑ�����@�Ƃ͈قȂ�A�X�R�A�J�[�h��4�̎x�X����������́A�{�Ɨ��v�̂悤�ȊO�ʓI�ړx�ƁA�V���i�J���̂悤�ȓ��ʓI�Ȏړx�Ƃ̃o�����X���}���Ă���B���̃o�����X��������w�W�̂������ŁA�o�c�҂͈قȂ�Ɛѕ]���w�W�ǂ����̂��܍��킹���������Ƃ����邵�A����̐����v�����������Ȃ��悤�ɒ������A�����̖ڕW�̒B���ɍv������B�v�i���o�[�g S.�L���v�����A�f�C�r�b�g P. �m�[�g���u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�ɂ���Ɗv�V�vp184�j
�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�̓����ɓ������Ă̍ő�̖��́A��ʓI�Ȋ�ƕ]���i�Ⴆ�Ί����j�ɕK�������D�e����^���Ȃ����Ƃł���B�u�X�R�A�J�[�h�͂���Ȃ�]�����x�ł͂Ȃ��B����͋�����A����I�ȋƐђB���ɂ͂��݂����邽�߂̌o�c�V�X�e���Ȃ̂ł���v�i���o�[�g S.�L���v�����A�f�C�r�b�g P. �m�[�g���u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�ɂ���Ɗv�V�v�w�Ɛѕ]���}�l�W�����g�xp201�j�Ƃ��Ă��A��ʓI�ɕ]������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�O�q�،���Ђ̂悤�ɁA�Q�ĂĎ��Y�Ǘ��^�̉c�ƕ��j��P�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
����1�_���̃V�X�e���Ō��O�����̂́A��e��ǂ����͈̂�e���A�Ƃ������ʂɏI����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B�É��^�A�Ƃ�����Ђɏo�����Ă������q�@���j�́A�J�Ў��̂̑������w�E����A����؍H�������w����悤�ɘJ����ē����Ɍ���ꂽ�����ł���B
�u�債���ݔ��̂���H��ł��Ȃ����A���S�̂��ߑ傰���ȓ��������Ă���l�q���Ȃ��������A���̍H��̌o�c�҂̘b���Ď��͊��������B�v
�u���S�́A�v����Ɍo�c�҂̐S�\���ɂ��Ƃ��낪�傫���B���ꂪ�ނ̈ӌ��ł������B�H��ɂ͑傫�ȗΏ\���̊��������Ă����B����͂ǂ��ł�������i�ł���B�Ⴄ�̂́A�Lj�t�ɑ傫�Ȏ��ŁA�u���S���A�\�����v�Ə��������������Ă��������Ƃł���B�v
�u�H��̌o�c�҂͂����������B�v
�u�\�\�O�́A�{���ɘJ�Ў��̂����������B�ł��A�l���̑������l�����Ƃ��A���Ƃ��Ă����̂����炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ōl�����̂́A�\�����グ�邱�Ƃ����������Ă��邤���͎��̂͂Ȃ��Ȃ�Ȃ����낤�Ƃ������Ƃ������\�\�B�v
�u���̋C������\�����߂��A�u���S���A�\�����v�Ƃ����W����H����Ɍf�����B���Ԃ��o�ɂ�A���S�̎��т͏��X�ɏオ�������A�\���͌����ė����Ȃ������Ƃ����B�v
�u�u���S���\�����A�ǂ��������������ƌ����Ă��������́A���ǂǂ�������r���[�ł����ˁB�v�Ƃ̍H��o�c�҂̌��t�́A���ɋ������̂��������B�v�i���q�@���j�w�o�c�w�xpp143�\144�j
�É��^�A�ł́A�u���S���A�\�����v�Ƃ����W����A���}�g�^�A�ł́u�T�[�r�X����A���v�͌�v�Ƃ������b�g�[������������ł���B
�������A���̂悤�Ȍ��t������̐ӔC�҂������������ł͖��Ӗ��ł���B�V�N�̌��ӂł͈��S��T�[�r�X���ł��o����Ă��A���Z�����߂Â��Ƃǂ����\���◘�v���グ��悤�Ɍ����ł��낤�ƌ���������Ă��邩��ł���B����Ȃ獡�܂łǂ���ŏ�������S��T�[�r�X���\���◘�v��Nj����������ȒP�ł͂Ȃ����B
���S�Ɣ\���A�T�[�r�X�Ɨ��v�A��������g���[�h�I�t�̊W�ɂ��邩�Ɏv����B�������A�g���[�h�I�t�ɂ��邩��Ƃ����āA�ǂ��������̑Ή������Ă����̂ł́A�i���ɖ��͉�������Ȃ��B���̂悤�ȕW��E���b�g�[�́u�В������猾���錾�t�ł���B�����炱���A�t�ɎВ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����t�Ȃ̂ł���B�v�i���q�@���j�w�o�c�w�xp142�j�}���l������������ڂ������Ă��邾���ł́A�����ď]�ƈ��͕t���Ă��Ȃ��B
�������Ȃ���A��Ƃ̋Ɛѕ]���ɂ����Ă��A������I���ʂ��d�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ���Ȃ��Ǝv����B�����ɁA��Ƃ̒n�����ւ̍v���x����ɓ������I�ʂ����G�R���W�[�E�t�@���h�����X�Ə،���Ђ��甭������Ă���A����s�����D���������ł���B
��ƋƐт����ʓI�ɕ]�������悤�ɂȂ�A���グ������������������Ƃ����čQ�ĂĎ��Y�Ǘ��^�c�ƕ��j��P��ȂǂƂ����݂��Ƃ��Ȃ��^��������K�v���Ȃ��Ȃ�̂ł��낤�B
4.��V�̕���
�ȏ�q�ׂĂ����悤�ȋƐѕ]���̌��ʂƂ��āA�]�ƈ��ɂ͕�V���x�����邱�ƂɂȂ�B��Ƃ���]�ƈ��ɑ��ẮA���^�A���������A�ސE���E�ސE�N���ȂǁA���܂��܂Ȗ��ڂŕ�V���x������B���̂����A�ł��䗦�������̂́A���^�ł���B
���^�ȊO�ɂ��A�X�g�b�N�E�I�v�V�����A�ސE���E�ސE�N���A�ސE�N���̂ЂƂ̐��x�ł���401�ik�j�Ȃǂ��܂��܂ȕ�V���x������B�����ł́A���^�ȊO�̕�V�Ƃ��āA�����I�ȃC���Z���e�B�u�ƍl������X�g�b�N�E�I�v�V�����A�ސE���E�ސE�N���A�����čŋߒ��ڂ���Ă���401�i���j�v�����ɂ��āA���̐��i�A�����b�g�E�f�����b�g���l����B
4.1�X�g�b�N�E�I�v�V����
�X�g�b�N�E�I�v�V���������̌o�܂ɂ͂��܂��܂Ȃ��̂����邪�A�����̏ꍇ�ɏd������Ă���̂́A�X�g�b�N�E�I�v�V��������l�Ԃɑ��Ċ�ƑS�̂̋ƐтɊ�Â�����V���x�������Ƃɂ���ƃ}�C���h�̈琬�ɂ���Ǝv����B
�u����܂ł̐��x�ł́A���N�̃{�[�i�X���ő�̕�V�ɂȂ��Ă����B�����ă{�[�i�X�͏������鎖�ƕ���̋Ɛтɉ����Č��߂��Ă����B�v
�u���鎖�ƕ���̋Ɛт��D���Ȃ�A��БS�̂̋Ɛт��s�U�ł��{�[�i�X�͏o��B�v
�u��Ђ�����ł���̂Ɉꕔ�̎��ƕ��傪�����Ɋ݂ɂ��ǂ���悤�Ȃ��̂ŁA���͂��������l�����ɂ͉䖝�Ȃ�Ȃ������B�v
�u���́A�X�̎��Ƃ����A��Ђ̋Ɛт⊔���̂ق����Ј��ɂƂ��ĈӖ������悤�ɂ����������B�v�i�W���b�N�E�E�F���`�w�W���b�N�E�E�F���` �킪�o�c�x��pp295�|296�j
���̂悤�ɁA�����C���Z���e�B�u�̈�Ƃ��ē������ꂽ�X�g�b�N�E�I�v�V�����ł��邪�A�ŋ߂ł͂��̕��Q�����ƂȂ��Ă���B
�܂���������̂́A�����͑傫���ϓ�����Ƃ������Ƃł���B
�����Ƃ͏��������z������Ƃ̉��l��\���Ă���Ƃ���Ă͂��邪�A���������ǂ����ؖ��������̂͂��Ȃ��B�܂��A�{���e�B���e�B�[���ɂ߂č����B
���������āA�����������Ƃ��ƒႢ�Ƃ��ɗ^����ꂽ�I�v�V�����̉��l�ɂ́A�傫�ȍ����o�Ă��܂��B�������͎̂s��Ō��肳���̂ŁA�o�c�w�́A���邢�͏]�ƈ��̓w�͂œ���������̂ł͂Ȃ��B
�܂��A�I�v�V��������Ђɑ���V�����s�������ł���ꍇ�ɂ́A�I�v�V�����̌����s�g�ɂ���Ĕ��s�ς݊������̑���������B�������̑����́A���ݓI�ɂ͊��������������鈳�͂ƂȂ肤��B�]���āA�X�g�b�N�E�I�v�V�����͊�������̐��ݓI�]���̂����ɐ��藧���Ă���Ƃ�������B
�܂��A�X�g�b�N�E�I�v�V�����͂����܂ł��I�v�V�����ł���A�^����ꂽ�l�Ԃ������̃_�E���T�C�h�E���X�N��Ȃ����Ƃ����ł���Ƃ���Ă���B�X�g�b�N�E�I�v�V������^����ꂽ�l�Ԃ��o�c�҂ł���ꍇ�ɂ́A�����������グ�邽�߂̖`���I�{������\�����w�E����Ă���B�������オ����̌o�c�҂�������n�b�s�[�ł���B�������A���̎{���s�ɏI������ꍇ�A����͊��������ɂ�鑹�����邪�A���̌o�c�҂͎�������킯�ł͂Ȃ��B
���������X�g�b�N�E�I�v�V���������p�����悤�ɂȂ��������́A�V���R���o���[�ɑ�\�����x���`���[��Ƃ��D�ꂽ�l�ނ��W�߂邽�߂ɑ��z�̕�V���x�����K�v������������ł���B�����グ���ɂ��莑�����v�̋����x���`���[��Ƃ́A�����̗��o�͔��������Ƃ����v���������B�����ōl����ꂽ�̂��X�g�b�N�E�I�v�V�����ł���B����Ӗ��ł́A�I���o�����X�Ŕ�p�Ɍv�コ���]�ƈ��ւ̎x�����A�I�t�o�����X�̋������ɐU��ւ��Ă���̂ł���B�X�g�b�N�E�I�v�V������^����ꂽ�l�Ԃ́A�I�v�V�������s�g���Ďs��ł���p���邱�Ƃɂ���ċ��K��B
�]���āA�������㏸��ɂ��鎞�̓I�v�V�����̍s�g��}�����悤�Ƃ����i�I�v�V�������̂��s�g���Ă��A�������͔̂��p�����ɏ��L��������j�C���Z���e�B�u�������B�t�ɁA������������ɓ������A���邢�͊�Ƃ��̂��̂��낤���A�Ƃ������ꍇ�ɂ́A�Ƃɂ����I�v�V�������s�g���Ċ����p���邱�Ƃɂ���Ď����m�肵�悤�Ƃ����C���Z���e�B�u�������B�X�g�b�N�E�I�v�V�����͊������㏸���Ă��邤���͒N�ɂ��ɂ݂������炳�Ȃ��A�D�ꂽ�V�X�e���ł��邪�A��U�������������n�߂�Ǝ��Ԃ��̂��Ȃ������������炷�\���̂���V�X�e���ł������̂ł���B
�X�g�b�N�E�I�v�V���������p�����o�c���j�Œm���Ă����G���������A�č��̊i���s��̒���ɂ��A���ɔn�r�������A���ǔj�]�ɒǂ����܂ꂽ�B
�X�g�b�N�E�I�v�V�����́A���z�I�ɂ͉�БS�̂̋Ɛт����f�����t�F�A�ȃV�X�e���̂悤�Ɏv���邪�A�o�c�����Ȃ炢���m�炸�A���[�̎Ј��ɂ́A�����ɗ^����ꂽ�E�������Ȃ��ȊO�ɂ��̑��̋Ɩ��ɌW���`�����X�͏��Ȃ��B�����ɊW�̂Ȃ��Ƃ���ʼn����ꂽ���f�Ŕ���������̐ӔC����炳���̂́A�C���̗ǂ����̂ł͂Ȃ����낤�i�����_�̕ł́A�G�������Ј��̓I�v�V�������s�g���邱�Ƃ͋ւ����Ă��������ł���B�I�v�V�������s�g���Ĕ��蔲����ꂽ�̂́A�ꈬ��̊��������ł������悤�ł���j�B
4.2�ސE���E�ސE�N��
���{�ɂ����ẮA�N�����x�̏ے��Ƃ��ď����̍����̂悤�Ɉ����Ă���ސE���E�ސE�N�����x�ł͂��邪�A���́A���x���̂ɖ�肪�������̂ł͂Ȃ��B
���{�ɂ����đސE�N�����x���������ꂽ�̂́A���A��������x�������Ȍ�ł���Ƃ����B����܂ł́A�ސE���i�ꎞ���j���x����ʓI�ł������B
�����A�ސE���͉i�N�Α����Ă��ꂽ�Ј�������Ĉ��ށi�N�G�����H�j����łɂ́A���ꕕ���i�悳���Ƃ����悤�ȈӖ������Ŏx������Ă����悤�ł���B�]���āA�N�G�������Ȃ������ɏ���Ɏ��߂Ă����悤�Ȑl�Ԃɂ́A���ꕕ�̂��J���͂Ȃ��̂ł���B
���̂悤�ȕ��I�Ȉʒu�Â����Ȃ���Ă����ސE���ɑ��āA�ސE�N�����x�͂�苋�^�̌㕥���I���i�̋������x�ł���B���x�������ȍ~�A��Ƃ����S����|���ւ̉ېŌJ�艄�ׂȂǐŐ���̗D���[�u�����ꂽ�̂ɂ͂킯������B
�u��͑ސE���̌����̊m�ۂƂ����˂炢���������B�����I�ɁA�����Α��̒�N�ސE���������Ă���ƁA���n�͔���Ȋz�ƂȂ邽�߁A��ƂƂ��Ă͌v��I�ɐςݗ��ĂĂ����K�v������B�����ŁA�Ő��K�i�N�����x�����A�|���ɑ���Ő��チ���b�g����Ƃɗ^���邱�ƂŁA�ϗ��Ă𑣂����Ƃ����̂ł���B�Ј��ɂƂ��Ă��A���n�̊m�ۂ͑傫�ȃ����b�g���������B�v
�u������B����w�i���������B���x�������A���{�̎Y�ƊE�͏�ɑ�ʂ̎�����K�v�Ƃ����B�����ŁA�N���̊|�����Ƃ����`�Ŏ������z���グ�A�����ی���Ђ�M����s����ĎY�ƊE�Ɋҗ������A���x�����̎������v���x����Ƃ������̎��삪�x�[�X�ɂ������͔̂ے�ł��Ȃ��B�v�i���� �r��w�l�ރ}�l�W�����g�_�xp201�j
���̂悤�ɂ��čL�����y�����ސE�N�����x�ł��邪�A������o�u������ƂƂ��������ĕϒ��𗈂����Ă��܂����B�܂��A�N�������̉^�p���A�o�u�������ɂ߂Ēᒲ�A������ɂ���Ă͌����ɑ傫���H�����ގ��Ԃ��������B���̈���ŁA�l���\���̍���͔N���x�o��ۉ����Ȃ����傳���Ă������B���ɂ����鐊�ގY�Ƃ̏ꍇ�ɂ͐l���\���̍���͒Ɏ�ŁA�����N��������ێ��ł����A���U����P�[�X�܂ł������B���̍ŏ��̗�Ƃ��āA1994�N�ɓ��{�a�ыƌ����N����������U�����B
�����āA�������2000�N���ȂǂƂ����Ă������ۉ�v��Ɋ�Â�������v�����̓��������߂����������B�����N������͏]��5.5���Ƃ��������\�藘����O��Ƃ��Đv����Ă����B���x�������ɂ͂���ȏ�ɍ����^�p�����������邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ��A���Ƃ̌����N������͕ۗ{���̍����Ȃǂ����������̂ł���B�Ƃ��낪�A���ۉ�v��̓����ɂ���Ă���܂ŕ\�ʉ����Ă��Ȃ������N���ϗ��Č����̕s���i�N�����j����Ƃ̍��Ƃ��Č���邱�ƂɂȂ�B�o�u�������̐��N�ԂŁA�ϗ��ĕs���͖c��ȋ��z�ɂȂ��Ă��܂��Ă����̂ł���B�\�藘���ɂ��Ă�1997�N�x�������������F�߂�ꂽ�B���̏ꍇ�A�\�藘���������������Ă��A�����̋��t���m�肵�Ă���̂ŁA��Ƃ̈�N���̐ϗ����͋t�Ɉ����グ���邱�ƂɂȂ�B���������āA�\�藘��������������ꂽ����Ƃ����Ċ�ƂɂƂ��Ă̖�肪���������̂ł͂Ȃ��B
���̂悤�Ȕw�i����o�Ă����̂����{��401�ik�j�ł���A�ސE�����x�̔p�~�������̂ł���B
4.3�@401�ik�j
�č��̊m�苒�o�^�N���́A�����@�ł�������Γ��@�̑�401�������ɂȂ���āA401�ik�j�v�����ȂǂƌĂ��B�m�苋�t�^�N���i���{�ň�ʓI�Ȍ����N���Ȃǂ͂��ׂĂ��̃^�C�v�j�ł͏����̋��t�z���m�肵�Ă���iDefined Benefit�j�̂ɑ��āA�m�苒�o�^�N���ł͋��o�z�������m�肵�Ă���iDefined Contribution�j�A�����̋��t�z�͋��o���ꂽ���Y�̉^�p�ɂ���Č��܂�B
�č��ɂ����Ă��A���������̓����̌o�܂͓��{�Ɠ�����1970�`1980�N��ɂ����ĔN���^�p����@�I�Ɋׂ������Ƃ����������œ��������Ƃ������Ă������̂ł���B
�������A�����I�Ƃ�������l�C���Ă̂́A1990�N��A�č����D�i�C�ɕ����������ł������̂́A���R�ł͂Ȃ��B�č�401�ik�j�ɂ����ẮA�����ΏۂɊ������g�ݍ��܂�Ă��铊���M���Ȃǂɑ����̎��������������B�č������͂���10�N�قǃu�[���ɂ������̂ł��邩��A�^�p���т��ǂ������͓̂��R�ł���B
�}1�@
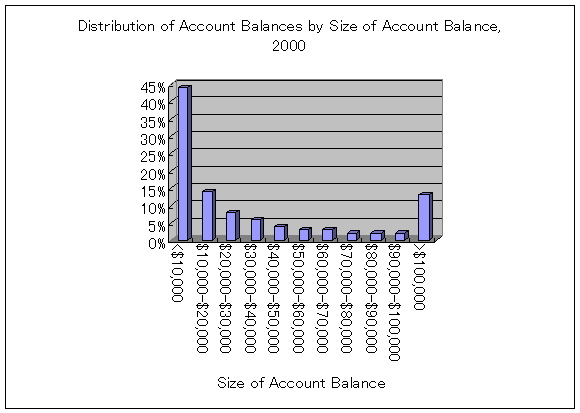 Source: Tabulations from EBRI/ICI Participant-Directed Retirement Plan Data
Collection Project.
Source: Tabulations from EBRI/ICI Participant-Directed Retirement Plan Data
Collection Project.
Note: Percentages may not add to 100 percent due to rounding.
�i�o�T EBRI �g401(k) Plan Asset Allocation, Account Balance, and Loan Activity in 2000�h�j
EBRI��Employee Benefit Research Institute �i�č��ސE���t�����������j�̗�
�Ƃ���ŁA���{��401�ik�j�����c�_�ł́A�č��ł�401�ik�j�����ɍL���p�����Ă��邩�̂悤�ȋc�_����������ꂽ���i�����҂͑S�̂Ŗ�42�S���l�i2000�N���AEBRI�j�A�N�x�͈قȂ邪�A2002�N1�������݂̘J���l����133.5�S���l�A Bureau of Labor Statistics�j�A�}1������킩��Ƃ���A��l������̎c���͈ӊO�Ə��Ȃ��B2000�N�x�ɂ����镽�ώc����49,024�h���ł���i�o�TEBRI���O�j�B�בփ��[�g�ɂ���邪�A500�`600���~�ł���B�������A�}1������ǂݎ���悤�ɁA���ϒl���ӊO�ƍ����̂́A�ꕔ�i�c��100,000�h���ȏ�A�S�̂�13���j�ɋɂ߂Ďc���̑����W�c�����݂��邩��ł���B���ώc����49,024�h���ɂ��邽�߂ɂ́A���̏W�c�̕��ώc���͖�235,000�h���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�i���̑��̏W�c�ɂ��Ă͏���Ɖ����̐��l�̒��Ԃ�X�I�ɕ��ώc���Ƃ����ꍇ�B�Ⴆ��10,000�h������20,000�h���̏W�c�ł����15,000�h���j�B���̃f�[�^��2000�N�x�̐��l�ł��邩��A�č���IT�o�u�����͂����Ă��Ȃ�����ł���A���̉��b�������ނ������X�����������̂ł��낤�B
���������āA401�ik�j�S�����҂̎c���̒��Ԓl�͂�������13,493�h���ł���i�o�TEBRI���O�j�B401�ik�j�̉����҂̔�����13,493�h���ȉ��̎c�����������Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
���{�ł́A401�ik�j�����\�ł��邩�̂悤�Ɍ��`���ꂽ���A�č��ł����������Ƃł́A�]������̊m�苋�t�^�N�����c���Ȃ��炻�̏�悹�Ƃ���401�ik�j�������Ƃ��낪�����A�N���V�X�e������ƂɂƂ��ĕ��S�̏��Ȃ�401�ik�j��{�ɂ��Ă��܂����̂́A�V���R���o���[��IT��Ƃɑ�\�����V��������Ƃ����������̂ł���B
�]���̊m�苋�t�^�N�����c���������͓��R�A���̂悤�ȔN���V�X�e���̕����]�ƈ��ɑ��郁���b�g���傫���ƍl����ꂽ����ł���B���������A�č��ɂ����Ă͊�ƔN�������L���Ă���̂͑��Ƃ����ł���A��ƔN���V�X�e�������L���Ă��邩�炱���i�]�ƈ��ɑ��đ傫�ȕ�V�������j�����̗D�G�Ȑl�ނ��m�ۂł����̂ł���B
���������A�^�p�ɂ̓��X�N���t���܂Ƃ��B�]���^�̊m�苋�t�^�N���V�X�e���́A���̃��X�N����Ƃ��w�����Ă���Ă����̂ł���B�Z���I�ɂ͂Ƃ������A�N���V�X�e�����]�ƈ��ɑ��钷���I�ȃx�l�t�B�b�g�ł��邱�Ƃ��l����A�m�苋�t�^�N�����ÏL���ĕϊv���K�v�ȃV�X�e���ł���ƌ��ߕt���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ��킩��B
5.�����I��V�̌n����̒E�p
�O�q������V�͂��ׂċ��K�i�X�g�b�N�E�I�v�V���������K�I�x�l�t�B�b�g�̑�ւƍl������j�ɂ���Ďx��������̂ł���B
�Ƃ��낪�A�ŋ߂ł͊�ƋƐт�l�̋Ɛт��O�q�̃o�����X�E�X�R�A�J�[�h�ɂ݂�悤�ɁA�����I�w�W��ӓ|�̕]�����狗����u�����Ƃ��Ă���B
�Ƃ��낪�A��V���x�����i�ɂȂ�ƁA�S�Ă������I��i�ɂȂ��Ă��܂��̂͂Ȃ��ł��낤���B�m���ɁA���K�Ŏx�����A�]�ƈ��͂��̕�V�������悤�ɂ��g������̂ł��邩��A���R�x�������A�D�ꂽ�V�X�e���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A��V�����ׂč����I��i�Ŏx����Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ���A�O�q�̏،���Ђ̂悤�Ɏ��Y�Ǘ��^�c�ƕ��j��ł��o���Ă��Ȃ�������w�W���ቺ����Ƃ����ɕ��j�]���𔗂��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
��Ƃ͏]�ƈ��ɑ��ċ��K�I�ȃx�l�t�B�b�g�������^�ł��Ȃ��̂ł��낤���B�����A���K�ȊO�̃x�l�t�B�b�g�ɂ���ď]�ƈ��ɕ邱�Ƃ��ł���̂ł���A���܂��܂ȍD�܂������ʂ����҂ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�ȉ��ɂ����āA�]����V�Ƃ͑������Ă͂��Ȃ��������̂́A������I��V���l�����ŎQ�l�ɂȂ�Ǝv����J�t�F�e���A�v�����ƃ��[�N�V�F�A�����O����グ��B
5.1�J�t�F�e���A�v����
�J�t�F�e���A�v�����Ƃ́A��ʓI�ɂ͑I���^�̕����������x���w���Ă���B�]���́A�ǂ̏]�ƈ��ɑ��Ă��ꗥ�̕����������x�i���N�ی��A�N���A���̑��j���K�������̂ɑ��āA�J�t�F�e���A�Ŏ����̍D���Ȃ��̂����g���[�Ɏ���Ă����悤�ɁA��Ђ̗p�ӂ��镟���������j���[���猈�܂����|�C���g���͈͓̔��őI���ł��邱�Ƃ���A���̂悤�Ȗ��̂�����ꂽ�B���{�ł�401�ik�j�̓����ƂƂ��������ĕp�ɂɂ��̖����o�ꂷ�邱�Ƃ������̂Ŗ��ڂȊW�����邩�̂悤�Ɏv���Ă��邪�A�{���͕ʂ̃V�X�e���ł���B
�J�t�F�e���A�v������1970�N��̏I��育��č��œo�ꂵ���Ƃ���Ă���B���{�̂悤�ɏ]�ƈ��S���������ł�����I�Ȉ�Õی����x�̂Ȃ��č��ɂ����ẮA��Ƃɂ�����]�ƈ��ɑ��������������̈�Ƃ��Ĉ�Õی�����Ƃ����S����Ⴊ���������B�������A���R�f�Ð��̕č��ɂ����āA��Ô�͔��ɍ����A��Õی�����ƌo�c���������܂łɂȂ��Ă��܂����B
�����ŁA���������R�X�g���������邱�Ƃ��ő�̖ړI�Ƃ��ē������ꂽ�̂��J�t�F�e���A�v�����ł���B�J�t�F�e���A�v�����ɂ́A�N�ԍő嗘�p�|�C���g�����߂��Ă���A�S�̂Ƃ��ăR�X�g�̍팸���}��邩��ł���B�������A���ꂾ���ł͏]�ƈ��ɑ������I�ȋ��t�팸�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����₤�Ӗ��ŏ]�ƈ��̗v���ɉ����������������j���[��I�ׂ�悤�ɂ������̂ł���B
���{�ɂ����Ă��A1995�N�̃x�l�b�Z�R�[�|���[�V�����ȗ��l�X�ȉ�ЂŃJ�t�F�e���A�v��������������Ă���B�č��ɂ����铱������L�̂悤�ɃR�X�g�팸��ړI�Ƃ��Ă��̂ł���̂ɑ��āA���l���������C�t�E�X�^�C���ɑ��Ă��K����������������������ړI�œ�������Ă���̂������ł���B
�]���āA���{�ɂ����ẮA���ی��⏕�A�l�N���⏕�A�_��������g�p�⏕�A�x�r�[�V�b�^�[��p�⏕�Ƃ������]���̕��������V�X�e������͊O����p�ɑ���⏕��A����⏕�A���i�擾�⏕�Ƃ��������Ȍ[���^�̃��j���[����������Ă��邱�Ƃ������B
�������A�J�t�F�e���A�v�����͈�ʓI�ɂ͕��������V�X�e���ł���B�N���v�����̈ꕔ�Ɋ�Ƒ������т̂������]�ƈ��ɑ��ē��ʂ̏�悹������Ƃ��������Ƃ͂�����̂́A��{�I�ɂ͊e�]�ƈ��Ɋ��蓖�Ă���|�C���g���͓���ł���B
�������A�J�t�F�e���A�v������ʂ��ď]�ƈ��ɒ����̂́A�P�Ȃ�����I���t�i�P���ɂ������K�Ŏx�����鋋���j�Ƃ͈قȂ����A�]�ƈ��̃N�I���e�B�[�E�I�u�E���C�t�����߂�悤�Ȃ��̂������܂܂�Ă���B
���n�I�Љ�ɂ����ẮA�P���ɑ��ЂƂ̋����ɏ��Ă悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��낤�B�J�t�F�e���A�v������ʂ��Ď��������]�ƈ��̃N�I���e�B�[�E�I�u�E���C�t�����߂�Ƃ����p�����A�]�ƈ��ւ̖{���I���t�ł����V�E���^�̎x�����ɐ������Ȃ����̂ł��낤���B
5.2���[�N�V�F�A�����O
���[�N�V�F�A�����O�Ƃ́A���`�ǂ���A�d�����������i�V�F�A�j���Ƃɂ���āA�]�ƈ��ЂƂ蓖��̘J�����Ԃ����炷�ւ��ɁA�S�̂Ƃ��Ă̌ٗp���ێ�������A���₵���肷��d�g�݂̂��Ƃł���B1970�N���2�x�̃I�C���V���b�N���_�@�Ƃ��ă��[���b�p�Ŏn�܂����Ƃ����Ă���B
���[���b�p�ł��A���ɂ��A���邢�͍̗p������Ƃɂ��l�X�Ȍ`�Ԃ̃��[�N�V�F�A�����O�����{����Ă���B��Ȃ��̂Ƃ��ẮA�@�ٗp�ێ��^�i�ً}���^�j�A�A�ٗp�ێ��^�i�����N��^�j�A�B�ٗp�n�o�^�A�C���l�A�ƑΉ��^��4���������Ă���i�����J���ȁu���[�N�V�F�A�����O�Ɋւ��钲���������v�j�B
�@�ٗp�ێ��^�i�ً}���^�j�Ƃ́A�Ⴆ����H��ɂ����鑀�Ɨ����ቺ�����ꍇ�A�{���ł���ΐl���팸������Ƃ�����A�l���팸�̑ւ��ɘJ���҂ЂƂ蓖����̘J�����Ԃ�Z�k���邱�Ƃɂ���đΉ����悤�Ƃ������̂ł���B
�A�ٗp�ێ��^�i�����N��^�j�Ƃ́A�����N�w�̌ٗp�ێ��̂��߁A�����N�w�̏]�ƈ���ΏۂɘJ�����Ԃ�Z�k���A�ٗp���m�ۂ�����̂ł���B
�B�ٗp�n�o�^�Ƃ́A���Ǝ҂ɏA�Ƌ@���^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���܂��͊�ƒP�ʂŘJ�����Ԃ�Z�k���邱�Ƃł���B
�h�C�c�ł�1995�N�ɋ����Y�Ƃł͏T35���Ԑ����������ꂽ�B�t�����X�ł�2000�N1�����]�ƈ���20�l���邷�ׂĂ̊�ƂɏT35���Ԑ��������ꂽ�B�܂��A�ʊ�Ƃ̗�Ƃ��āA�t�H���N�X���[�Q���ł�1994�N���T�x3���ɂ��28.8���ԘJ���������B�J�����Ԃ�20�����Z�k���ꂽ����A�N����10�����������Ă���Ƃ����B�i2002�N2��12���t�����{�o�ϐV���u���[�N�V�F�A�����O�v�j
�C���l�A�ƑΉ��^�Ƃ́A�I�����_�ɂ����郏�[�N�V�F�A�����O�̑̌n�����f���ɂ��Ă���B����J�����l�E��������i�����d�������Ă���Ȃ�A�����������j����{�Ƃ��āA��Ύ҂ƃp�[�g�^�C���]�ƈ��̒����i�����Ȃ����A�ϋɓI�Ƀp�[�g�^�C���ւ̃V�t�g�𐄐i���Ă���B����ɂ��A��Ƃ͎��v�̑����ɂ��J���͂̉ߕs�����p�[�g�^�C���]�ƈ��̑����Œ��߂ł������A�]�ƈ������A���тƂ��Ă݂�A�傽�鐶�v�҂̒������������Ă��A�p�[�g�^�C���]�Ǝ҂̎����̌���ɂ��A���ю�����������x�ێ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ�����̂ł���B
�ȏ�̂悤�ɁA���[�N�V�F�A�����O�Ƃ����������t���g���Ă���ꍇ�ł��A���ɂ���āA���邢�͓K�p�Ǝ�E��Ƃɂ���Ă��܂��܂ȈӖ����������邱�Ƃɂ́A�\�����ӂ��K�v������Ǝv����B
�������Ȃ���A�]���̂悤�ɁA�����Ȃ�ł������𑝂₳�Ȃ��Ă��͂����Ȃ��A�Ƃ����p���ɕω��������邱�Ƃ́A�����ł��낤�B���݂̐�i���ɂ����ẮA������x�̎d�������Ă���A���Ȃ��Ƃ��������̂����������A�Ƃ����悤�Ȏ��Ԃ͂Ȃ��Ȃ����Ƃ�������B�����āA������x�l�ԓI�Ȑ������ł���̂ł���A�d������ł͂Ȃ��ꏊ�Ŏ��Ȃ̔\�͂��������Ǝv���Ă���l�Ԃ͑����̂ł͂Ȃ����낤���B
���݂̓��{�Ń��[�N�V�F�A�����O���b��ɂȂ��Ă���̂́A���݂̕s���̒��ŁA�]��ɂ��]���̈������X�g���Ƃ������̂��ƍs���Ă�����ɑւ��ٗp������i�Ƃ��Ăł���B�������A���[�N�V�F�A�����O�́A���n�^�Љ�ɋ��߂��Ă���l�ނ��m�ۂ����ŁA�d�v�ȃt�@�N�^�[�ɂȂ�̂ł���B
6.������I�ȕ�V�Ƃ�
�O�q�̂悤�ɁA���ݕ�V�Ƃ��čl�����Ă�����̂́A�قƂ�ǂ������I�ȁi���K�I�j��V�ł���B�������A��L�J�t�F�e���A�v�����ƃ��[�N�V�F�A�����O�̍l��������́A������I��V�Ƃ��ď]�ƈ��ɑ��Ēł���ł��낤���ڂ������яオ���Ă���B
6.1��V�Ƃ��ẴJ�t�F�e���A�v����
�܂��A�J�t�F�e���A�v��������́A�]�ƈ��̌l�Ƃ��Ă̎��������コ���邽�߂̋���x������������B
�J�t�F�e���A�v�����̏]�ƈ��ЂƂ蓖��̋��z��10���~���x�ƈӊO�ɂ����Ȃ��B�x�l�b�Z�R�[�|���[�V�����̗�ł́A�u�]�ƈ�1�l����̔N�ԗ��p���x��92�|�C���g�B1�|�C���g��1000�~�ɑ�������̂ŁA���z�Ɋ��Z�����1�l����9��2000�~�ɂȂ�B���̋��z�́A�J�t�F�e���A�v���������ȑO�ɂ������Ă����@��O�̕�����������x�[�X�ɂ��Č��肳�ꂽ�v�i�����@�r��w�J�t�F�e���A�v�����xp123�j�����ł���B���{�ɂ�����J�t�F�e���A�v�����́A�]���^�̕��������i���N�ی��A�Љ�ۏ�j�Ȃǂ�S�ʓI�Ɍ����肷����̂ł͂Ȃ��A���̕s���i���z�I�ȕs������ł͂Ȃ��A���j���[�Ȃǎ��I�ȕs�����܂ށj���U���邽�߂̂��̂ł���ƈʒu�Â����Ă��邩��ł���B�]���āA���z�I�ɂ͑S�]�ƈ��ꗥ�ŌJ��z���������Ȃ��Ƃ��������̂��قƂ�ǂł���i���Ȃ݂Ƀx�l�b�Z�R�[�|���[�V�����ł͌J�z����F�߂Ă���j�B
�������A������V�I�Ȉʒu�Â��ɕύX����̂ł���A���z�I�ɂ���葽���̋��z��ł���ł��낤�B�܂��A�J�z����F�߂邱�Ƃɂ���āA��荂�x�Ŏ��Ԃ��|��悤�Ȏ��i�Ƀ`�������W���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��낤�B
�]���A��Ƃ��]�ƈ��ɒ��鋳��v���O�����́A��Ƃ̕K�v���Ƀ_�C���N�g�Ɍ��т��Ă���ꍇ�����������B��Ƒ������K�I�ȕ��S�͂�����ɁA���̐��ʂ͂�������ƋƖ���ʂ��Ĕ������Ăق����Ƃ����A����ΐ�s�����ł���B�]���āA���̃J���L�����������d�����ŁA���R�ɑI�Ԃ��Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ������B��V�ł�����̎g�r������������Ƃ��F�������邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��̂ł��邩��A��V�I�Ȑ��i�������Ă���Ƃ͌����ɂ����ł��낤�B
�܂��A���т�\�͂ɑ��ċ��t�����̂��K���ł���Ƃ��v���Ȃ����A�o�Y�E�玙���邢�͉��ɑ��鋋�t���A�傫����グ���Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B
��ƂɂƂ��āA�ƒ됶���Ɏ��Ԃ�����邱�Ƃ͐��Y�����ɑ���P�Ȃ�T�{�^�[�W���ł���A�]�ƈ��͑S�g�S����X���Ċ�Ƃɐs���ׂ��ł���Ƃł���������̑ԓx�����{�ł͖ڗ����A��Ƃ��Љ�I���݂ł���B�����āA���ݎЉ�͋��n��������B�����ł��\���̏オ��Ȃ����̂����X�Ƃ��тɂ��Ă����A�Ɛт�����Nj����邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�t�ɁA�o�Y��玙�Ɍ��炸�A���n�I�Ȕ��z�Ɋ�Â������t���]�ƈ��ɑ��čs���Ă����Ƃ́A�����P�ɋ��K�I�ȃx�l�t�B�b�g������������A�D�G�Ȑl�ނ��m�ۂ��A�q���~�߂Ă����m���͍����Ȃ�͓̂��R�ł͂Ȃ����B
������ӂ܂ʼnc�Ƃɖ������Ă���]�ƈ����A�Љ�ɂ����邳�܂��܂Ȋ�����ʂ��Čo����ς]�ƈ��̕����A���n�����s��ɂ�����ڋq�����x�����߂�悤�Ȕ��z�E���Ăɗ͂�����Ǝv����B
���݂͏]�ƈ����������̈�Ƃ��đ������Ă���J�t�F�e���A�v�����ł��邪�A��Ƃ̐l���헪�ɓK������`�Ŋ��p���Ă������Ƃ��]�܂��B
6.2��V�Ƃ��Ẵ��[�N�V�F�A�����O
��L��V�Ƃ��ẴJ�t�F�e���A�v�����Ƃ��傫���W����Ƃ���ł��邪�A���[�N�V�F�A�����O�̍l��������́A���Ԃƕ�V�Ɋւ���l�@��������B
���݂̓��{�ɂ����ẮA�ǂ������������������Ƃł��邩�̂悤�ȍ��o���������Ă��邱�Ƃ���`���āA���[�N�V�F�A�����O��ϋɓI�Ɏ�荞��ł������Ƃ������́A�s���̂Ȃ��A�ꂵ����ɍ̗p���Ă���悤�ɂ��v����B�Ђǂ��ꍇ�ɂ́A��Ƒ��̒����}����̈�тƂ��č̗p�����ꍇ������悤�ł���B
�������Ȃ���A��L�J�t�F�e���A�v�����ɑg�ݍ��܂�Ă��鎩�Ȍ[���v���O�����Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�ʂ̊��p���@�������Ă���B
���^�̑ւ��Ɏ��Ԃ��x�����Ă���ƍl����̂ł���B
���݂ł́A�ǂ��̊�Ƃł����Ȍ[�������サ�Ă���Ǝv���B�������A���Ȍ[���ɕK�v�Ƃ���鎑�����U���Ă���ꍇ�ł��A���Ԃ܂ł͖ʓ|�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���͂�邩�炠�Ƃ͏���ɂ��A�Ƃ����킯�ł���B���܂��ɓ��{��Ƃł͈ˑR�Ƃ��ĒP�ɒ�����Ђɂ��邾���̒����ԘJ�����͂т����Ă���B���Ȍ[���Ɏ��Ԃ��������Ǝv���Ă��A��قǂ̌��ӂ����Ă�����Ȃ��ƍ��܂��Ă��܂����Ƃ́A�Љ�l���o���������Ȃ�N�ł��o��������̂ł͂Ȃ����낤���B
���݁A���{�o�ς̒�����A�����̊�Ƃ��J�����Ԃ̒Z�k�A���X�g���i�Ƃ������̂��Ƃ̎��j���������Ă���B���̒��ŁA���[�N�V�F�A�����O��������Ă����Ƃ������B�Ƃ���ŁA��Ƃ͏]�ƈ��̘J�����Ԃ�Z�k�����Ƃ��A�]�ƈ������̎��Ԃʼn������邱�Ƃ�����Ă���̂��낤���B�P�ɒ��Q���Ă��邱�Ƃ�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤�B�A���o�C�g��F�߂Ă����Ƃ܂ł���i����2�Q�Ɓj�B�������A���[�N�V�F�A�����O�ɂ��ƌv�S�̂̎����s������Ȃ��Ă͐������ł��Ȃ��̂ł�����̂悤�Ȏ{����Ӗ��̂��邱�Ƃł��낤�B�������A���ђ��̘J���\�Ȑl�Ԃ����ׂĒ�����ӂ܂œ����Ȃ��Ă͐������ł��Ȃ��A�Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̏ꍇ�A�]�������Ԃ����Ȍ[���ɓ��ĂĂ��Ă���邱�Ƃ́A��ƂɂƂ��Ă��A�]�ƈ��ɂƂ��Ă��A�Ӌ`�̂��邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
���l�̂��Ƃ́A�ʂɃ��[�N�V�F�A�����O���s���Ă��Ȃ��ꍇ�ł��̗p���邱�Ƃ��ł���ł��낤�B������x�̘J�����Ԃ����i��V���A�����Č��炷�j���Ƃƈ��������ɘJ�����Ԃ�Z������A�ȂǂƂ������Ƃ��\�ł��낤�B���Ƃ����w�S�ɔR���Ă����ɂ��Ă��A���̂悤�Ȃ��Ƃ͌��݂ł͂����炭�A���o�C�g�̂悤�ȘJ�������łȂ��Ă͎����ł��Ȃ��ł��낤�B
�܂��A���݂ł͒����x�E��������Ƃ���ANGO�Ȃǂ̎Љ�v�������ɎQ���������Ǝv���Ă��A�Љ�l�����ۂɒ����ԎQ�����邱�Ƃ͓���B�d���Ȃ���Ƃ�ސE���Ă���ꍇ�������悤�ł���B
���̂悤�ȍv���������������Ǝv���Ă���l�ԂɂƂ��ĕK�v�Ȃ̂́A�������I�����ꍇ�ɋA���Ă��邱�Ƃ��ł���E�ꂪ�������ł悢�̂ł͂Ȃ����낤���B�ʂɊ������^���Ă���A�A���Ă����łɂ͂�荂���|�X�g����Ă���A�ȂǂƂ������Ƃ����߂Ă���̂ł͂Ȃ����낤�B�C���I����ɋA���Ă�����|�X�g��p�ӂ��邱�Ƃ����A���̂悤�Ȋ����ɒ��킵�悤�Ƃ����l�ނ͐���������Ǝv���̂����������ł��낤���B
���ꂾ���ł͂Ȃ��ANGO�̂悤�ȎЉ�I�v�������Ɋ�^�����l�ނ���Ƃɑ��݂���Ƃ������Ƃ́A��Ƃ̎Љ�I���]�����߂�������A��߂邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�������A���݂̐��n�����s��Ōڋq�ƑΛ�����l�ނ����߂�Ƃ��A�Љ�v�����������H���Ă����l�ނ͑�ϗL�p�ł���Ǝv���̂����������ł��낤���B
���e�I�ɂ̓I�[�o�[���b�v���邱�Ƃ������J�t�F�e���A�v�����ƃ��[�N�V�F�A�����O�̍l�����̊��p�ł��邪�A���ʂ��邱�Ƃ́A�]���͏]�ƈ��ɑ���C���Z���e�B�u�Ƃ͍l�����Ȃ��������̂��A��Ƃ̐헪�ɍ��킹���`�Ŋ��p����A�]�ƈ��̃C���Z���e�B�u�������o����ő傫�ȕ���ƂȂ�Ƃ������Ƃł���B
����ɁA���݂̐��n�����s���Ƃ���l�ނ���Ă�ɂ́A���܂Ŋ�Ƃ����ʂł���Ƃ��đł��̂ĂĂ����悤�Ȕ�����I�ȉ��l�ς�D�悹����Ȃ��B�����ł���Ƃ���A�]�ƈ��ɑ����V�̎x�������A�C���Z���e�B�u�̗^���������̂��ƕω����Ă�������Ȃ��̂ł���B���̏ꍇ�ɁA��L�̂悤�Ȕ�����I�ȁi���K�ł͂Ȃ��j��V���\���ɍl���ɒl������̂ɂȂ�̂ł���B
7.���_
���ݓ��{��Ƃ����ʂ��Ă���s��́A��ϐ��n�����s��ł���B����ɕs���Ƃ����v�f�������A����҂̊�Ƃɑ���ڂ͑�ό��������̂ɂȂ��Ă���B�P�Ɉ����Ƃ��������ł͏���҂͐U������Ȃ��B�����A�i�����ǂ��A�Ȃ����̔���A�t�^�[�T�[�r�X�ɂ�����]�ƈ��̐ڋq�ԓx�܂ōō��̂��̂����߂��Ă���B��Ƃ͏���҂̗v���ɖؖڍׂ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�悲����A�e��Ђɑ����Ďq��Ђł��s�ˎ������o�������H�i���A�������o����قǂȂ����U�ɒǂ����܂�Ă��܂����i����4�Q�Ɓj�B�Љ�͋��n�����Ă���̂ł���B��Ƃ̓s���������l���Ă���悢����ł͂Ȃ��Ȃ����̂ł���B
���̂悤�Ȋ�ƂɂƂ��āA�]���̂悤�ɁA�����I�w�W�ɂ̂ݗ����Čo�c���s���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�����œo�ꂵ�Ă����̂��A�o�����X�X�R�A�J�[�h�̂悤�ɁA�����w�W�ȊO�̎w�W������荞��ł����l�����ɂ���Ċ�ƋƐт𑽊p�I�ɑ�����悤�ɂȂ��Ă����B
��Ƃɋ��߂���l�ނɂ��������Ƃ�������B�}�j���A�������Ȃ��Ă��������ŋ����ꂽ����Ƃ͈قȂ�A�ڋq�̂킪�܂܂Ȓ����ɉ����邽�߂ɑn�ӍH�v���Â炷���Ƃ��v������Ă���B�����ɂ̓}�j���A�����Ȃ���ΐ����Ȃ��̂ł���B
���̂悤�Ȑl�ނ�]������ɂ́A���R�]���̂悤�ɔ����{�ŕ]������ȂǂƂ������Ƃ͋�����Ȃ��͂��ł���B�������A���݂ł����ю�`�̖��̂��ƂɁA���ǂ͍����I�w�W�����̉��ɂ��܂��ėD�悳��Ă���ꍇ������B
���ꂾ���łȂ��A�Ɛт�]������A����Ɍ�������V���x������̂ł��邪�A���̎�i�͂قƂ�ǂ������I��i�i���K�j�ɂ���Ďx�����Ă���B
��ƋƐт�]������ɂ��A�]�ƈ��̋Ɛт�]������ɂ������I�w�W����ł͂Ȃ����̎w�W��������Ă���ɂ�������炸��V���x�����i�ɂȂ�ƍ����I��i�����p���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��낤���B����ł́A�u���Ǒ�Ȃ̂͋����v�ƍ������Ă���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
��Ƃ������I�C���Z���e�B�u�Ƃ��Ďx�����Ă���͂��̃X�g�b�N�E�I�v�V�������A���ۂɂ̓L���b�V���t���[���m�ۂ��邽�߂̎�i�ɉ߂��Ȃ��������A�]�ƈ��̂��߂ɗp�ӂ����ސE���E�N���V�X�e�����A���ǂ͊�Ƃ̍������e�����P���邽�߂�401�ik�j�̂悤�ȃV�X�e���ɕύX����Ă��܂����B�������A���݂̐��n�s��ł͊�Ƃ͌ڋq�̃��C�����e�B�[�����߂悤�Ƃ��Ă���B���̏ꍇ���R�]�ƈ��̃��C�����e�B�[�����߂���B
�����Ŏ����{�e�Œ�Ă���̂��A������I��@��p������V�̎x���ł���B
�]�ƈ���]������ꍇ�ɁA������I�Ȏw�W��p����̂ł���A��V���x�����ꍇ�ɂ�������I�Ȏ�i��p�����ق����A��Ɨ��O�����悭�]�ƈ��ɓ`���邱�Ƃ��ł��A�Ȃ����]�ƈ��ɂƂ��Ă������b�g�̂���V�X�e���Ƃ��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł���B
������I�ȕ�V���l����ۂɎQ�l�ɂȂ�̂��A�]���͕��������V�X�e���̈�Ƃ��đ������Ă����J�t�F�e���A�v������[�N�V�F�A�����O�̍l�����ł���B�{�e�ł́A�J�t�F�e���A�v������[�N�V�F�A�����O�̍l�������g����������I�ȕ�V����������B������I�ȕ�V�Ɋւ��ẮA����ȊO�ɂ������̎g����������ł��낤���A�܂��A�����ɂ͐Ő���̖��Ȃlj������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������̖����܂�ł��邱�Ƃ������ł���B����ł��A����������I��V�́A�]���̍����I�i���K�I�j��V�ł͎���������Ȃ������]�ƈ��̃N�I���e�B�[�E�I�u�E���C�t�̌���Ɏ�������̂ł���Ǝv���B
�l�ނƂ������t���A�����ꌗ�ł͐l�u�ˁv�Ə����悤�ł���i�C���^�[�l�b�g�Ől�˂ŃT�[�`��������ƒ�����n�̃w�b�h�n���e�B���O��Ђ�l�ˁi�l�ށj��W�炵���z�[���y�[�W����������o�Ă���j�B��ƂɂƂ��Đl�ނƂ́A�g���̂Ă��ł��A������ł���[���������ޗ��ł͂Ȃ��A�M�d�Ȍo�c�����ł��邱�Ƃ��悭�����Ă���B
�u��ƌo�c�ɂ����āA�l�̖��͍ł��d�v�ȉۑ�ł���B��Ƃ��Љ�I�ȑ��݂Ƃ��ĔF�߂���̂́A�l�̓��������邩��ł���B�l�̓����͂ǂ��ł���������A�������������̌����݂̂����߂����Ƃ������ƉƂ́A���ƉƂ���߂����������Ǝ��͎v���B���Ƃ��s���ȏ�A�Ј��̓����������ĎЉ�ɍv��������̂łȂ���A��Ƃ��Љ�I�ɑ��݂���Ӗ����Ȃ��Ǝv���̂ł���B�v�i���q�@���j�w�o�c�w�xp141�j�����ł���B
���{��Ƃ͍\���I�ȕs���ɋꂵ��ł���B�����̊�Ƃ����X�g���̈��z�Ɋׂ��Ă���B�܂��A�l�������鏔���x�́A���łɃA�����J�ɂ����Ė�肪�I�悵�Ă��܂�����@��������邽�߂̖@���x������Ɛ������ꂽ�ɂ���B����x�A��ƂƏ]�ƈ��̊W���������A���S�Ȕ��W��������x�Ƃ���ǂ���i�Ƃ��Ĕ�����I�ȕ�V�̊��p���肢�������̂ł���B
�����P
�u�]�ƈ������Ȃ��v�͌���@�x�m�ʂ̕��В����ߖ�
�@�x�m�ʂ̏H�����V�В����o�ώ��̃C���^�r���[�L���ŁA�Ɛт̈����́u�]�ƈ��������Ȃ����炢���Ȃ��v�ȂǂƏ]�ƈ��ɐӔC�]�ł��锭�����������Ƃɂ��āA���J�앛�В��͂Q�S���u�r�W�l�X�͌o�c�҂��ӔC���Ƃ���̂��B�i�H���В��́j�������锭���������v�Əq�ׁA�L���͐^�ӂ��`����Ă��Ȃ������Ƃ̎ߖ��������B���Ԍ��Z�̔��\��Ŏ���ɓ������B
�@�H���В��͍������s���ꂽ�u�T�����m�o�ρv�̋L���ŋƐш����̐ӔC�ɂ��Ď��₳��A�u����ɑ��Ă͂�����a����^�c���Ă���Ƃ����ӔC�����邪�A�]�ƈ��ɑ��ĐӔC�͂Ȃ��B���ƌ����āi�В��͏]�ƈ��Ɂj���߂���B�o�c�Ƃ͂����������̂��v�ȂǂƔ����B�ꕔ�̏T��������Ȃǔg����ĂB
�͖k�V���10��24�� http://www.kahoku.co.jp/news_s/20011024KIIAEA21610.htm (01/16/2002)
����2�Ǝ���1���ׂ�ƁA�o�c�҂Ƃ��Ă̎����ɍ�������悤�ɂ���������B�������A�o�u�������AIT�o�u�������Č������ɒǂ����܂ꂽ2001�N��IT�Y�ƂƁA1989�N�o�u���̐Ⓒ�ɂ���A�������̖����ł��������{�̋��Z�@�ւƂ̍��͝Ύނ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ł��낤�B���{�̋��Z�@�ւ��^��������̂́A���ꂩ��ł���B
����2�@���������]�ƈ��̃A���o�C�g�n�j�@�����ቺ��Ă�̗�O�[�u��
(�����V��-�S��)
2002�N2��21��(��)22��2��
�@�������쏊�͂Q�P���A�����R�J���̔����̍H��Ō��ƕ���̏]�ƈ���Q�O�O�O�l��ΏۂɁA�A�ƋK�����ւ��Ă���A���o�C�g�Ȃǁu���Ɓv��F�߂Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�h�s�i���Z�p�j�s���ŁA�R�H��͍H��̉ғ����������A��N�P�P������R���܂ł̊��Ԍ���Ń��[�N�V�F�A�����O�����Ă��邪�A�����ቺ���Ă邽�߂̗�O�[�u���Ƃ����B
�@�R�H��́A��錧�̓߉ϐ����{���ƌQ�n�����萻���{���A�R�����̍b�{�����{���B�]���͂S�l�P�g�̂R���Ζ����������A���݂͂P�l�����T�l�ŕ��S���Ă���A���̕��P�l������̘J�����Ԃƒ��������Ȃ��Ȃ��Ă���B�����́u�Ζ��`�Ԃ̕ύX���̂��ً}���I�ȑ[�u�ŁA�S�ГI�ɕ��Ƃ��L����l���͂Ȃ��v�Ƙb���Ă���B�܂��A���ۂɉ��l�����Ƃ��Ă��邩�ɂ��Ă��A�c�����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�h�s�s���ŋƐш����̓d�@���[�J�[�̘J�g�ł���d�@�A���́A���[�N�V�F�A�����O�̓����ɔ����āA���ƋK��̌��������N���Ă���B�S���ɓ����\��̎O�m�d�@�́A�J�g�ԂŏA�ƋK���ŋ֎~���Ă��镛�Ƃ̈����ɂ��ċ��c�𑱂��Ă���B
�m�����V���Q���Q�P���n
( 2002-02-21-22:02 )
�ihttp://news.lycos.co.jp/topics/business/hitachi.html?cat=2&d=21mainichiF0222m048�@02/23/2002�j
����3 ��Ƃ�
�u�c�ƈ��͏����ł����т��グ�邽�߁A���ɂ�ɂ���Ŋ�揑�쐬�ɂƂ肩����A1���ł������㗝�X������Ă���B��x���ɉƂɋA��ƁA�[�H�ǂ��납�w�L��Q�Ԓ��ɒ��ւ��A�����͐Q�Ԓ�����w�L�ɒ��ւ��ďo����B���̌J�Ԃ��ɈႢ�Ȃ��B����ł͎d���ɒǂ����ςȂ��ŁA�l�ԂƂ��Ă̂�Ƃ�����܂�Ȃ��B�l���Ă݂�A�����g���Ⴂ������A���̔w�L�ƐQ�Ԓ��̌J�Ԃ��������B�v
�u���c�Ђ�89�N�i�������N�j2���Ɋ��S�T�x2�������������A���̈���Ŏc�Ǝ��Ԃ͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�v
�u�����������Ԃ܂��A���N�Ɂu��Ƃ�ƖL�����̂����Ɓv����Ɛ헪�̈�Ɍf�����B�v
�u���ϘJ�����Ԃ�Z�k���A���������Ԃ�L���Ɏg���A���Ȍ[���A�Ƒ��Ƃ̑Θb�A�n��ł̕�d�����ɐU������Ăق����B����ɂ���Đ����̒����͖L���ɂȂ�A��Ђ̎d�������x���A�b�v����͂����B�v
�i�㓡 �N�j ���c�ЊC��ی����_� ���{�o�ϐV���u���̗������v2002�N2��19���j
����4���H�i�S�����U�@�U���Ōo�c����
![]()
���Ƃ��x���������߁@�c�Ə��n�ڎw��
�@�����U�������Ōo�c��Ɋׂ��Ă������H�i�͂Q�Q���ߑO�A�Վ����������J���A�o�c�Č���f�O���A�Վ����呍��̌��c���o�ĂS�������߂ǂɉ�Ђ����U���邱�Ƃ����߂��B�H���A�n���E�\�[�Z�[�W�Ȃǂ̎��Ƃ��R�����܂łɏ����k������B���H�i�͎��Ƃ�]�ƈ��̌ٗp�������Ă����c�Ə��n���T���Ƃ��Ă��邪�A�ŏI�I�ɂ͐��Z����錩�ʂ����B���U�ɔ��������z�͂Q�S�O���~�ɒB���邪�A�e��Ђ̐����Ƃ��ő�Q�T�O���~�̋��Z�x�����s���A�����ւ̑���x�����╉�ٍ̕ςɂ��Ă�B����җ���ɂ���ĉ�Ђ����U�ɒǂ����܂��͈̂ٗ�ŁA���O���[�v�͏���҂̐M���Ɍ����āA���������������o�c�𔗂��邱�ƂɂȂ�B
�i2002�N2��22���ǔ��I�����C���A�@http://www.yomiuri.co.jp/gisou/g20020222_40.htm�@�i02/24/2002�j�j
�Q�l����
�A�[�T�[�A���_�[�Z���@�q���[�}���E�L���s�^���E�T�[�r�X���i2000�j�w�l���v�V�}�l�W�����g�x���Y���o��
Carlos Ghosn (2001), Renaissance, �i���� ���q��i2001�j�w���l�b�T���X �Đ��ւ̒����x�_�C�������h�Ёj
Brian Friedman, James A. Hatch and David Walker (1998), DELIVERING ON THE PROMISE, Arthur Andersen LIP �i�~�Á@�S�ǖ�i1999�j�w�q���[�}���E�L���s�^���E�}�l�W�����g�x���Y���o�Łj
����@����i1998�j�w���ꂩ��̐l���]���Ɗ�x���Y���o��
Robert S. Kaplan, David P. Norton, (1992), The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review1992 Jan.-Feb. �iDiamond�n�[�o�[�h�E�r�W�l�X�E���r���[�ҏW����i2001�j�u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�Ƃ͉����v�w�Ɛѕ]���}�l�W�����g�x�i2001�j�_�C�A�����h��pp155�|180�j
Robert
S. Kaplan, David P. Norton, (1993), Putting
the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review1993 Sep.-Oct. �iDiamond�n�[�o�[�h�E�r�W�l�X�E���r���[�ҏW����i2001�j�u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�ɂ���Ɗv�V�v�w�Ɛѕ]���}�l�W�����g�x�i2001�j�_�C�A�����h��pp181�|222�j
Robert S. Kaplan, David P. Norton, (1996), Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review1996 Jan.-Feb. �iDiamond�n�[�o�[�h�E�r�W�l�X�E���r���[�ҏW����i2001�j�u�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�ɂ��헪�I�}�l�W�����g�v�w�Ɛѕ]���}�l�W�����g�x�i2001�j�_�C�A�����h��pp223�|256�j
�����J���ȁu���[�N�V�F�A�����O�Ɋւ��钲���������vhttp://www.jil.go.jp/kisha/stoukatu/20010426_02_st/20010426_02_st.html �i02/13/2002�j
���q�@���j�i1999�j�w�o�c�w�x���oBP�o�ŃZ���^�[
�䉮
����i1993�j�w�g�D�̐����\������Ƃ̖��^�����߂�̂��x
PHP������
�����@�r��i1996�j�w�J�t�F�e���A�v�����x���oBP��
�����@�r��i1998�j�w�l�ރ}�l�W�����g�_�x���m�o�ϐV���
�����@�r��i2001�j�w�g�D�v���x���m�o�ϐV���
Jack Welch, John A. Byrne
(2001), Jack Straight from the Gut,
John F. Warner Books, �i�{�{ ����i2001�j�w�W���b�N�E�E�F���`
�킪�o�c�x���{�o�ϐV���Ёj
���c �M�j�i1998�j�w���̍��̎��s�̖{���x�u�k��
�@