リスク調整後期待収益率およびシナリオ分析手法のプロダクト・ライフサイクルへの応用に関する一考察
![]()
金融界において、従来型の規制資本(Regulatory
Capital)による規制だけではなく、金融機関が独自に算出する経済資本(Economic
Capital、以下「エコノミック・キャピタル」と記述)を使った先進的リスク管理手法が内外の金融機関によって用いられるようになった。
本稿は金融界における新しいリスク管理の考え方を紹介するとともに、そこに見られるリスク調整後期待収益率およびシナリオ分析手法をプロダクト・ライフサイクルへ適用するという一般企業でも応用可能な経営手法のアイデアを示すものであり、実証的データの収集、厳密な数学的解析を基にした論考ではない。
コンプライアンス部門も含まれるオペレーション関係の業務は企業において通常コスト・センターであると理解されている。オペレーション関係の業務に必要とされるコストは人件費以下比較的容易に把握される一方、それによって削減されるリスク量とその金額は把握が極めて困難であるためである。これが経営陣に対してオペレーション関係の施策の実施を要請する場合に大きな障害となってきた。
金融界におけるコンプライアンス・リスクを含むオペレーショナル・リスク、さらに想定外のリスクにまで備えるエコノミック・キャピタルの計量化を含むバーゼルIIの規制に基づくリスクの計量化及びリスクを勘案したエコノミック・キャピタルを経営管理に使うという考え方は、コスト・センターであるとしか認識されていなかったオペレーション部門のパフォーマンス測定に結びつくものであり、さまざまな企業分野においても応用可能であると思われる。また、企業の内部統制を重視する考え方は、SOX法、日本版SOX法の制定などに鑑みても必然と思われる。バーゼルIIそのものは金融界の中でも銀行(投資銀行業務を営む証券会社などにも適用される)のみに適用される規制ではあるが、一般企業でも応用可能な優れたアイデアが含まれていると考える。
バーゼルIIの特徴はリスク管理手法を金融機関側で選択可能にするなど画一的な管理手法を廃し、金融機関に対して内部統制の確立を求めていることが大きな特徴である。従来型の規制資本(Regulatory
Capital)に加え、金融機関が独自に算出するエコノミック・キャピタルの計量化によるリスク管理が求められることになった。エコノミック・キャピタルとはビジネスを営んでいく上において発生する想定内の損失のみならず想定外の損失をもカバーするためのバッファーとして必要とされる資本量である。単純に経費対比の収益を計算するのではなく、リスクを勘案したエコノミック・キャピタルを金融機関内の各ビジネス・ラインに配賦することにより、各ビジネス・ラインが適正な収益を生み出しているかなどの分析が可能になるのである。
本稿においてはエコノミック・キャピタルを勘案した場合の各ビジネスラインにおける収益率として示されるリスク調整後期待収益率およびストレス・テストとして用いられるシナリオ分析手法を導入期―成長期―成熟期―衰退期で表されるプロダクト・ライフサイクルに適用することを提案するものである。このような手法を導入することにより、従来の投入資本対リターンという概念では見落とされていたリスクの存在を図示することが可能となり、より優れた経営管理が可能かつ容易なものになると考える。
第1章
バーゼルII−金融界におけるエコノミック・キャピタルの考え方
1.バーゼルII導入の背景
2.バーゼルII 3本の柱
3.リスク管理ツールとしてのエコノミック・キャピタルの利用
4.
リスク管理ツールとしてのシナリオ分析の利用
5. エコノミック・キャピタルとシナリオ分析の適用とその限界
第2章
リスク調整後期待利益率およびシナリオ分析手法のプロダクト・ライフサイクルへの応用
バーゼルII自体は金融機関(銀行)に対する規制であり、金融機関でも保険会社などには規制が及ばないし、一般的な事業会社にはもちろん適用されない。しかしながら、エコノミック・キャピタルといったリスクを加味した上で企業経営を再検討する、といった方法は一般企業に対しても多くの示唆を与えるものと思われる。以下において企業全体ではなく、経営戦略及びマーケティング戦略理論に用いられるプロダクト・ライフサイクルにエコノミック・キャピタルの観点やシナリオ分析を加味して分析するためのアイデアを紹介する。
1. リスク計量化の手法とエコノミック・キャピタルの視点の一般企業における応用
コンプライアンスを含むオペレーションの実務に携わる際の最も大きな困難は、毎年のように改正・新設される法令にキャッチアップすることではなく、オペレーション業務の評価、特にコスト・パフォーマンス評価である。オペレーションに関連する事業にかかるコストは人件費を始め比較的簡単に入手可能であるが、どのようにリスクが軽減されたかを示すことは難しい。コスト・パフォーマンスは事後に評価することですら困難であるのに、オペレーションに関連する新規事業を立ち上げる際の事前予測はさらに困難であり、特に経営陣に対して事業の正当性を訴える際に有効な指標が存在しないのである。従って業界横並び、といった対応が取られることになる。積極的にオペレーション部門に資金を投入するわけではないから、オペレーション関連部署は単なるコスト・センターとして捉えられがちであった。
昨今も企業における不祥事が相次いで報道されている。不祥事が起こってから問題に対処することも大変重要ではあるが、不祥事が起きないような体制を作ることは内部統制の上からは極めて重要なことである。
米国におけるSOX法や日本版SOX法を通して内部統制に基づくオペレーショナル・リスクの管理強化は一般企業に対しても否応無く要請されているが、営利企業にとっては管理部門を闇雲に強化することは出来ない。当然コストと対比した効果が求められる。バーゼルIIに見られるオペレーショナル・リスクの計量化とその利用方法は一般企業に対しても示唆を与えてくれるものと考える。特にコンプライアンス・リスクを含むオペレーショナル・リスクを計量化し、さらにはその他想定外のリスクにまで対処するためのエコノミック・キャピタルを企業経営に利用する考え方は一般企業にも適用可能であり、コスト対比の効果を計測する上できわめて有効であると考える。
さらに、コンプライアンス・リスク、オペレーショナル・リスクなどについては、各ビジネスライン/製品、あるいは市場の成熟度によって大きく変化する。競合商品もない新種の商品では、市場に投入した後に潜在的リスクが顕在化することもある。逆に成熟した商品であれば、今後顕在化する潜在的リスクは小さく見積もることが可能である。昨今問題になっているサブ・プライム問題なども、問題の根本は信用リスクという金融機関が慣れ親しんだリスクであるにもかかわらず、問題が現在化するまでは誰一人として気づかなかったのである。
このような観点を踏まえた経営管理ツールを提供するため、以下一般的に経営戦略及びマーケティング戦略理論として用いられているプロダクト・ライフサイクルに、ビジネスラインの成熟度に応じて変化するエコノミック・キャピタルを表す指標としてリスク調整後期待利益率を適用、さらにはストレス・テストとして使用可能なシナリオ分析手法を適用してプロダクト・ライフサイクルとしておなじみの図形を変換した新しいプロダクト・ライフサイクルに関するアイデアを提供する。このような手法を導入することにより、従来の投入資本対リターンという概念では見落とされていたリスクの存在を図示することが可能となり、より優れた経営管理が可能かつ容易になるのである。
2. 一般的プロダクト・ライフサイクルと、リスク調整後期待利益率及びシナリオ分析手法を適用した変換
図表2は一般的なプロダクト・ライフサイクルを示したものである。市場に投入された商品は投入後、導入期―成長期―成熟期―衰退期というライフサイクルを辿るとされている。
導入期においては当然売上を期待できないが、成長期においては売上の向上が見込まれる。期間収益が黒字化するのもこの時期である。成熟期において売上は最高になる。成熟期において今まで投下された資本の回収が行われる。そして商品が一般化する、競合商品が競争力をつけるなどの要因により売上は低下、プロダクト・ライフサイクルは衰退期を迎えるというのが標準的とされる商品の標準的ライフサイクルである。
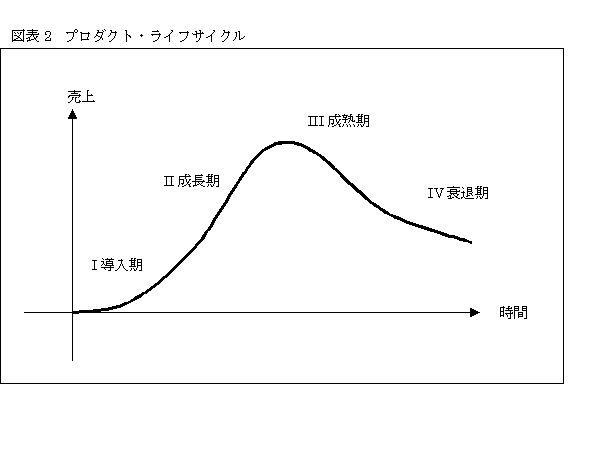
プロダクト・ライフサイクルを別の角度から見たのが図表3である。横軸に時間、縦軸には累積収支を取っている。導入期においては売上が期待できない一方、生産拡張に備えた投資、販売促進のための投資などにより赤字が累積する。成長期において売上は急成長することにより赤字の回収が始まるが累積赤字一掃とまでは行かない。成熟期において本格的な投入資本の回収が行われることになる。そして衰退期においては、商品需要を伸ばすため新たな販売キャンペーンや化粧直しなどが行われるが、効果がなければ今までの黒字を食いつぶす形になる。売上が減少していく場合、回収率も悪化、商品寿命は終焉を迎える。
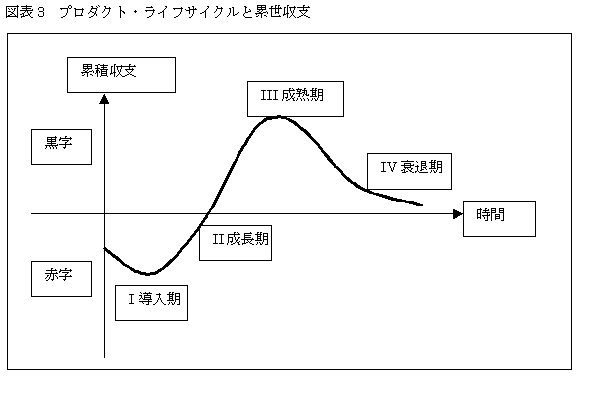
3. プロダクト・ライフサイクルと投入コストとリターンのグラフの融合
投入される資本の調達には当然コストが掛かる。プロダクト・ライフサイクルに期待収益率(投入コストを勘案して各事業・製品に対して求められるリターン。企業経営で用いられる各ビジネスラインに求められる期待収益率は投入資本額の大小に関わらず一定である場合が多いと思われるので、ここではX軸と平行な直線で表されている)を加味したものが図表4である。図表4では横軸が投入資本、縦軸にリターンを表している。
導入期においては多くの資本が投入されるがリターンは低く、期待収益率を下回っている。成長期において、より多くの資本が投入されることになるが、売上が順調に伸張すればリターンが期待利益率に到達する。つまり期間収益が黒字化する。成熟期においては追加的な開発費、宣伝費といったものが徐々に不要になることから投入資本の減少が見込まれる一方売上は伸張する。従ってリターンは最高になる。その後売上の減少と共にリターンは低下して行く。商品寿命を延長するために化粧直しをするなど追加資本が投入されるかもしれないが、リターンが低下した時点で商品寿命が尽きたと判断される。
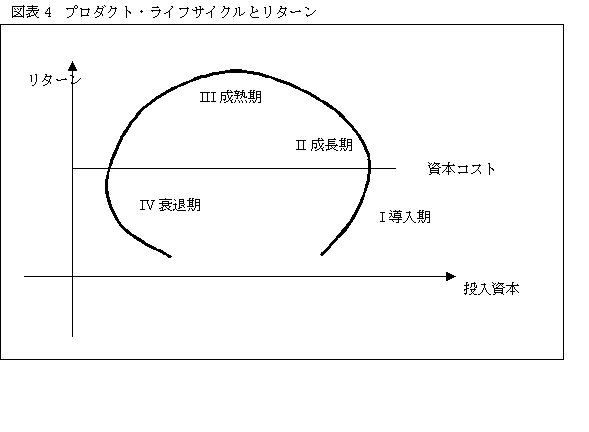
4. 右肩上がりとなるリスク調整後期待利益率
上記図表4を、さまざまなリスクを勘案し検討しなおしたものが図表5である。バーゼルIIにおけるエコノミック・キャピタルの測定においては信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクのほか金利リスク、レピュテーショナル・リスク、戦略リスクなど“想定外”の損失に対しても備えることが要請されている。想定外のリスクにも備えるという考え方はそのまま一般企業の経営管理にも応用可能であると考える。
図表4において横軸は投入資本そのものを取っていたが、図表5においてはリスクを勘案して配賦されたエコノミック・キャピタルを投入資本で割ったもの(EC/AC)に置き換えられている。また、図表4ではX軸と並行であった期待利益率がリスクを勘案して右上がりの直線で表されている(RA(リスク調整後)期待利益率)。エコノミック・キャピタルと投入資本が等しくなる(EC/AC=1)地点でRA期待収益率と縦軸との交点における金利が図表4における期待収益率と同じになる。
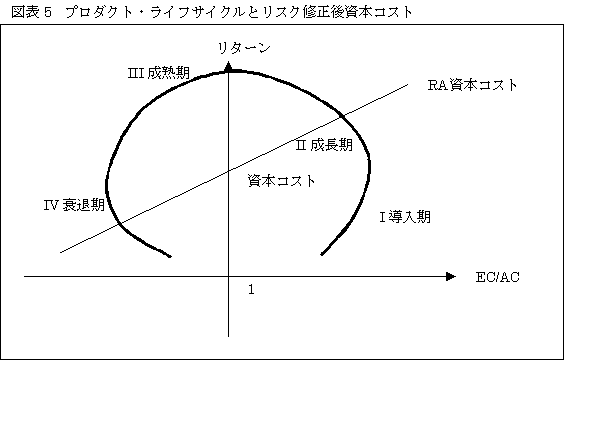
RA期待収益率が右上がりの直線で表されていることから、図表4において期待収益率を上回るプロダクト・ライフサイクルのステージと、図表5においてRA期待収益率を上回るプロダクト・ライフサイクルのステージが異なることに気づく。図表4において期待収益率とほぼ同じリターンが期待できた成長期においても、リスクを勘案すると依然として期待された利回りが実現できていないことに気が付く。また、すでにプロダクト・ライフサイクルが終焉にあると思われる衰退期においては、依然としてRA期待収益率を上回っている。なぜRA期待収益率は右上がりの直線で表されているのであろうか。
まず成長期に注目してみよう。成長期においてはEC/ACが1を上回っている。つまりリスクを勘案すると実際に配賦された資本量より多くの資本量が配賦されないといけないことになる。商品の成長期においては販売数量が飛躍的に増大する。それに対していわゆる初期不良は出尽くしていない上、販売量が増大すると商品を開発した側では全く想定していなかったような使い方をされ、想定外の故障や事故が発生したりする。また、販売側も商品特性を充分に把握していないなど不慣れなこともあり充分な顧客対応が出来ないことも考えられる。つまり、販売体制・内部管理体制などが増大する販売量に追いつかないのである。急成長した企業がコンプライアンス関係の問題を指摘され、市場からの退出を余儀なくされる例が思い起こされる。表面的な売上や利益を追い求めるあまり、潜在的リスクへの資本配賦が不十分だったと言えるだろう。
バーゼルIIの第二の柱においては一般的なリスクばかりではなく「あらゆる」リスクに対応できる資本量の配賦が求められている。そういう意味からすると成長期には想定外のリスクを担保する必要があるため、実際に配賦された資本量よりも多くのエコノミック・キャピタルが必要とされており、リスクに見合った収益を確保するためには、単純な期待収益率より高いリターンが求められていることになる。
衰退期の場合はどうであろうか。衰退期においてはEC/ACが1を下回っている。通常の理解では配賦資本が充分に活用されていないことを意味しており、配賦されている資本を減少させ、配賦資本が不足している部門に移転させることが通常の処方箋となる。
これに対し、リスクの概念を導入すると別の角度からの分析も可能となる。衰退期においては、初期不良などは出尽くしており、会社側の販売体制・内部管理体制なども完備しており、クレーム処理なども的確かつ迅速に行える。リスクはほぼ顕在化しており、その対処方法も確立されている。それ以前のサイクルにおいて社内体制の整備などに多額の投資が行われてきたことであろう。以前の投資を勘案すれば、確立された経営インフラを利用する他部署、あるいはプロダクトに対してコストの請求も可能であるとも考えられる。従って必要とされるエコノミック・キャピタルの水準も低くなる。
また、製品として成熟し市場にも長く受け入れられている商品は、認知力も強く顧客ロイヤリティーも期待できる。つまり、ブランドとして確立していると考えられる。ブランドの確立には長い時間が掛かる割には不祥事などによって失われるときは一瞬にして胡散霧消してしまうのが特徴である。そうであるとすれば、ブランドはコストとは逆のバリューを生み出していると考えることができる。プロダクト・ライフサイクルにおいては衰退期にあるとはいえ、そのリスク量の少なさ、あるいは生み出すバリューを勘案すれば、少々リターンが低くても製品寿命が尽きたと判断するのは早計であることになる。
以上のようにリスク概念を勘案するとRA期待収益率は右肩上がりの直線で表されることになる。また、RA期待収益率の概念を導入することにより今までとは異なった切り口でプロダクト・ライフサイクルを見ることが可能になるのである。
5. シナリオの導入によるストレス・テスト
さらに、シナリオ分析を導入するとどのような分析が可能になるのであろうか。図表6はさまざまなプロダクト・ライフサイクルを示している。通常想定されるプロダクト・ライフサイクルは実線で、それ以外のシナリオに沿ったプロダクト・ライフサイクルは破線で示されている。ばら色のシナリオばかりでなく、事業が失敗に終わるシナリオも想定することにより、一種のストレス・テストが可能になる。
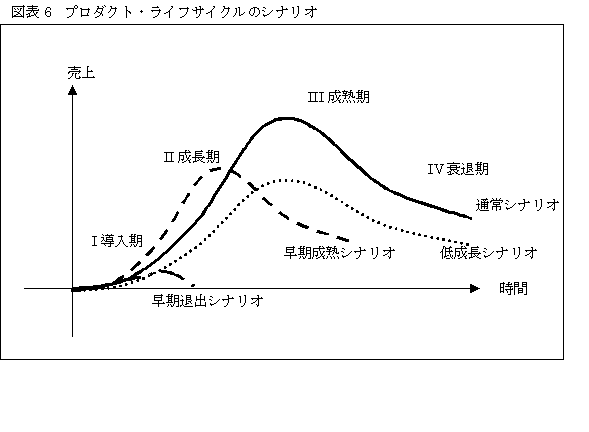
一般的なプロダクト・ライフサイクルでは導入期から始まり成長期・成熟期・衰退期といったプロセスを辿るとされているが、実際には多くの商品が早期退出シナリオで示されるような、まともに市場に現れることなく消え去って行く哀れな末路を辿ると言われている。
図表6ではそのほか市場には受け入れられるものの非常に早く製品寿命が尽きてしまう早期成熟シナリオ、商品の売上が伸びない低成長シナリオを示した。
以下、それぞれのシナリオにおけるプロダクト・ライフサイクルと累積収支およびプロダクト・ライフサイクルとRA期待収益率のグラフを検討してみよう。
図表7は早期退出シナリオにおける2つのグラフである。累積収支は悪化しっぱなしで製品は市場から退出してしまう。当然RA期待収益率を上回ることはないし、期間収益の黒字化も期待できない。もしこのようなシナリオに蓋然性があるのであれば、複数の早期退出シナリオを想定することにより、どの程度の累積赤字であれば許容可能であり、赤字額がどの程度になったら市場から撤退すべきであるかといったシミュレーションが可能であろう。シミュレーションの結果として累積収支に一定の枠を設け、実際の累積赤字が枠に到達した時点で市場からの撤退を決定する、といった使い方ができるであろう。
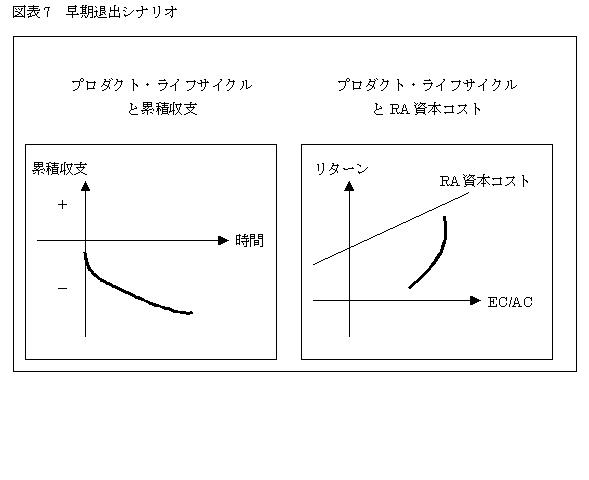
図表8は早期成熟シナリオに沿った2つのグラフを示している。まず、累積収支のグラフにおいては、早期に成長期・成熟期を迎えることから早期に期間収支の黒字化を期待できる。しかしながら商品寿命が短く、本格的に投下資本を回収する成熟期が短いため、累積収支を黒字化できるかどうかは微妙である。商品寿命が短いことが予期できるのであれば、複数の早期熟成シナリオを作成、初期投資と成熟期の資本回収の条件を変えながらシミュレーションすることによりどの程度の初期投資まで許容できるかが決定できる。当然のことながら、商品開発や営業活動といった初期投資に一定の歯止めをかけるといった計画が合理性を持つであろう。
また、RA期待収益率の図においては、プロダクト・ライフサイクルの円が若干右側にシフトしていること、およびRA期待収益率を上回る期間が短いことが示されている。これはそれぞれ、商品寿命が限られていることから潜在的リスクが顕在化せず、プロダクト・ライフサイクルを通じてリスクを抱え続けることを余儀なくされていること、投下資本を回収できる期間が限られていることを示している。期待される合理的な事業計画は上記のとおりである。
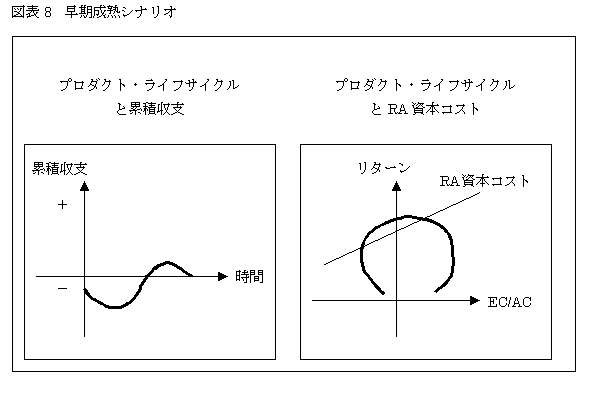
図表9は低成長シナリオにおける2つの図を示している。低成長シナリオではプロダクト・ライフサイクルの最盛期においても大きな売上を期待できない。したがって累積収支で見ると赤字の期間がだらだらと長く続くことになる。低成長シナリオが想定される場合、さまざまな低成長シナリオを想定することにより、累積収支を黒字にするにはどの程度の成長率が最低限でも必要なのかシミュレーションが出来るであろう。その場合、それ以上の高成長を実現させるための無理な資本投下は控えるといった事業計画が合理性を持つことになる。
また、RA期待収益率の図において、早期成熟シナリオと同じようにRA期待収益率を上回る期間が短いことが示されている。ただし、プロダクト・ライフサイクルの円は早期熟成シナリオのような右シフトは見られない。これは、プロダクト・ライフサイクルが一定の長さを持つことが期待されているため、潜在的リスクがある程度顕在化し、対処方法もある程度完備されることが期待されているからである。
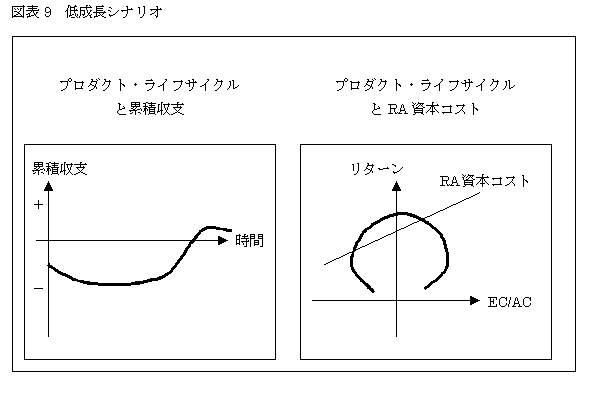
以上検討してきたのは抽象的シナリオであったが、実際の事業計画への適用に当たっては、シナリオそれぞれに対して合理的な売上、成長率、利益率、あるいはリスク・ファクターといった数値を想定することによってより具体的なシナリオ分析が可能になる。シナリオを想定することにより、ばら色ではない事態が想起した場合におけるストレス・テストが実施できることになる。そもそも、事業が不調に陥った場合、いったん事業として始めてしまった以上事業が失敗であったとして撤退を決断することは困難な場合が多い。判断を先送りして傷を深めてしまう事例には事欠かない。事例及びなぜそのようなことが起こるかについては拙稿「コンプライアンスを機能させるための組織」(http://www.fpohkuni.com/HRE703.htm)を参照されたい。
シナリオ分析は新製品の将来予測といった経験的データが集めにくい分野における将来予測においてもっとも大きな効果を発揮する。ただしシナリオ分析は絶対的ツールではなく、予測結果の精度はすべて策定されたシナリオの作り込みにかかっている点には注意が必要である。あくまでもシミュレーションであり、それをどのように経営に生かすかは経営判断の問題である。
さらに、バーゼルIIで問題にしている集中リスクなどもシナリオ分析によって分析可能である。最終的な消費者への販売を除けば、販売ルートというものはある程度限定的であることが予想される。販社がライバル商品を取り扱っている会社と合併したとか、最近よく耳にするような不祥事を起こして販社の会社機能が停止してしまった、などと言う商品そのものとは全く関係のない理由で商品寿命が尽きてしまう場合もある。単一商品について複数の販売ルートを持つことが難しい場合でも別商品では別販売ルートを用意するなど対処が可能な場合もある。どのような対策が可能か、どのような対策を採るべきか、などはシナリオを使ったリスク分析が役に立つものと思われる。
第3章
結論