ヒューマン・リソース(MGM705)4クレジット
ゲーム理論と共創社会
Rushmore
University
Global
Distance Learning DBA
大國
亨
このコースワークを提出するにあたって、ここに記述されている文章/アイデアは、引用の表記がない限り、私の作品であります。また、私がこのコースの研究を手がけるまでは、このコースワークは存在しなかったことを確認します。
ビジネスはよく戦争にたとえられる。戦争では相手を倒すか、相手に倒されるかしかないかのように思われてきたからである。しかし、社会の進展は、社会のネットワーク化をもたらした。ネットワーク社会においては、企業と消費者の関係も、今までのような一方的なものではなくなってくる。
それだけではなく、今までは単なるライバルであった他社との関係も、勝ち負けを競うだけではすまなくなってきている。このことを、ゲーム理論とコーペティションの概念を使うことによって明らかにする。
ただし、ゲーム理論からは、ネットワーク社会では必要とされる“協力的な”(あるいはコーペティションに基づく)行動をなぜとらなくてはいけないかは必ずしも明らかにされない。そこで、“信頼”という言葉をキーワードとして、協力を安定的に供給する社会の在り方を探る。
最終的に、ネットワーク社会が必然的に求める共創社会を条件づけるものである。
目次
1.はじめに
2.ゲーム理論
2.1ゲーム理論とは
2.2囚人のジレンマ
2.3絶対優位戦略とナッシュ均衡
2.4デファクト・スタンダードの動学的分析
2.5継続的囚人のジレンマ
3.ゲーム理論の応用
3.1あるビジネスゲーム
3.2Win-Win戦略
4.ゲームを変える
4.1コーペティション
4.2一番安いと一番よい
4.3 航空会社のマイレージ・プログラム
5.共創社会とは
5.1顧客ロイヤリティー
5.2共創社会と信頼
5.3低信頼社会と高信頼社会
5.4安心と信頼
5.5信頼とコミットメント
5.6評判の重要性
6.共創社会における信頼
6.1社会的知性としての信頼
6.2信頼すると信頼される
6.3信頼の発信
7.結論
1.はじめに
ビジネスはよく戦争にたとえられる。戦争では相手を倒すか、相手に倒されるかしかないかのように思われてきたからである。このような現実の関係を表現するのに用いられるのがゲーム理論である。
しかし、社会の進展は、社会のネットワーク化をもたらした。ネットワーク社会においては、企業と消費者の関係も、今までのような一方的なものではなくなってくる。自分と相手が食うか食われるかの対決をしているのではなく、共存共栄を目指す社会なのである。
共創社会のように一方的な勝ち負けが問題とならない社会を、ゲーム理論を使って分析するとどのようなことが明らかになるのであろうか。
2.ゲーム理論
ゲーム理論は、コンピュータ理論の父としても有名なジョン・フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンシュタインによってその基礎が作られた。最初の著作『ゲームの理論と経済行動(Theory
of Game and Economic Behavior)』は1944年に刊行された。
フォン・ノイマンは、コンピュータ理論の父としても、また、OR(オペレーションズ・リサーチ)の開祖としても知られている。フォン・ノイマンはその他にも、マンハッタン計画にかかわった科学者の一員であり、スタンリー・キューブリック監督の映画「博士の異常な愛情」(1963)に出てくる車椅子の博士(ピーター・セラーズが演じた)のモデルであるとも言われている。フォン・ノイマンは幼くして神童といわれた早熟の天才でありながら、成人してからも様々な分野で大きな足跡を残した巨人であった。ガンにより1957年54歳の若さで亡くなった。
2.1ゲーム理論とは
彼らは、経済活動など、複雑な要因に基づいて行動する人間を、チェスなどの予め定められたルールに従ったゲームとして分析することを目的とした。「彼らは、複数のプレーヤーがあるルールに従ったゲームを行う場合においては、自分自身のゲームの結果が自分の行動のみならず、他の参加者の行動にも依存することに注目した。このようなゲーム(相互依存性のあるゲーム)においては、他の参加者の行動を予測することがきわめて大切であり、そのために必要な非常に複雑な推測を体系的に理論づけることが、彼らの研究の本質的テーマであった。」(鈴木一功
『MBA ゲーム理論』監修者まえがき)
ORが実は戦争遂行の必要性から生み出されたことは、拙稿(http://www.fpohkuni.com
「ランチェスター理論の応用」)でもご紹介したとおりである。実は、ゲーム理論にも同様の背景があるらしい。
第一次世界大戦において、英国は散々ドイツのUボートにてこずらされた。そこで、潜水艦を攻撃するために爆雷(水中に投下する爆弾。爆発する深度を予めセットして投下される)を駆逐艦から投下して攻撃するようになった。当時の潜水艦は海中におけるスピードは遅く、換気のためにしばしば浮上しなくてはならないなどの制約はあったものの、水上の駆逐艦に対して、水中にいる限り姿が見えないという有利な条件があった。
潜水艦側はこの条件をフルに生かして駆逐艦から逃れようとし、駆逐艦側は逃がすまいとするのである。海中でエンジンを止めて(大きな音を出すと駆逐艦側のソナーに探知される)敵駆逐艦の攻撃に耳を澄ませ、爆雷の直撃を躱しながら逃げようとするのである。
海中に潜む潜水艦の位置を海上から探知することは難しい。姿の見えない潜水艦に対して絨毯爆撃をするわけにもいかない。しかし、何らかのきっかけ(攻撃してきた、浮上しているところを発見したなど)で発見した後は、その後の行動を予測することができる。当時の潜水艦は海中から水上の艦船を攻撃できなかったようであるから、一旦潜水艦が潜ってしまえば、攻撃するのは駆逐艦側だけである。攻撃することによって潜水艦の進路を一定の方向に追い込み、止めを刺すのである。当然潜水艦側は駆逐艦側の予想の裏をかこうとして行動する。ところが、潜水艦の位置を予測するのは専ら艦長達の直感に頼っていたので、攻撃成績はあまりよくなかった。
英国は大体において駆逐艦側(英国は一大海軍国であるが、英国の潜水艦が第一・二次世界大戦を通して活躍したという話はあまり聞かない)であったので、いかにすれば駆逐艦からの攻撃を効率的に行うことができるかが研究の対象になったのである。
潜水艦が逃げる場合、決してランダムに進路や深度を変更するのではない。駆逐艦の攻撃能力、速度、進路、潜水艦の速度、潜っていられる時間、海中の地形などを総合的に判断して決定しているはずである。従って、潜水艦の乗組員の思考を適確に予想することができれば、潜水艦の行方もつかめるはずである。
このようなことを背景にゲーム理論は生まれたのである。そのような考え方を導入することによって、攻撃成績は飛躍的に向上したそうである(Adam
M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff『コーペティション経営』p12)。
また、米国においては、日本における空爆の目標を設定する際に、爆撃機が打ち落とされる確率が最小となるような爆撃戦略を考案するために活用された。もし、米国が常に最も重要な標的ばかりを狙っていると、日本側が先回りして防空体制を敷く可能性があるからである。実際には、広島・長崎に対する原爆投下がこのような考察の後に決定されたそうである(William
Poundstone『囚人のジレンマ』p96)。
詳しくは後述するが、この潜水艦と駆逐艦の関係、あるいは米軍爆撃機と日本軍の関係は、利害関係が完全に対立している(取り逃がした場合には駆逐艦は敵潜水艦の攻撃に脅えることになる、爆撃機は打ち落とされる可能性がある)、お互いに合理的な行動をとることが期待されている(双方とも高度な教育と経験を積んだ士官が決断を下している)、相手の行動によって自分の対応を変えなくてはならないなど、ゲーム理論の前提となる要素がふんだんに盛り込まれているのが特徴である。
2.2囚人のジレンマ
ゲームの理論の中で、最もよく知られている例が、囚人のジレンマである。
<事例1>
甲乙という2人の囚人が別々にとらわれ、取り調べを受けている。2人は別々に収監されているので、お互いの行動は分らない。
2人が犯したとされる犯罪には確たる証拠がなく、自白が決めてとなる(このような取り調べの是非は本稿では問わない)。
そこで、警察は取引を持ち掛ける。
「おまえ達が2人とも黙秘しても、2人とも1年の刑を科す。そのかわり、おまえだけが相棒を密告すれば、おまえは無罪放免してやる。その代わり、相棒の刑期は5年だ。ただし、2人とも密告したら、2人とも刑期は3年だ。」
お互いの行動と刑期をマトリックスにしたものが下記である。
表1
|
|
乙が密告しない |
乙が密告する |
|
甲が密告しない |
甲 1年 乙 1年 |
甲 5年 乙0 |
|
甲が密告する |
甲 0 乙 5年 |
甲 3年 乙 3年 |
このような場合において、甲乙はどのような行動をとることが予想されるだろうか。
個人として好ましいのは、刑を受けないことであるが、そのためには自分が密告し、相手が密告しないことが必要とされる。自分が密告したことを相手が知れば(刑期が長くなることで必然的に相手は気付く)、あとで復讐されたりするかもしれない。
であるとすれば、お互いに好ましいのは、お互いに秘密を守ることによって、1年の刑期を務めることであろう。お互いの被害が最小限に留められる。それでは、お互いに合理的に行動するとして、左上の欄のような結論に到るのであろうか。実は、容易に想像できる通り、甲乙ともに相手を密告することによって、お互いに3年の刑期を務めることになる右下の欄のような結論に到ってしまうのである。
なぜならば、自分が密告した場合には、刑期は0年もしくは3年であるのに対して、自分が密告しない場合には、刑期は1年もしくは5年になる。乙が密告する場合と密告しない場合の確率がいかなる割合で与えられていたとしても、甲は密告した方が刑期の期待値は短くなってしまう。つまり密告する方が合理的なのである。従って、甲は密告するのである。
逆に、乙の立場にたった場合、まったく同じ推論が乙の側からなされる。従って、乙も密告するのである。
従って、甲乙ともに3年の刑期を務めなくてはならない。お互いに密告し合わなかった場合にはお互いに1年で済むのであるから、その方がどう考えても好ましいように思われるが、甲乙が合理的に行動するとそのような結論は出てこない。お互いが得るところがないにもかかわらず(お互いが得るところがあるのは、お互いが密告しなかった場合)、お互いに密告しあうという結論に結び付いてしまうのである。
個人、あるいは個別の企業として合理的な行動をとっているにもかかわらず、社会全体として見れば、不利益に結び付いてしまうことから、「ジレンマ」と呼ばれているのである。
2.3絶対優位戦略とナッシュ均衡
上記は、甲乙ともに相手が取った戦略に関係なく自分がある戦略を取った方が高い利得を得られる場合を得られる戦略が存在する場合である。このような戦略を絶対優位の戦略と呼ぶ。このような場合には、甲乙の取る戦略はひとつに決定されてしまう。
ところが、現実には絶対優位の戦略が存在するとは限らない。しかし、そのような場合でも十分合理的な戦略が取られる。このような均衡を研究したのが、ノーベル賞受賞者であるジョン・ナッシュ(2002年アカデミー作品賞を受賞した「ビューティフル・マインド」は彼の伝記映画である)であり、そのような状態をナッシュ均衡と呼ぶ。
ナッシュ均衡とは、「全プレーヤーが、『他のプレーヤーの戦略を前提とした場合に、自分が最適な戦略を取っている』という状態」(鈴木 一功監修 グロービス・マネジメント・インスティテュート編『MBA ゲーム理論』p22)のことである。
<事例2>
例えば、甲銀行と乙銀行が合併をすることになった。銀行が合併する場合には、どのようなシステムを採用するかが大きな問題となる。システム開発が銀行業の根幹を揺るがすほどの巨額の資金を食ってしまうからである。そこで規模の収益を求めて合併を画策するのである。両行のシステムが同じであればなんの問題もないが、異なっていた場合には大きな問題になる。採用されなかったシステムを開発していた銀行にとっては、投資は無駄になり、行員達は新しいシステムを再度習得しなくてはならない。さらに、メンツもつぶれる。
このような場合の利得をマトリックスに表すと、下記のようになるであろう。
甲銀行がAシステムを、乙銀行がBシステムを採用していたとする。
表2
|
|
乙銀行 |
||
|
Aシステム |
Bシステム |
||
|
甲銀行 |
Aシステム |
甲2、乙1 |
甲0、乙0 |
|
Bシステム |
甲0、乙0 |
甲1、乙2 |
|
甲銀行と乙銀行にとって、合併をしてもシステムが統合されないのでは、合併メリットが全くない。場合によっては、合併そのものが破談になる可能性すらある。
通常は、甲銀行か乙銀行のどちらかが譲ることによって、両行がともに同じシステムを使うことになる。しかし、その場合でも、先行してそのシステムを使っていた銀行の効用が大きいことは容易に推察できる。そのため、AシステムもしくはBシステムを両行が採用した場合の甲乙の効用が異なるのである。
もし、何らかの原因でAシステムが採用されたとする。この場合、甲2、乙1の効用が得られることになる。この場合、甲乙ともに相手の選択を所与とした場合、自分の選択を変更するインセンティブは働かない。なぜならば、甲にとってAからBシステムへの変更は効用を2から1へ減少させ、乙にとっても効用を1から0へと減少させるからである。これは、効用の数値は異なるものの、Bシステムが採用された場合でも同じである。従って、このような均衡状態は安定的であるといえる。このような均衡をナッシュ均衡と呼ぶ。
それでは、ナッシュ均衡に基づいて、A、Bどちらのシステムが選択されるか判明するのであろうか。実はナッシュ均衡からは、どちらの選択がなされるかは分らない。唯一分るのは、その均衡状態が安定的であるということだけである。
両行が同じシステムを採用するメリットは自明のことであるから、現実的にはどちらかが譲るのであろう(最近の合併のケースでは、実際にシステムを使う両行の事務職員に実際に両行のシステムを使わせた上で評価させ、使い易い方のシステムを採用したそうである)。大変共創的な考え方である。逆に、3行合併で世界有数の巨大銀行となったみずほ銀行は、お互いに自行のシステムを使うことを譲らず、結局ひとつのシステムに集約できなかった。結局それぞれのネットワークをブリッジ・コンピュータで繋ぐ方式を採用したが、開発時間不足で大量の未処理を発生させた(資料1参照)。参加者が3人に増えても、ゲーム理論は成り立つ。ただしその場合、利得マトリックスは表2よりも複雑なものとなる。みずほの当事者はシステム統合の利得を分析しなかったのであろうか。それとも、みずほの場合には、利得構造が全く違っていたのであろうか。興味の持たれるところである。
現実にはこのようなナッシュ均衡は日常的に見られる。例えば、駅のエスカレーターの片側を急ぐ人のために空けておくことは良く見られる光景である。しかし、東京では右側を空けるのに対して大阪では左側を空けるそうである。これがいわゆるデファクト・スタンダードである。刀を腰に差しているわけでもなく、どちらかに並ぶことに特に合理的な理由があるわけでもない。しかし、デファクト・スタンダードに異を唱えても仕方がない。反対側に立っていて邪険にされるのは自分だからである。デファクト・スタンダードの例は、PCのOSのウィンドウズ対マッキントッシュ、VTRのVHS対ベータなど数多く存在することが知られている。ただし、そのような均衡状態に何が要因となって達したかの分析は今後の課題として残されている。
2.4デファクト・スタンダードの動学的分析
なぜウィンドウズが選ばれたのかについては確定的な分析はできないものの、どのようにしてデファクト・スタンダードになったかについて、ゲーム理論は興味深い分析を提供してくれる。
<事例3>
職場に5人の人間がいて、3人がAソフト、2人がBソフトを使っているとする。このときの状態を(3A、2B)と表す。Aソフトの方が若干性能はよく使いやすいものの、ソフト間には互換性はまったくなく、ひとりがふたつのソフトを同時に使いこなすことはできない。しかし、この職場ではよく2人がペアを組んで仕事をする。その場合、2人が同じソフトを使った方が効率は上がるものとする。その際のふたり(甲乙)の利得は表3-1に示されているとおりである。ペアを組む相手はランダムに決定されるものとする。
この集団のひとりがソフトを新しく購入する。その際、ペアを組んで仕事をする際の利得の期待値に従ってソフトを選択するものとする
表3-1
|
甲╲乙 |
Aを使用 |
Bを使用 |
|
Aを使用 |
6、6 |
1、1 |
|
Bを使用 |
1、1 |
4、4 |
(3A、2B)の状態において、Aを使用している人間がソフトを買い換えるとする。残りの4人はふたりずつAとBを使用している。その際の利得の期待値は、
Aを選んだ場合、
![]()
Bを選んだ場合、
![]()
となるので、Aを選ぶことになる。5人中3人がAを現に所有しているので、3/5の確率で(3A、2B)の状態から再び(3A、2B)の状態になる。表3-2において(3A、2B)の下側に描かれている矢印がこのことを示している。
同様に、Bを使用している人間がソフトとを買い換えるとすると、その際の利得の期待値は、
Aを選んだ場合、
![]()
Bを選んだ場合、
![]()
となるので、BからAへと買い換えることになる。Bを使用している人間は5人中2人であるので、2/5の確率でBからAへの買い替えが起こる。表3-2において(3A、2B)の左上に示されている矢印がこのことを示している。
同様にすべての場合の確率を表3-2に示した。
矢印の上側の数値は買い替えが起こりABそれぞれのソフトを使う人数が変化する場合を示し、下側の矢印は買い替えが起こらず同じ数の組み合わせに戻ることを示している。
表3-2
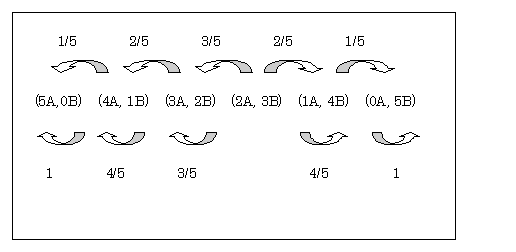
表3-2で興味深いのは、(2A、3B)の状態以外からは、常に一方にしか推移しないことである。また、上記設例ではA、Bへの選択が確定的に行われるとしたが、プレーヤーが間違いを犯す可能性のある場合についてもシミュレーションができる。その場合、「このような動学的な推移を十分に長い時間観察した場合に、そのほとんどの時間においてこのグループのメンバーはXを使用する状態になることが示されています。」(武藤 滋夫『ゲーム理論入門』p218、ただし、拙稿中ではXはAと表記されている)
上記設例では、Aを使用する人間の方が多く、なおかつAの性能が優れているように設定されている。しかし、たとえ性能が劣っていたとしてもそれを覆すほどの数的優位にある場合、逆に数的に劣っていたとしても、それを覆すほどの性能差があればそのようなソフトが選択されることも同様にして証明されるのである。
ウィンドウズ対マッキントッシュのように、にわかには性能差がわからない場合でも、数的に優位に立つことによって、みんなが使っているから自分も使うというその製品にとっての好循環を作り出すことができるのである。
デファクト・スタンダードに見られるナッシュ均衡状態へはこのように導かれるのである。
2.5継続的囚人のジレンマ
たった一回だけのチャンスしかない事例1や事例2は、ビジネスの場面で言えば、一見の客が店頭に現れた場合などに当てはまるのであろう。商品を売る側にしてみれば、どのくらい買う気があるのか分らず、継続的に買ってくれるかどうかも分らない一見の客には、愛想良くするだけ労力の無駄に思えてしまい、魅力的な価格提示だってできないであろう。
一方、客の側にしてみれば、店の信用だって分らないし、アフターサービスも分らない。熱心に買い気を見せれば、高い値段を吹っかけられるかもしれない。従ってこわもてで交渉に臨むことになる。
結果売買交渉は不成立に終わる。
それでは永遠に何も起きないことになってしまうが、実際には交渉などではある程度の駆け引き、やり取りが行われるのが当然であり、双方の意思表示が一回しかできない、といったことは考えにくい。
そのような事例をパターン化したのが、継続的囚人のジレンマである。
<事例4>
この場合は、事例1のような密告するかしないかでは、一回しかゲームが成立しないので、お互いに赤と黒カードを提示し合うようにする。
お互いのカードの出し方と、得点パターンは下記のようになる。
表4
|
Aの選択╲Bの選択 |
赤 |
黒 |
|
赤 |
A 2点
B 2点 |
A −5点
B 5点 |
|
黒 |
A 5点
B −5点 |
A −1点
B −1点 |
上記囚人のジレンマと同じように、これが1回だけのゲームであれば、お互いに負けまいとすれば、黒を出すことになる。
このようなゲームを無限に繰り返す場合には、「TIT
FOR TAT」と呼ばれる戦略(略してTIT戦略とも言う。「Tit for
tat」とは、しっぺ返しの意味)がもっとも有効であるといわれている(資料2参照。資料2では「お返し戦略」と呼ばれている。その他、「おうむ返し」などとも訳されている)。
TIT FOR TAT戦略
1.
1回目は協調的戦略を取って、相手の出方を見る(つまり赤を出す)
2.
2回目以降は、前回相手が出したのと同じカードを出す。相手が協調的な行動をとればそのまま協調的行動を続けるし、相手がこちらを出し抜こうとして黒を出せば、その次の回にはこちらも黒を出してリベンジするのである。
つまり、最初はお互いの協調を期待している振りをするが、一旦相手が裏切った場合には、猛然と反撃に打って出るのである。そして、相手が反省してもう一度協調的な行動をとった場合には許してやるのである。
なにやら、現在世界で唯一の超大国と呼ばれている国の外交戦略とぴたりと附合しているような気がするが如何であろうか。
また、ゲームが無限に続く場合には、トリガー戦略が有効であるといわれている。トリガー戦略というのは、TIT戦略と同様最初は協調的行動をとり、相手が裏切ったと見るや反撃に打て出る。そして、この場合、相手がどのような行動をとったとしても、絶対に許さず、以後お仕置きをし続けるのである。
この戦略は、報復の脅しを利かせることによって、相手に協調的行動をとらせる場合を説明するときに良く使われるようである。例えば、核の報復を前提とした平和などである。
ただし、このような理論の現実世界への反映には慎重であるべきはずである。TIT戦略の有効性を証明したアクセルロッドは、「この理論の目的は、そういったものではなく、人々が物事をはっきりと見ることができるようにすることなのです。ゲーム理論のみならず、こうした形式的なモデルがあった方がモデルなしでものごとを見るよりも、物事を動かす本質を、はっきりととらえることができるのです。ただし、すべての本質が明らかになるわけではありません。モデル化するために捨てられる要素も多々ありますし、その中には、きっと重要なものもあるでしょう」(William
Poundstone『囚人のジレンマ』p326)といっている。
しかし、現実の国際問題を考えると、TIT戦略を地で行くような報復戦略が幅を利かせている。報復がさらなる報復を呼ぶ、OK牧場の決闘のごとき復讐劇が際限もなく繰り返されている。
「フォン・ノイマンは、その晩年、現実の戦争が空想的なジレンマ、つまり彼の理論でいう抽象的なゲームにどんどん近づいていくのに気付いた。時として、核時代の危険は「倫理の進歩が技術の進歩に追いつかない」ことからくる、と言われることがある。このような見立ては、倫理的進歩など果たしてあり得るのか、原爆は成長しても人間の方は何一つ変わっていないのではないか、という疑念によって、さらにいっそう気を滅入らせるものとなる。」
「ゲーム理論に現在かかわっている人たちは、ある意味で、倫理的進歩を創り出そうと考えている。つまり、囚人のジレンマにおいて共通の利益を増す方法は何かないだろうか、ということである。」(William
Poundstone『囚人のジレンマ』p22)
ゲーム理論から協調政策を導き出すにはどうすればよいのであろうか。
3.ゲーム理論の応用
ゲーム理論を軽々に現実に適用するには慎重であらねばならないであろう。しかし、ゲーム理論は物事に対して体系的なアプローチを与えてくれる。ゲーム理論によってゲームを構成要素ごとに分解し、何がどのような影響力をもっているか分析するという戦略的思考を可能にする。ゲーム理論は、正しい戦略の見つけ方を教えてくれるのである。
3.1あるビジネスゲーム
<事例5>
ゲームの内容は上記の継続的囚人のジレンマと同じで、ある一定の回数繰り返される。従って、得点配分等は事例4と同じである。
ただしゲームのルールは以下の2つである。
l
ゲームの目的は勝つこと。
l
勝つための条件は、最終フレームに累積されたプラスのポイントをできるだけ大きくすること。
というものである。
このゲームは私が実際に体験したものを再構成したものである。
このゲームが、上記の継続的囚人のジレンマゲームと同じであるとすれば、ビジネス研修として取り上げるには余りにも芸がない。そう気がついた私たちは、もう一度ゲームのルールを検討してみた。そこで気がついたのは、目的は勝つことであるといっているが、「相手に」勝つとはいっていないこと、勝つための条件は得点がプラスでなくてはいけないことに気がついた。
お互いにプラスをためるにはどうするか。答えは簡単で、お互いに協調的行動をとれば(赤を出せば)よいのである。
そこでわがチームは赤いカードを提示したのであるが、相手は何と黒いカードを提示してきた。相手はこのゲームを典型的な囚人のジレンマ・ゲームであるとみなしているのである。つまり、「勝つ」とは「相手に勝つ」ことであると無条件に信じてしまったのである。
このとき、わがチームはどのような反応を取ったのであろうか。実は、次回も赤を出し続けた。理由の一つには、TIT戦略を誰一人として知らなかった、ということもあるかもしれない。しかし、相手チームに協調的な戦略を取らなくては、お互いにゲームに負けてしまうというこちらのメッセージを伝えるには、これしか方法がなかったからである。
結果的には、相手方もこちらのメッセージに気付き、お互いに赤いカードを出し合うことで最終的に両チームとも勝利を収めることができたのである。
実際にこのゲームを研修等で使うと(実際にゲームをする場合には有限回の試行になってしまうが)、お互いに最初から黒を出し合ってしまう場合が多いそうである。
結果はともかくとして、このゲームが示唆するところは重大ではないだろうか。ビジネスにおいて、勝者は必ずしもひとり、1社とは限らない。複数が勝利を収めることも可能なのである。競合他社と協調しなくてはならない場合というのは、大変多いと思われる。
3.2Win−Win戦略
上記のように、競争に関わる双方が満足行くような結果をもたらすような解決方法をWin-Win Solutionと呼ぶ。お互いに満足できるのであれば、両者ともに勝者であると言いうる、ということである。
我々が経済活動を繰り広げていく上で、さまざまな企業や顧客と関わり合いを持つことになる。例えば、ある会社が何か製品を作って販売する場合、その原材料を仕入れ、加工し、販売する。それだけでも原料を供給する会社、顧客が登場する。その他にも、流通業者、広告を委託すれば広報関係の会社、それを印刷したり放送したりする会社、弁護士、会計士などなど無数の関わり合いが生まれてくるのである。それだけではなく、ライバル会社でさえ、Win-Winの関係に立ち得るのである。
例えば、高性能コンピュータ・チップのメーカーとして名高いインテルと、ソフトウェアメーカーのマクロソフトの関係を考えてみよう。インテルにとっては、高性能なハードを要求するソフトウェアを開発してくれないと、自社の製品が売れなくなってしまう。それだけではなく、自社の製品開発のサイクルとソフトウェアの開発サイクルもできれば似通ったものであってほしいと思っているであろう。なぜならば、ハードの開発には膨大な手間と資金が必要であるのに対して、製造自体のランニングコストは意外に安い。従って、資金回収のためには、販売価格が低下する前にいかに開発コストを償却してしまうかが問題になる。高性能なハードを必要とする新しいソフトウェアの発売などは、新しい高性能チップの販売を促進する上で最高のプロモーションになる。
逆に、マイクロソフトの側から考えるとどうなるであろうか。最近のソフトウェアは高機能であることは確かではあるが、大変重いものになっている。ソフトウェアには最低限必要なハードウェアの条件が記載されているが、ますます高性能なハードが求められるようになってきている。このような高性能化は、高性能チップを搭載したコンピュータが安価に製造されるようになったことが要因となっている。コンピュータが高価格で誰も買わないのであれば、高機能ソフトなども売れるはずがないのである。安くて高性能なコンピュータが作られることと、安くて高機能なソフトウェアが作られることは、車軸に繋がった両輪のようなものなのである。
それだけではない。高性能チップの価格を、量産効果を通して低下させるためには、数多くのコンピュータメーカーの存在さえもWin-Win関係に立っているといえるだろう。
さらに、これらを購入する消費者を考えてみよう。現在のPCに搭載されているワードプロセッサーの機能は、一昔前であればプロが使う高価な編集用ソフトでしか実現できなかったような多彩な表現を可能にしている(購入者(私?)が使いこなしているかは別問題)。なぜそのようなことが可能になったかというと、膨大な開発費を多くの購入者で分け合っているからである。何千人ものプログラマーを長期間雇用して作られるソフトウェアの開発費は、ひとりで負担できるものではない。
それだけではない。多くの人間が同じようなソフトウェアを使うことによって、コミュニケーションが容易になるのである。ワープロ時代に、データを交換しようとしても互換性がなく、結局紙に印刷したものを手渡すしかなかったのは、たった10数年前のことなのである。何という進歩であろうか。
このことを、コンピュータを作っている会社やインテル・マイクロソフトの側から見るとどうなるであろうか。彼らにとって、製品価格の低下は短期的には利益率の低下を意味する。しかし、それによってもたらされる市場の拡大は、量産効果によるコスト削減とあいまって、利益率の低下を上回る利益をもたらすのである。
現在のところ、コンピュータの製造に係る側と消費者の間Win-Win関係が成り立っているといえるであろう。
このような好循環は、映画産業とビデオ業界などにも見られる。VTRが出回り始めた頃は、誰も高いお金を出して映画館まで行かなくなるので、映画産業はすたれてしまうと思われていた。ところが、現在の状況が証明するように、映画とビデオ業界は共存、それどころか共栄している。現在では、映画館でヒットした作品についてはビデオも売れることが経験的に証明されているので、映画製作にも大変力が入るようになっている。映画がヒットすると、映画を見た人もまた見ようとしてビデオを購入し、映画を見なかった人までビデオを購入するように勧めてくれるからである。映画のヒットはビデオの最高のプロモーションなのである。しかも、そのプロモーションには、入場料まで払ってくれる。そのような関係が明らかになったので、以前はあれほど高価だったビデオも安価に購入できるようになっている。そうなると、ますますビデオの購入者は増えることになる。
これに対して、悪循環が起こった場合にはどのようなことが起きるのであろうか。よく知られた例としては、ベータ対VHSのVTR戦争などがあるだろう。機能的には優位にあったともいわれるベータ側ではあるが、結局魅力あるソフトを供給できず、敗退してしまった。魅力あるソフトがない、誰も買わない、作っても数が売れそうにない、高価格になる、誰も買わない、という悪循環に嵌まってしまったのである。現在世界中でVHS方式が主流となっているのはご存知のとおりである。
コンピュータ業界にしても、今後もこのようなWin-Win関係が成立し続ける保証はない。例えば、これはすでに現実のものとなりつつあるが、少しずつ新しい機能を追加したハードやソフトを次々と買い換えなくてはならないことに消費者が腹を立てて、古いハードやソフトをやりくりして済ませてしまうようになるかもしれない。あるいは、全く別の設計思想で同様の働きをするバイオコンピュータや自ら考えて進歩し続けるソフトが発明され、現在のコンピュータが突然過去の遺物になってしまう可能性もある。その場合、現在のコンピュータメーカーと消費者の間の蜜月は終わってしまうであろう。あるいは、コンピュータは人類の健康にとって有害であるとして突然厚生労働省から使用禁止宣言が出るのかもしれない。
突然、今まで永遠に続くと思ってきたゲームが終了してしまうのである。そのようなときにはどのように対応すればよいのだろうか。その場合に重要なのは、旧来の枠組みに囚われるのではなく、ゲームを変える努力をすることなのである。
4.ゲームを変える
ところで、事例5のビジネスゲームのように協力が成り立つゲームの分析もゲーム理論を使って多く行われている(事例5はコミュニケーションが取れないなかで行われたが、相手と話し合いをしてもよいという条件のゲームもある)。
ゲーム理論というと、対立した2者のゲームという感覚があるが(冒頭に記述した潜水艦と駆逐艦では協力関係は成り立たない)、協力を織り込んだゲームも考えられている。
このような関係を象徴述する言葉として競争(competition)と協力(cooperation)を合成してコーペティション(co-opetition)という言葉が作られた。
4.1コーペティション
「ビジネスは、「パイ」を作り出すときには協力し、その「パイ」を分けるときには競争するものなのだ。換言すれば、ビジネスは「戦争と平和」である。しかし、それはトルストイ―――際限のない戦争と平和の繰返し―――ではない。戦争と平和が同時に起こるのである。ネットワークソフトウェアの会社であるノヴェルを設立したレイ・ノーダの言葉にあるように、「競争すると同時に協力しなければならない」のである(原書注)。競争(コンペティション)と協力(コーポレーション)が合わさると、それぞれの言葉がそれだけで意味していたものよりも、ずっとダイナミックな関係を作り出していく。それゆえに、我々はノーダの用いた「コーペティション」(co-opetition)という言葉を本のタイトルとした。(原書注
Electronic Business
Buyer, December 1993より。“Co-opetition(コーペティション)”という合成語は、レイ・ノーダによって編み出された。)」(Adam
M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff『コーペティション経営』pp10-11)
勝つか負けるかの二者選択しかない従来型の考え方では、ネットワーク化した現在社会におけるビジネスを生き抜いていくことはできない。ビジネスというゲームにおいては、競争が必要な場合も協調が必要な場合もあるであろう。コーペティションの概念はいつ競争すべきか、いつ協調すべきかについて示唆を与えてくれる。それだけではなく、コーペティションの概念はゲームを変えることの重要性を教えてくれるのである。ビジネスはチェスや将棋ではない。守らなくてはいけないルールや社会的規範は存在するが、だからといって従来の考え方の枠に囚われていたのでは発展は望めない。一生懸命やったのに失敗することもある。努力が足りなかったことも原因かもしれない。しかし、間違ったゲームをプレーしていた可能性もある。ゲームを変える努力をしただろうか。
4.2一番安いと一番よい
このようなスローガンは如何だろうか。
「私たちは一番安い製品を売っているのではありません。
私たちは一番よい製品を売っているのです。」
なにやら一度は耳にしたことがありそうなフレーズではあるが(著者のオリジナルです)、実はWin-Win理論やコーペティションに関する興味深い真実を語ってくれているのである。
もし、価格競争を仕掛けることによって市場占有率を上げようとした場合には、どのようなことが起きるであろうか。通常そのような分析には、ゲームツリーと呼ばれるゲーム理論の応用版が用いられることが多い。
甲乙の2社が例えばビール市場を牛耳っていたとする。甲社が価格引き下げを行って市場占有率を高めようとしたとする。その場合、乙社は価格をそのままにするか、追随するかの選択ができる。
どちらを選択するかは、ゲームであれば与えられた条件によっても異なるであろうし、実際のビジネスにおいても正しい行動が簡単に分るわけではないだろう。ゲームツリーの設例などにおいては、値下げに同調しない方が賢明である場合の説明として用いられているようである。
しかし、顧客から価格引き下げか取引打ち切りを選択せよと迫られた企業は、とにかく値下げに同調することによって取引を守ろうとしがちである。
価格引き下げ競争に巻込まれることは、単純にその取引から得られる利益を削減するばかりではないのである。それでは、どのようなデメリットが考えられるのであろうか。
例えば、価格引き下げによってその顧客との取引は守られたかもしれない。しかし、その取引価格が企業にとって妥当なものであるとは限らない。競争に勝つことだけを意識する余り、コスト割れで入札するなどは、シェアを重視する日本ではかなり頻繁に見聞することができる(「できた」というべきかもしれないが)。それだけではなく、その他の顧客にその取引条件を知られた場合、必要もないのに価格を引き下げなくてはならなくなるかもしれない。また、競争相手もその価格を基準として別の顧客あるいは潜在的顧客に取引を要請することであろう。自らの企業がそれら全てを受けて立つほどの財務的余力が有り、価格競争に耐えられる、あるいは価格競争を仕掛けることが可能な場合もあるかもしれない。その場合は、今度は独占禁止法が足枷となるのである。
「自分が勝てば相手が負けるという考え方は、単純すぎて危険でもある。「コーペティション」を思い出してもらいたい。もしライバルの利益を引き下げたなら、ライバルは失うものが減り攻撃的になる。自由にこちらの顧客を狙ってくる。対照的に、利益が大きければ大きいほど、価格競争によって失うものが大きくなるのだ。ガラスの家に住まないものは、こちらに石を投げてくるのだ。ライバルが「ガラスの家」を建てることを助けることは、自分にとっても利益となるのだ。」(Adam
M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff『コーペティション経営』pp130-131)
単純に価格を下げて取引を拡大しようとすることは、相手を捨て身の攻撃に誘うようなものである。市場価格が自社のコストを下回ってしまった場合、いずれは撤退しなくてはならないという判断を下したにせよ、下手をすると玉砕覚悟の攻撃を仕掛けてこないとも限らないのである。競争相手を失うものがない状態にまで追い込んではいけないのである。
4.3航空会社のマイレージ・プログラム
1981年にアメリカン航空によって導入られたマイレージ・サービス(同社の場合A-アドバンテージと呼ばれた)は、ネイルバフとブランデンバーガーによって書かれた『コーペティション経営』においてしばしば引用されるばかりではなく、絶賛されている。導入当初は他社にないサービスであるとして、固定ファンを得ることができたからである。また、それらの固定ファンは、低料金を追求するタイプの顧客ではなく、正規料金を支払ってくれる顧客層であったことも大きなメリットであった。そして、他社が同様のサービスを模倣して提供し始めた後も、会社へのロイヤリティーを高める、優れたアイデアであったとしている。
マイレージ・サービスのアイデアが優れていたのは、航空会社にとって見かけほどにはコストがかからなかったことである。なぜならば、航空機は常に満席の状態で飛んでいるわけではない。航空機を飛ばすには相当額の費用がかかる。そしてその費用は、満席であろうが空席があろうがそれほど大きな違いはない。空気を載せて飛ぶよりはましであるとディスカウント・チケットを販売するのもひとつの方法であろうが、マイレージ・サービスはこの空席を固定ファン獲得のために使ったのである。固定ファン獲得のための追加費用は、航空会社にとっては大きなものではない。しかし、顧客にとっては、正規の料金を支払わなくては得られないチケットを“ただ”で手に入れられるのである。
「利用マイル数に応じた特典制度は、固定ファンを作り出し、航空会社にとっては「双方が勝つ」結果を生んだ。コーペティションの典型的な例だ。」
「欠点はあるにしても、この特典制度は天才的な発明であった。パイを大きくし、固定ファンを作り出す、他に例を見ない方法だ。新規メンバーをめぐる競争は、度を越すこともあるだろう。しかし、てんびんにかけてみれば、航空会社、顧客、ハワイの観光業すべてが勝つ結果を生んだのだ。」(Adam
M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff『コーペティション経営』pp196-197)
このように絶賛された手法であるので、多くの業界で模倣されることになった。現在では航空会社のほかにも、同様の顧客囲い込みの方法は小売業、自動車業界(自動車会社も利用金額に応じて次回新車を購入する際に割引をする特典つきのカードを発行している。最初に発行したのはGM)などでも行われている。
『コーペティション経営』が書かれた1997年には絶賛された制度も、1998年には、「現に、エアライン各社の競争が激烈を極めているアメリカでは、大手エアラインの間で過剰なFFPによりコスト対効果が悪化し、プログラムを縮小する方向にある。また、粗利益の変化が収益に大きな影響を及ぼす百貨店の場合、割引率の競争は経営の根幹を揺るがしかねないとの懸念も高まっている。」(高橋 俊輔『人材マネジメント論』p33、FFPはフリークエント・フラーイヤーズ・プログラムの略。代表例がマイレージ・プログラム)と書かれている。米国のエアライン各社の経営は、2001年秋のテロ事件以後、一段と厳しさを増しているのは、各種新聞報道の伝えるところである。
「米国のサウスウェスト航空は、同じ航空業界でも他社とは、まったく異なった経営戦略を選択し成功を収めた。既存の航空会社は、ルートという利権を手に入れ、より多くのルートを確保するという規模の経済をベースに、マイレージ・プログラムのような、本社中枢のスタッフが立案するマーケティング戦略を中心に競争上の優位性を構築しようとしてきた。そして、現場でオペレーションに携わる多くの社員は、正確性や安全性は求められても、彼ら自体が優位性を生み出す存在とはさほど期待されているわけではなかった。しかし、マイレージ・プログラムなどは各社ともサービス競争が過熱し、競争優位が成り立ちにくくなっているのは、周知の事実だ。」
「これに対し、米国の航空業界でも後発のサウスウェスト航空は、現場のオペレーションにおける顧客とのヒューマンタッチ、すなわち、人的な接点の部分を中心に大きな競争優位性を築こうとし、そのため、従来の航空会社とはまったく異なった人材マネジメントを行うようになった。」(高橋 俊輔『組織革命』p32)サウスウェスト航空は、価格競争などの航空各社にとって好ましくない手法によって業績を伸ばしたのではない。顧客との共創関係を他の航空会社とは全く異なった方法で獲得したのである。同じ航空会社の例でも、サウスウェスト航空の事例の方が、コーペティションの精神に合致していると思われるのであるがいかがであろうか。
同様のことは、クロネコヤマトの宅急便で有名な小倉 昌男も書いている。「宅急便を担う中心的存在は、現場で顧客に接する約3万人の「セールス・ドライバー(SD)」である。彼らは荷物の集配、営業、集金などひとりでさまざまな業務をこなさなくてはならない。まさに「寿司屋の職人」のような働き方が求められる。サッカーで言えば、最前線の「フォワード」にあたる彼らのやる気をいかに引き出し、楽しく働いてもらうか。全員経営の成功はそこにかかっている」(小倉
昌男『経営学』p171)のである。
ヤマト運輸の料金が特に安いという話は聞いたことがない。それでも、1998年の宅配市場では37%のシェアで断然トップである(2位の日本通運のペリカン便は17%、3位の郵便小包は15%、数字は小倉 昌男同前p1)。
ヤマト運輸では、SDには正社員しかなれない。アルバイト、パート、外注による人員はSDにはなれない。その他の顧客に接しない部門ではアルバイトなども活用しているが、顧客とじかに接する部分には、教育の行き届いた正社員しかなれないのである。それが顧客サービスを高め、顧客のロイヤリティーを獲得する道だからである。
ヤマト運輸の配送車は、制限速度などを実によく遵守している。車で後ろに付くとイラつかないといえばうそになるかもしれない。しかし、配送を依頼する段になると、そのように丁寧に扱ってもらえるヤマト運輸に依頼するのではないだろうか。配送効率を上げるため配送車がすっ飛ばしているような会社には依頼しない。競争相手とのコーペティションばかりではなく、社会との共創関係も重要な要素なのである。ネットワーク社会においては、あらゆる方面に対してコーペティションの考え方を維持しなくてはならない。通常はサービスの要素とはいえないような配送車のスピードも、サービスを差別化する重大な要因なのである。
5.共創社会とは
現代社会がいかにネットワーク化し、そのことが共創社会をもたらすものであることは、拙稿「コンプライアンスとリーダーシップ」(http://www.fpohkuni.com)でも明らかにしたところである。それでは、共創社会を成り立たせる条件とは何であろうか。
5.1顧客ロイヤリティー
共創社会とは、ある社会の構成員が何らかの共通の目的を実現するために協力して社会を作り出して行く関係であるといえるであろう。そして、その関係が例えば企業内などにとどまっておらず、外延的に広がっているのが共創社会である。
従来、企業などはピラミッド状の組織を形作っていることが多かった。また、このピラミッドは年齢構成においても同様の構成を持っていた。
しかし、近年企業におけるピラミッド構造はさまざまな理由から崩れつつある。
その第一の原因は、企業として直面している市場の成熟化である。近代・現代社会とともに企業が活動し、販売活動を行っている市場も成長してきた。そして、現代においてはあらゆる市場が成熟化してきている。もちろん、現在でも急成長を遂げているマーケットは存在する。しかし、それは経済全体から見れば大変小さな部分を占めているに過ぎない。実際、主要各国の経済成長率は決して高いものではない。
表 各国の実質経済成長率(%)
|
|
1970 |
1980 |
1990 |
1998 |
|
日本 |
8.2 |
2.6 |
5.5 |
-1.9 |
|
中国 |
--- |
7.8 |
3.8 |
8.8(1997) |
|
イタリア |
5.3 |
3.5 |
2.2 |
1.4 |
|
ドイツ |
4.9 |
1.0 |
5.7 |
1.9 |
|
フランス |
7.2 |
1.6 |
2.5 |
3.2 |
|
米国 |
0.1 |
-0.3 |
1.2 |
3.9 |
|
世界平均 |
3.7 |
2.6 |
3.2 |
4.2(1997) |
IMF,
“International Financial Statistics Yearbook”(1999)による。ただし日本は経済企画庁による。
出典『世界国勢図会2000/2001』国勢社
新しいマーケットがどんどん広がっていくのでない以上、既存マーケットの維持を重視せざるを得ない。そのような社会では、企業と顧客の関係も、一方が他方を収奪するといった一方的関係ではありえない。企業にとっても、顧客ロイヤリティーが重要となってくる所以である。顧客ロイヤリティーはどのようにすれば構築できるのであろうか。
5.2共創社会と信頼
人間は海に浮かぶ孤島ではない。生活していく上で、人との関わりを裂けて通ることはできない。全く周りの人間を信頼しなかったら、生活が成り立たない。ただ単にタクシーに乗ることも、純粋に法律的に考えれば、運転手と運送契約を結んでいることになるのであろう。タクシーに乗るときに隅からすみまで運送約款や契約書を読み、弁護士にも相談し、挙げ句の果てその弁護士も信頼できない、となれば、タクシーに乗ることもできない。
通常はある程度のところで妥協し、契約を結ぶのである。なぜならば、相手を信頼しているからである。
経済学の教科書によく載っているすっぱいレモンというたとえ話がある(レモンとは米国の俗語で不良品の中古車のことである)。内容的には、トマス・グレシャムの唱えた「悪貨は良貨を駆逐する」の現代版である。米国での中古車市場というのは、車が安く買える代りに何の保証もないのが通例であった。米国では、中古車のセールスマンといえば、信用できない職業として真っ先にあげられる。どんなポンコツでもお買い得と言いくるめて売りつけてしまうからである(別に中古車のセールスマンに対する職業差別を意図しているわけではありません。最近では、中古車に対しても保証は付く。また、このような低信用を逆手にとって中古車市場において広く店舗展開を広げることで品揃えや品質を保証する大手業者も現れているようである)。
素人である買い手には不良品と良品の区別はつかない。中古車のディーラーは当然どれが不良品であるかは知っている。このような状況では、お客はわざわざ高いお金を払って中古車を買ったりはしない。万一レモンであっても正当化されるような値段しか払わなくなる。
一方中古車業者も良品を仕入れても買いたたかれて儲からない。いきおいレモンばかり仕入れることになる。結局は中古車市場にはレモンしか見当たらなくなり、市場そのものが崩壊してしまうという、業者、お客双方にとって好ましくない結果を生み出してしまうというものである。もし業者とお客の間に一般的な信頼関係があれば、このような事態は防げたのではないだろうか。
5.3低信頼社会と高信頼社会
フランシス・フクヤマは、経済発展を生み出す要因として、信頼の存在をあげている。きわめて家族主義的な社会では、家族の枠組みを超えて外部の人間とつながりを持つことができない。信頼できないからである。そのような低信頼社会においては、企業組織においても、家族としての枠組みを保ったままの運営を続けざるを得ない。家族主義的な経営も企業組織が小さい場合には通用するが、組織が大きくなると充分な運営ができなくなってしまう。ベンチャー企業などがつまずくのも、売上げや企業規模に見合った企業経営ができなくなってしまうことが原因であることが多い。この場合には、創業者個人、あるいはその取り巻きの結びつきが強すぎる余り、外部の人間を信頼することができなくなっているのである。このような社会をフクヤマは低信頼社会と呼んでいる。
これに対して、家族を超えた他社に対して信頼が存在する社会を高信頼社会と呼んでいる。高信頼社会においては、一般的に他社に対する信頼度が高い。従って、低信頼社会に比べ大きな組織の組成が容易になる。そして、そのような高信頼社会をバックにして経済成長が可能になるとしている。高信頼社会では民間企業に大規模なものが多いのに対して低信頼社会では比較的小規模なものが多数を占めている。この現象の原因をフクヤマはそれぞれの社会における「信頼」の程度によって説明を試みたものである。
低信頼社会の例として中国社会、イタリア社会、フランス社会があげられており、高信頼社会の例としては日本社会、ドイツ社会、アメリカ社会があげられている。
中国、イタリア、フランスなど、いずれも過去に輝かしい栄光を持つ国々である。しかし、それは同時に強力な中央集権的政権でもあった。そのような時代を通じて社会における中間的な組織は破壊されてしまい、社会は二極化した。
例えば、中国の歴史は、皇帝を頂点とする大帝国の勃興の繰り返しである。覇者である皇帝とその側近を中心としたインサイダー達が別の挑戦者と戦いを続け、負けた場合は挑戦者が次期皇帝となるのである。決して安定的な長期政権が続いた訳ではない。
信頼できるのは家族、あるいは一族だけであった。ところが、財産(多くの場合は土地)は息子全員で相続されていく。決して共有財産でも長子(一子)相続ではない。その結果、土地はどんどん細分化され、大企業を成立させるような社会資本が蓄積されず、どんどんばらばらになってしまうのである。
イタリアについてフクヤマはエドワード・バンフィールドの『送れた社会の道徳基礎』という著書を引用している。「モンテグラーノの精神風土を説明するには、まず個人の家族への従属という問題から始めなければならない。ここでは、大人でさえもいったん家族から離れると、個性というものがほとんど認められなくなる。」「モンテグラーノでは、人に利益を与えるのは、常に自分の家族を犠牲にすることだと考えられている。」(Francis
Fukuyama『「信」無くば立たず』pp164-165)
南部イタリア社会も、極めて家族主義的なことが特徴であり、その象徴がマフィアであろう。家族以外のものが信用できないので、マフィアの中核組織はあるひとつの家族が占めている。また、マフィアは「沈黙の掟」(「血の宣誓」、「鉄の掟」などとも言われているようである)でも有名である。
組織を維持していく上で、当然よそ者も加わることになる。いくら大家族のイタリア人でも必要な人員を家族だけでは揃えられないからである。ただし、マフィアは必ずしもその人物を信頼したから加入を認めるのではない。一旦加入した後は、絶対に足抜けは認めないし、一言でも秘密を漏らしたら、永遠の沈黙が待っているのである。沈黙の掟が有効であると確信しているから部外者の加入も認められるのである。沈黙の掟を通して擬似的な血縁関係を作るのである。
「フランスの民間企業は150年以上もの間、新たな組織形態において先進的立場に立った経験がなく、その規模の大きさや、複雑な生産工程をわが物にする能力などの点で特筆されたこともない。国有化されたり国の助成を受けたりした企業を除けば、最も成功しているのは、比較的小規模な、高級品を扱う消費者市場もしくは専門品市場をターゲットにした家族企業である。」(Francis
Fukuyama『「信」無くば立たず』p187)確かに、高級品メーカーは伝統的に家族的経営が中心であった。それでも、最近はLVMHに見るように、ブランドをキーワードとしたコングロマリットを形成しつつある。また、現在紛争が起こっている地域での活躍が高く評価されている「国境なき医師団」などもフランスから生まれている。高信頼社会へと変貌を遂げるのであろうか。
一方の高信頼社会である日本はどうであろうか。「日本の<イエ>は一般に血のつながった家族を指すが、必ずしもそうであるとは限らない。それはむしろ家の財産の信託のようなものであり、家族構成員が共同で使い、課長はその主要受託者の役割を担う。重要なのは<イエ>が何世代も存続することだ。すなわち、それは管理人の役割を果たしている現行の家族が、かりそめにその場を占めるような構造なのである。しかし、これらの役割が血縁者によって演じられる必要はない。」(Francis
Fukuyama『「信」無くば立たず』p267)日本では、<イエ>を継ぐものとして、外部から養子を迎えることは珍しくなかった。戦後首相を相次いで務めた岸信介と佐藤栄作は実の兄弟であるが、姓が違う。佐藤栄作が佐藤家を継いだからである。岸兄弟は若いころからその俊英を称えられていた。佐藤栄作はその能力を評価されたからこそ他家を継ぐことができたのである。戦前までは、結婚を機に姓が変わることが意外に多かったそうであるが、現在ではほとんどの場合男性側の姓が選ばれている。そこで今度は一気に夫婦別姓の議論が進展している。核家族化とも重なるが、高信頼社会の変質を意味するのであろうか。
ドイツはヨーロッパを代表する自由主義、資本主義の国でありながら、日本が模範とする米国型の資本主義とはかなり異なる形態をとっているのが特徴である。ドイツ人は否定したがるそうであるが、むしろ日本との相似を指摘される。「実際、ドイツと日本の文化の間にある類似性の多さは興味深く、その多くは両国に共通して存在す光度に発達した共同社会的な連帯に起因している。これらの類似性は、数多くの人々によって注目されてきた。清潔な公共の場所や整理整頓された家庭にも見るように、両国はともに秩序と規律では定評がある。両国の社会を構成する人々はともに、喜んで規則に従って行動し、またそれによって、独自の文化集団へ帰属しているという意識を強めている。」(Francis
Fukuyama『「信」無くば立たず』p314)
このような日本とドイツの事例と比べると、高信頼社会の一員としてアメリカがあげられるのは不思議な気がする。アメリカ人は極めて個人主義的であると思われているし、第一アメリカ人自ら個人主義だと思っているからである。
アメリカは多くの人種からなる移民国家であり、この点でも日本やドイツとは大きく異なっている。そのままであれば、悪名高いフランスの個人主義のような社会になってしまう。しかし、アメリカは世界で最初に近代的な大企業を成立させた国である。
アメリカ人は、「一般には個人主義者と思われているけれども、歴史的に見ればアメリカ人は異常なほどに「団体好き」でもあった。自発的に結成された強力かつ長命な組織は数多く、少年野球のリトル・リーグ、農村青年の近代的技術教育を目的とする4Hクラブ、全米ライフル協会、全米黒人地位向上協会、女性有権者連盟など、例をあげたらきりがない」(Francis
Fukuyama『「信」無くば立たず』p395)。確かにアメリカはモザイク国家である。しかし、アメリカでは専制主義が発達しなかったこともあり、人々は分断されていなかった。民主主義のもと、人々が何かを実現するために力を合わせるようになった。前提となる社会の条件は日本やドイツとは異なるものの、結果として高信頼社会を構築できたのである。
5.4安心と信頼
フクヤマは信頼(英語ではTrust)の語を用いている。この点について、山岸俊男は英語では信頼(Trust)の語が用いられている場合、異なったふたつの概念が含まれており、「安心」と「信頼」を区別すべきであると提案している。安心とは、相手の能力に対する期待であり、信頼とは相手の意図に対する期待である(山岸 俊男『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』p35)。
タクシーに乗るのは、運転手を信頼しているからである。しかし、いくらタクシーの運転手を信頼しているからといって、その人物が自分の伴侶としてふさわしいと思っているわけではない。タクシーの運転手としての能力を信頼しているだけである。
逆に、自分の伴侶を信頼しているから浮気などしないと思っている場合はどうであろうか。この場合、自分の伴侶が浮気をする能力を持っていないということを意味するのではない。相手が浮気などしないであろうという、相手の意図を信頼しているのである。
マフィアの沈黙の掟についてはどうであろうか。部下は裏切る意図がない(沈黙の掟によって裏切れるはずがない)からボスはどんな無茶な要求でも通ると思っている。一見信頼が成り立っているようにも思えるが、山岸はこれを安心に分類している。
信頼とは、社会的不確実性が存在する状態、つまり相手が裏切るという選択が可能な状態において相手が利己的にふるまうことはないだろうと期待することである。マフィアの「沈黙の掟」の場合には、事実上相手は裏切ることができない(筆者はなにもマフィア社会においては絶対に裏切りが存在しないというなどということを主張しているのではない。社会的不確実性が少ないということの例証としてマフィアを使っているだけであるのでご了承いただきたい)。社会的不確実性が少ないのである。この場合存在しているのは「安心」であるとしている。
相手を信頼して何かを依頼する場合、相手に付け込まれ、何らかの不利益が発生する可能性がある。もし相手を信頼して行動しても、自分が何らの不利益も負わない社会的不確実性のない状態では、なにも信頼などは必要ない。
このような観点から考えると、社会的均質性の高い日本において存在しているのはどちらかというと「安心」であり、アメリカでは「信頼」であるともいえるであろう。しかし、日本においても社会的均質性は過去の伝説となりつつある。また、日本に限らず現代社会はネットワーク化しつつある。
以上の議論から、すっぱいレモンの場面、あるいは共創社会で必要とされるのは、相手の意図に対する期待としての信頼であることが分る。
5.5信頼とコミットメント
社会的不確実性が存在する場合、人々は少しでもその不確実性を減少させようとする。マフィアの沈黙の掟を課そうとする場合もあるかもしれないが、それは例外である。通常は、取引の相手と信頼関係を強めようとする。企業と顧客の関係において、企業側から見ても、顧客側から見ても、この信頼関係を強めようとする動機は同じである。安定的な取引を望んでいるのである。
山岸
俊男は「社会的不確実性はコミットメント形成を促進する」、「社会的不確実性と一般的信頼のレベルが同じであれば、日本人参加者とアメリカ人参加者の間には、コミットメントを形成する傾向に差が見られない」という2つの仮説を検証するために、ゲーム理論に基づく環境を実験的に作り出し、資料3のような実験を行っている。
現実社会では完全にゲーム理論的な環境というのは考えにくい。実験室内でゲーム理論的な環境を作り出すことによって、不確定な要素を排除し、信頼に係る人間の行動を純粋に抽出しようというものである。実験からは、いくつもの興味深い結果が明らかにされている。
実験から明らかになったのは、社会的不確実性が大きいほど、人々が特定の相手との間でコミットメント関係を形成する傾向が強いという仮説1が成り立っていると同時に、社会的不確実性と一般的信頼のレベルが同じであれば、日本人参加者とアメリカ人参加者の間には、コミットメントを形成する傾向に差が見られないという仮説2が成り立っていることである。
この実験の結果は意外であろうか?確かに、経済活動においても阿吽の呼吸が要求されるインサイダー大国の日本と、何事につけ分厚い契約書を交わさなくては安心して取引しようとしないアメリカ人が、ある程度の条件をコントロールすると、見事に極めて似通った反応を示すようになるというのは、意外かもしれない。しかし、このことは、日本人とアメリカ人が経済活動(あるいは社会一般の活動)で見せる違いは、日本人とアメリカ人がもって生まれた性質の差を表しているのではなく、両者が置かれている社会的条件、両者が社会や他人に対して抱いている安心の度合いによってもたらされていると考えれば、納得がいくのではないだろうか。
それでは、仮説1に示された点はいかがであろうか。
社会的な不確実性が大きい、つまり価格条件などだけをもとにして取引相手を変えてしまうことは危険が多いとして、信用できる取引相手との取引の方を重視するのは、特に不思議な経済行動とは言えない。
それだけでなく、自分をだますような取引先とは取引をしなくなることは、21回目からの取引において、新しく参入した売り手を信用しなかったことからも明らかであろう(ただし、このことは<資料2>の実験では直接的には示されていない。続く実験で同じ取引相手を選ぶかどうかの実験を行っている)。
しかも、裏切り行為に対しては、日米において全く同じように信頼関係を損ねることが示されている。
企業と消費者の関係に置き換えてみると、消費者を裏切るような行為を行った企業を、消費者は忌避するようになることを示している。それだけではない。実験ではCという売り手が「巻き上げチャンス」を利用しただけで、その後マーケットに参入してきた、つまり信頼できるかできないかまったく分らない新規参入者に対しても、消費者はマイナスイメージを持ってしまう。その結果、新規参入者は市場の支持を得ることが難しくなってしまうのである。
また、そのような行動をとったため引き起こされたダメージは、その企業だけに向かうのではない。ちょうど、消費者の信用を失うような行動をとった企業が現れた結果、業界全体がダメージを受けることがある。最近の事例では、BSE騒動に端を発する食肉偽装事件などがあげられるであろう。実際に食肉偽装事件を引き起こした企業以外にもボロボロと同種の事件が重なったこともあるが、食品業界全体に対して不信の目が向けられることになった。また、BSEに関しては、食用牛に対して全数検査が行われるようになった後も、初期対応のまずさから引き起こされた不信が尾を引いて、焼肉屋がしばらくはがらがらになってしまった。
このことは、資料4に示される、山岸 俊男の実験における低信頼者の16試行目から32試行目までの行動によって裏付けられるであろう。
つまり、今まで「安心」して食品を買っていたのがその安心感が壊されてしまった。その結果不信感のみが残ってしまい、業界全体のイメージが傷つき、不祥事に係らなかった企業側の積極的な働きかけにも応じなくなってしまっているのである。
また、この実験からは、信頼に関する別の側面も明らかにされている。
それは、社会一般に対する信頼度の高い高信頼者とは、無条件に相手を信頼してしまう「お人好し」ではないということである。むしろ、相手が信頼できるかどうかに対して敏感で、相手の行動から得られた情報に対して積極的に反応を示す人物なのである。
社会的不確実性の高い環境に置かれた場合、低信頼者は「安心」に寄りかかろうとする。従って、以前から取引があるなどの安心材料がある環境の内にこもろうとする。外部者に対しては「人を見たら泥棒と思え」といった対応に陥りがちである。従って、「安心」が崩れると一気に不信の塊になってしまうのである。
これに対して高信頼者は社会的不確実性の高い状況に置かれても、相手の信頼性を的確に判断できる人間は、低信頼者に比べて、相手が信頼できると思えば協力し、信頼できないと思えば協力しないといった柔軟な対応が取れる。そうであればこそ、「人を見たら泥棒と思え」と決め付ける必要もないのである。
5.6評判の重要性
社会がネットワーク化している現状においては、企業の社会的評判も考慮しなくてはならないであろう。上記のゲームでは、売り手が「巻き上げチャンス」を利用してことを知っており、なおかつその情報を利用できるのは買い手として参加した参加者だけであった。
しかし、現実の経済活動においては、ひとりの人間に対して「巻き上げチャンス」を利用したならば、それがその他市場参加者へも伝達されることを覚悟しなくてはならない。
不祥事に対しては、市場は大変厳しい判断を下す。自らの責任を棚に上げて流言飛語の責任にしていると、とんでもない結末が待ち受けている。このことは、最近話題となっているさまざまな事件が物語っているところである。
それでは、企業はいかなる行動をとればよかったのであろうか。食品会社はただ単に偽装工作をしなければよかったのであろうか。ただ単に顧客至上主義を掲げていればよかったのであろうか。
断じてそのようなことはない。企業のなすべきことは、社会に対して信頼の存在を発信していくことでなければならないのである。
6.共創社会における信頼
社会において信頼は必要とされるものなのだろうか。なぜ信頼を得るような行動をとらなくてはいけないのであろうか。それが「正しい」行動だからだ、という倫理的な価値基準を持ち込むことも可能である。しかし、現在の世の中は、ネットワーク化している。即ち、価値基準も多極化しているのである。その中で、倫理的な基準だけをもってすべての人間に対する価値基準とすることには無理がある。それでは、どのような原理に基づいて信頼は必要とされるのであろうか。
6.1社会的知性としての信頼
山岸の主張するとおり、信頼に基づいた社会は、お題目として「信頼感の醸成」を唱えていても始まらない。
現在、日本では地域社会の崩壊が危惧されている。これは、なにも日本に限ったことではなく、アメリカ社会においても信頼の崩壊を危惧する声は高まっているという。また、信頼に関する研究や学術会議も頻繁に開かれるようになっているそうである。その表れが前述のフクヤマの著作である。
確かに、インターネットを代表とする現在のネットワーク社会を存立させている技術は、旧来の社会秩序に対して大きな変革を迫るものであった。しかし、それは単に従来の価値観を打ち壊すものではない。
安心と信頼の項でも触れたことであるが、われわれがいくら信頼感に裏付けされた社会であると思っていても、それが実は仲間内だけのコミットメントに基づく安心を基礎とした社会だったのである。アメリカも、建国の理想に燃えて人民が平等である社会の建設を目指したのであろう。最近では、アメリカの独立は独立「革命」であると認識されているようである。つまり、それ以後に続くフランス革命など欧州における革命の最初の一歩になったと認定されているのである。
しかし、最初は人民の信頼に基づく社会であったとしても、次第に内向きの理論が優先し、マフィア世界の「沈黙の掟」にも似た仲間内のコミットメントを中心とした世界に変質してしまったのではないだろうか。最近のアメリカの国際社会における行動は、このことを端無くも暴露しているのではないだろうか。
しかし、現在信頼に基づく社会が崩壊に瀕しているからといって、そのことがネットワーク社会においては信頼が不要であることを意味しているのではない。逆に、ネットワーク社会を成立させるのは、実は社会的、一般的信頼の存在なのである。
「この一般的信頼の育成にあたって、社会的知性によって一般的信頼が裏打ちされていることを認識することの重要性である。しかし同時に、一般的信頼の育成のためには社会的知性だけでは限界があるという点を、本書の最後に強調しておきたい。開かれた社会の基盤としての一般的信頼の育成のためには、ザッカーが述べているように、関係に依存しない普遍的な原理に従った効率的で公正な社会・経済・政治制度を確立する必要がある。効率的で公正な制度を確立できれば、機会コストが増すにつれ、社会的知性と信頼と信頼性のセットが有利な特性セットになっていくはずである。そうなってはじめて、お説教やかけ声では達成できない、開かれた社会の基盤が自ら生まれるようになるだろう。それは、他人を信頼する正直者が馬鹿を見ない、そういった人たちが得をする社会である。」(山岸
俊男『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』p202。文中ザッカーとは、Zucker,
L. 1986 Production of trust: Institutional sources of economic structure,
1840-1920. Research in Organization Behavior, 8, 53-111を示す)
ネットワーク社会においては、ひとつの大きな組織が永続するということはない。むしろ、小さなセル(細胞)が自在に形を変えながら、そして、様々なセルと集合離散を繰り返していくのである。従って、ネットワーク社会は、機会コストの高い社会であるといえるだろう。つまり、仲間内の取引に安住するのではなく、外部に開かれたネットワークを使って積極的に新しい関係を築いていった方がより大きな成果が期待できる社会なのである。そのようなダイナミックな活動を支える社会には、社会的信頼の存在が不可欠である。
もし、社会的な信頼が欠如していたとしたら、ネットワークは広がっていくことはできない。ネットワークの交点となるべきセルから別のセルとの交流は生まれず、バラバラのままである。
6.2信頼すると信頼される
マフィアの世界のような閉ざされた社会においては、信頼ではなく、「沈黙の掟」を基にして社会が成り立っていることは前述のとおりである。
しかし、このような閉鎖社会では、外部との交流もなく、社会の発展性に乏しいことは明らかである。そのような低信頼社会の発展性の乏しさは、フランシス・フクヤマの『「信」無くば立たず』に明かにされているところである。別な言葉で言えば、外部との取引をしないことによる機会コストがコミットメントによって得られる利益を上回ってしまうのである。
現在の社会はネットワーク社会という、あらゆる方向に対して開かれた社会になっている。ネットワーク社会になることが有利であるとか、その方が効率的である、といった理由に基づいて主体的に選択したというよりは、さまざまな要因によって社会はそのような方向に変化してしまった、という方が正しいのであろう。
そのような環境の中で、人々は今までのコミットメント関係を離脱して、新たなパートナーを探さなくてはならない。その場合に、自らが信頼できる相手を探すのはもちろん、自らが相手に信頼されなければ、取引関係が成り立たない。自らが信頼に値する行動をとっていなくては、相手に選択してもらえないのであるから、相手が信頼できるかどうかは問題にならない。
現在産業界では、コンプライアンス体制の確立があらゆる業界において問題になっている。ある一面においては、現在の社会が大変不安定になってきたことの裏返しとして社会的安定(コミットメント関係)を求めるためにそのような要求があるのかもしれない(今も昔も「昔は良かった」という慨嘆が聞かれるようである)。
しかし、社会の変化が外部的な要因によって必然的にもたらされたものであるならば、そのような社会的変化に対して対応することが必要とされるのではないだろうか。企業と顧客の考えてみればどうであろうか。ネットワーク社会においては、人々は信頼を求めている。その際、信頼という社会的知性は大きな武器となるのではないだろうか。
良く言われることであるが、顧客の信頼を裏切るのは簡単であるが、信頼を作り上げることは難しい。なぜならば、信頼は企業の都合で作り出せるものではなく、顧客の内にあるからである。顧客の内にある企業に対する信頼を高めるには、企業が自らを信頼に値することを証明し続けなくてはならない。一度でも顧客の信頼を裏切ってしまえば、またゼロから(場合によってはマイナスから)始めなくてはならない。
それでは、企業はどのようにすれば顧客に信頼を与えることが可能なのであろうか。
6.3信頼の発信
以上の議論から明らかかにされたように、ネットワーク社会を成立させるためには信頼が必要である。前述のコーペティションにしても同じである。もし、抜け駆けが許され、それが正当化されるような社会であれば、コーペティションは成り立たない。逆に、そのような抜け駆けを許さない、正直者が馬鹿を見ないような社会を作り出さなくてはいけないのである。
そのような価値観が備わって始めてネットワーク社会が共創社会といえるようになるのである。
コンプライアンスとは、まさにこの社会的知性である信頼の発信に他ならないのである。コンプライアンスは、自らの会社が顧客に選ばれるためだけに行われるのではない。顧客が、安心して経済活動を行えること、あるいはそのような信頼を社会に対して抱くことを可能にする社会を作り出すために必要な行為なのである。さらに、このような社会的信頼を生み出す行為はなにも企業にのみ求められているのではない。信頼すると信頼されるの章で明らかにしたとおり、信頼とは他者との関係の内に生まれてくる。
現在、金融界は護送船団方式により国家が何でも保証してくれた時代は終わり、自己責任の時代に突入している。これは、金融界にとどまらない、今後の経済活動全般に当てはまる基本方針であろう。企業側にコンプライアンスの確立が求められる一方で、消費者にも共創社会の一員として責任を分かち合うことが求められるようになっているのである。
我々全てが必ずしも企業あるいは生産者としての立場を持っているとは限らないが、我々全てが消費者としての立場は持っている。そして、消費者は消費活動を通じて企業や生産者に影響を与える立場にある。共創社会においては、消費者も生産者と同様に重要な社会の構成員なのである。
共創社会の構成員はすべて信頼を発信し続けなくてはならない、などというとお説教じみたお題目に聞こえてしまう。しかし、ネットワーク化した社会においては、社会的信頼がなければ社会そのものが成り立たないのである。
ネットワーク社会を成立させるために社会的信頼が必要であるのならば、企業は自ら信頼を発信し続けなくてはならないのである。
7.結論
功利的な基準のみで人間の行動が決まることを前提としているようなゲーム理論も、現実に即した様々な制約を盛り込むことによって、現実社会に起こる様々な事件を大変効率よく説明できることが明らかにされた。
また、コーペティションのような協力的ゲーム理論もその延長線上で理解されることも明らかになった。
しかし、功利的なゲーム理論だけでは、いかにすれば囚人のジレンマを回避できるかは明らかにされなかった。社会的に好ましい状態が他にあったとしても、ゲーム理論からは大変不安定な状態であることが明らかにされてしまう。不安定な状態はゲームを変えない限り安定的、恒常的な状態とはならないのである。
そこで、コーペティションなど、協調を前提とするゲームを説明する場合には、「信頼」というキーワードを持ち込むことによって、なぜそのような条件が選ばれるかが明確に位置付けられた。特に繰り返しゲームの場合には、従来からの取引実績がある(信頼感がある)取引先を選ぶと言う大変一般的かつ穏当な結論が導き出されることになった。
次に、信頼の中味を検証すると、英語ではTrustの一語で表される信頼も、実は相手の能力に対する期待としての安心と、相手の意図に対する期待である信頼とに分かれることが明らかにされた。
フクヤマの著作に見られるように、社会的信頼の度合いは国、地域によって多様に異なっている。しかし、山岸の実験からは、社会的不確実性をコントロールすることによって、少なくとも日本と米国の間では同じ信頼度を持つ実験参加者の間では、社会的不確実性に対する反応にほとんど差がないことが示された。むしろ、明確に差があるのは、低信頼者と高信頼者間の行動の差である。ネットワーク社会では、安心が不信に変化すると「人を見たら泥棒と思え」と決め付けてしまう低信頼者より、社会的不確実性を確実にコントロールできる高信頼者の方がより適していることは言うまでもないだろう。
そして、信頼関係とは、相手がいて初めて成り立つものである。一方的に自分が相手を信頼したとしても、相手が信頼してくれなくては、関係が成り立たない。そこで、相手の内に自分に対する信頼感を醸成しなくてはならない。そのような信頼感を醸成する方法は唯一、自らの行動を通じて示す方法しかないのである。
ネットワーク社会は広く外部に開かれた社会である。しかし、その特性も社会的信頼が存在して初めて活用され得るものなのである。
以上から、ネットワーク社会とは必然的に信頼に基づく共創社会でなくてはならないことが判明したのである。
<資料1>みずほ銀行システム障害
「(4/3)3行主導権争いも響く・複雑なシステム、統合準備遅れる
第一勧業、富士、日本興業の3行の再編で1日に発足した個人・中小企業向けの「みずほ銀行」の大規模なシステム障害は、発生から丸1日たった2日朝になってようやくほぼ復旧した。開業初日の混乱の背景には、システム面の準備不足とともに、統合をめぐる3行の主導権争いもある。
銀行界にはみずほ銀の発足前から「システム不良が発生する可能性が高い」との観測があった。その根拠は、みずほ銀の複雑なシステム統合計画だ。みずほ銀は、一気にシステム統合をせず、まず3行のシステムを中継コンピュータを通じて相互接続する方式を選んだ。完全な統合は1年後をメドに第一勧銀のシステムに集約する2段階の計画だ。
この背景には経営統合前の主導権争いがある。第一勧銀と富士銀が自行システムへの集約にこだわり、最終的な統合システムの青写真をつくるのが大幅に遅れた。発表から実際の経営統合までの2年以上の準備期間も十分に生かせなかった。計画作りに時間がかかり、接続試験などの準備が不足したまま本番を迎えることになったようだ。
みずほ銀のシステムの完全統合にはまだ1年かかる。みずほ銀は「再発防止に万全の態勢をとる」としているが、そのためにはまず組織内固めが必要との声がグループ内でもあがっている。」
日本経済新聞
NIKKEI NET 2002年4月3日
(http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt26/20020405kr545001_05.html (2002/04/08))
<資料2>強かったのはお返し戦略
「アクセルロッド(R.
Axelrod)は、囚人のジレンマ型ゲームの繰り返しに関して、いろいろな戦略のコンピューター・プログラムを競わせる選手権を開催しました。様々な分野の研究者から14通りのプログラムの応募があり、それに、毎期まったくランダムに「協調」と「裏切り」を選ぶプログラムを加えた15通りのプログラムの総当りリーグ戦が行われました。
この選手権で最もよい成績をおさめたのは、ラポポート(A.
Rapoport)によるtit for tat戦略でした。tit for tat戦略というのは、まず第1期は「協調」をとり、第2期以降は相手が前の期にとったのと同じ選択肢をとる、つまり前の期に相手が「協調」をとっていれば「協調」を、「裏切り」をとっていれば「裏切り」をとるという単純な戦略です。訳語はいくつかありますが、本書ではお返し戦略と呼ぶことにします。アクセルロッドは、この選手権の結果を公表したうえでもう一度選手権を開催しました。第2回選手権には第1回を上回る参加者があったのですが、ラポポートは再びお返し戦略で参加し優勝をしてしまいました。
さらに、アクセルロッドは、架空の選手権を何回も繰り返し行っていくシミュレーション実験を行いました。ただし、毎回の各参加プログラムの数を前回の成績に比例して決めました。よい成績をおさめたプログラムは数が増え、悪い成績のプログラムは数が減ります。その結果、お返し戦略のプログラムは常に最も多く、しかも最後まで増加しつづけました。
このように、自分からは裏切らず、相手が裏切れば即座に報復し、相手が協調に戻ればただちにこちらも協調行動に出るというお返し戦略が、選手権で優勝し、さらにシミュレーション実験から長期にわたってその勢力を増大していくこともわかりました。この結果は、われわれが社会においてとるべき行動にたいしても大きな示唆をあたえるものといえるでしょう。」
(武藤 滋夫『ゲーム理論入門』p109)
<資料3>山岸
俊男の行った実験---信頼とコミットメント
実験対象は日本人学生100人とアメリカ人学生100人。
実験参加者はひとりずつ小部屋に入ってパソコンを相手に実験を行う。他の参加者と顔を合わせることはない。
参加者はまず、「くじ引き」で売り手か買い手のどちらかになることを決める。この「くじ引き」には仕掛けがあり、すべての参加者は買い手になるように設定してある。
参加者には500円(アメリカでは1ドル100円換算で計算されたドル額)が取引の元手として渡され、売り手から商品を仕入れ、その商品を実験者に転売する取引を行う。転売価格より高い値段で仕入れた場合には損失となる。このようにして行われた取引の結果残った金額が報酬として参加者に支払われる。
買い手は1回の取引について、2人の売り手のどちらかから商品を仕入れて転売する。買い手は「くじ引きで」AとCの売り手が割り当てられる。参加者には知らされていないが、AもCも実際はコンピュータ・プログラムである。
また、買い手は2人の売り手のうち、どちらかから商品を仕入れることになっているが、売り手も2人の買い手を相手にしているように設定されている。あまり買い手がもたもたしていると、いずれの売り手からも商品は別の買い手にいってしまい、その回の取引における参加者の収益はなくなってしまうようにセットされている。
標準的な商品の価値は140円に設定されているが、売り手にも商品の大まかな品質しか分らないことになっている。従って、売り手は大体の見当で値段を提示してくるとされている。また、買い手も実験者に転売するまでは、いくら利益を上げられたか損をしたかは分らない。実際には、最大50円の利益、10円の損失の範囲で変化するようにプログラムされており、売り手の行動はAとCで異ならない。
この実験には、社会的不確実性の代用品として売り手には「巻き上げチャンス」が与えられている。売り手は、1回の取引が終了するたびに何分の1かの確率で「巻き上げチャンス」が与えられる。売り手は巻き上げチャンスを利用するかしないかを決定する。利用することにした売り手は、1回目から7回目の取引の後では120円、8回目から14回目は190円、15回から20回目は250円を買い手から巻き上げる。売り手には20回の取引のうち、2回「巻き上げチャンス」が与えられるようにプログラムされている。
AとCはこの「巻き上げチャンス」の利用において差がつけられている。Aはこのチャンスを積極的に利用するのに対して、Cはチャンスを与えられてもそのような搾取的な行動は慎むようにプログラムされている。
20回の取引の後、売り手Aは別の売り手Fと交替する。21回目からの取引においては、買い手はCとFのどちらかから商品を仕入れて実験者に売り渡さなくてはならない。Cは「巻き上げチャンス」を利用しない、安心できる相手であることは分っているが、Fは実はCより安い値段で商品を提供するようにプログラムされている。
21回目からの取引において、「巻き上げチャンス」が存在している場合と存在しない場合の2通りの実験が行われ、参加者にはその旨伝えられる。また、巻き上げられる金額は400円に引き上げられている。
結果
実験の結果は図<資料3>に示されている。図は、売り手がAからFに交替した後に行われた10回の取引のうち、何回以前取引をしたことがあり「巻き上げチャンス」を利用しなかったCと取引したかを示している。
FはCよりも安い価格を提示しているのであるから、もしFが信頼できる人間であると分っているのであればFと取引するのであろう。ところが、不確実性が大きい場合には、多くの参加者が、値段が割高なCとの取引を選んでいる。
不確実性大と不確実性小の間の差は、統計的に有意な差であるとの結果が出ている。逆に、日本人とアメリカ人の行動は、同じ不確実性大の場合でも、多少の差があることが分る。ただし、この差は統計的に有意な差ではない。
図<資料3>
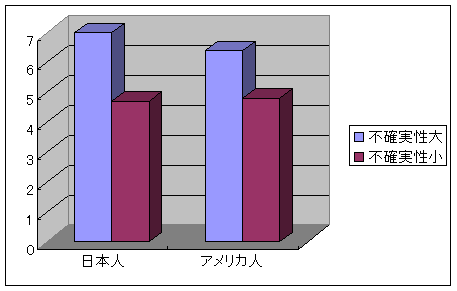
(出典 山岸 俊男『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』p122、ただし、グラフは著作からスキャンして読み込んだものではなく、Excelで書き直したもの。)
以上の結果は、社会的不確実性が大きいほど、人々が特定の相手との間でコミットメント関係を形成する傾向が強いという仮説1が成り立っていると同時に、社会的不確実性と一般的信頼のレベルが同じであれば、日本人参加者とアメリカ人参加者の間には、コミットメントを形成する傾向に差が見られないという仮説2が成り立っていることを示している。
(山岸
俊男『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』pp115〜123)
<資料4>山岸
俊男の行った実験---高信頼者と低信頼者
高信頼者と低信頼者とは、山岸 俊男が開発した信頼感尺度を用いて個人の特定個人に対する信頼度ではなく、社会一般に対する信頼度が高いか低いかに基づいて区分けしたものである。高信頼者のほうが、一般的に低信頼者より、社会一般の人々は正直であり、善良であると信じている度合いが高い。ただし、高信頼者とはだまされやすいお人好しのことではない。高信頼者のほうが、取引相手などのネガティブな情報には強く反応するなど、情報感応度が高いという。
<実験の内容>
実験は日本人学生80人に対して行われた、依存度選択型囚人のジレンマ実験である。
与えられた利得のマトリックスは以下のとおり。
表<資料4>
|
|
相手の選択 |
||
|
A |
B |
||
|
自分の選択 |
A |
自分10円/相手10円 |
自分-30円/相手30円 |
|
B |
自分30円/相手-30円 |
自分-10円/相手-10円 |
|
ふたりの参加者同志の間で、囚人のジレンマのゲームを繰り返し行う。実験は48回行われるが、その回数は参加者には知らされていない。また、相手が誰かは分らない。
参加者には500円が全員に渡されており、実験の結果の利得を500円に加減した金額がお礼として支払われる。
さらにこの実験では、上の表で与えられたマトリックスの利得を参加者は変化させることができるようになっている。1回の実験が終わるたびに、利得の1/10(比率ではなく、10の利得に対しては1、30の利得に対しては3)を加減できる。その場合、加減の方向はもとの利得の方向と同じ、つまり、プラスを増やすと、マイナスも同時に増える。1/10の増加を決定した場合、自分の利得は、11、33、-11、-33になる。利得を増加させると、自分のプラスも増加する変わりに、相手が協力してくれなかった場合のマイナスも増加してしまう。
<結果>
実験参加者は自分の利得を加減できる。相手が信頼できると思えば利得を増大させ、信頼できないと思えば減少させるであろう。
図<資料4-1>
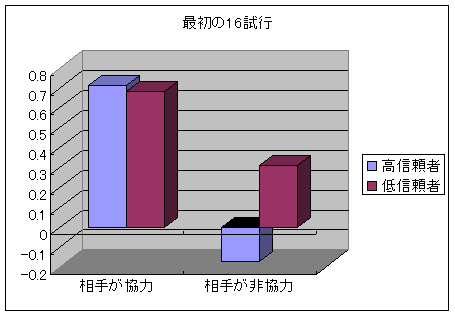
最初の16試行の結果が上図に示されている。相手が協力してくれた場合には、高信頼者も低信頼者も同じように利得の大きさを増加させており、その選択には統計上の有意な差はない。ところが、相手が非協力を選んだ場合の行動には、大きな差がある。高信頼者は利得を引き下げている(平均-0.17)のに対して、低信頼者は相変わらず利得を増加させている(平均0.31)。この差は統計上有意である。
高信頼者の方が、得られた情報(相手が非協力を選んだこと)に対して敏感に反応していることがわかる。
ところが、続く17試行目から32試行目の結果は面白い変化をしている。
図<資料4-2>
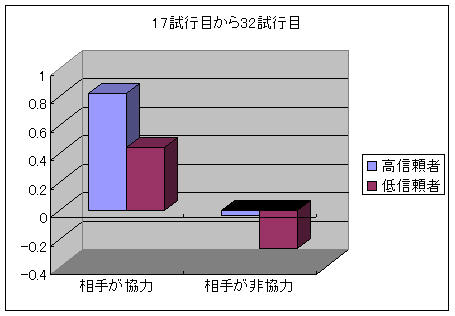
低信頼者は「羹に懲りて膾を吹く」の例えどおり、今度は相手に協力するのを躊躇する行動に出ている。これに対して、高信頼者は1試行目からのときと行動パターンに大きな差はない。
さらに33試行目から48試行目まででは、今度は低信頼者も十分に教訓を得たのであろうか、低信頼者と高信頼者の間では差は目立たなくなった。
(山岸
俊男『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』pp162〜168、グラフに関しては1試行目から16試行目までのものが引用文献中に掲載されている。ただし、図<資料4-1>は著作からスキャンしたものではなく、Excelで再構成した。図<資料4-2>は本文中の数値をもとに再構成した。)
参考文献
Adam
M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff (1997), Co-opetition,
Adam M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff, (嶋津 祐一・東田 啓作訳(1998)『コーペティション経営』日本経済新聞社)
Francis
Fukuyama (1995), TRUST, Francis
Fukuyama (加藤 寛訳(1966)『「信」無くば立たず』株式会社三笠書房)
武藤 滋夫(2001)『ゲーム理論入門』日本経済新聞社
小倉 昌男(1999)『経営学』日経BP出版センター
William
Poundstone (1995), PRISONER’S DILLEMMA,
Doubleday, (松浦 俊輔訳(1995)『囚人のジレンマ』青土社)
鈴木 一功監修 グロービス・マネジメント・インスティテュート編(1999)『MBA ゲーム理論』ダイヤモンド社
高橋 俊介(1998)『人材マネジメント論』東洋経済新報社
高橋 俊介(2001)『組織革命』東洋経済新報社
Jack
Welch, John A. Byrne (2001), Jack Straight
from the Gut, John F. Warner Books, (宮本
喜一訳(2001)『ジャック・ウェルチ
わが経営』日本経済新聞社)
山岸 俊男(1998)『信頼の構造―――こころと社会の進化ゲーム』東京大学出版会